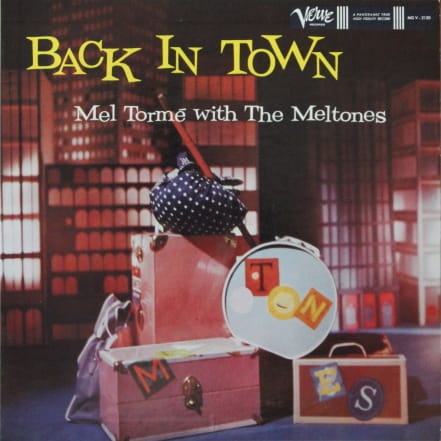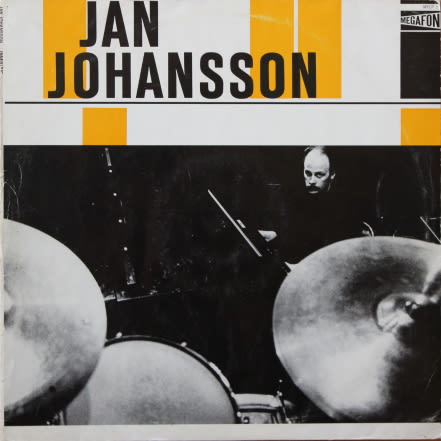Clifford Brown With Strings ( 米 Emercy MG 36005 )
バックの弦楽団のサウンドがまずくて、アルバムトータルとして足を引っ張ってしまっているのがとても残念だ。 ヴァイオリンが6人、ヴィオラが2人、
チェロが1人、という意味のあまりよくわからない構成がとにかくまずい。 この高音域帯に偏った弦楽アンサンブルとトランペットという高音域楽器の
サウンドが完全に被っていて、トランペットの演奏がまったく映えないことになってしまっている。 これは完全にアルバムプロデューサーの失敗だ。
よくパーカーのウィズ・ストリングスのバックの演奏がダサい、と言われるけれど、私はそうは思わない。 あちらは弦楽器の各帯域のバランスが良く、
オーボエやハープが幻想的な効果を割と上手く出していて、背景音楽としてはよく出来ていると思う。 ところがこのブラウニーの方はニール・ヘフティの
ポップでわかりやすいアレンジが全然表現できておらず、軸が壊れて曲がってしまったスツールに腰かけているような座り心地の悪さがどうにもまずい。
チェロをもっと増やすか、コントラバスを入れるかして、低音域に厚みと深みを持たせて欲しかった。
更に、エマーシー独特の奥行き感の希薄で二次元的な音場感が、弦楽のアンサンブルとトランペットの音の分離の悪さを助長している。 トランペットの
音自体は生々しく音圧高く録れているのに、音場の中でバックの弦楽隊との距離感を作れていないので、どの楽器の音も同じように前に飛び出してきて、
ブラウニーの演奏の凄みがうまく体感できないのだ。
そのブラウニーは、この時24歳。 それが信じられないような楽器コントロールと歌心を発揮している。 とにかく弱音箇所でも音が100%出切っていて、
ロングトーンも不安定な音の揺らぎは一切なく、上品なヴィヴラートとのバランスもよく、こんな演奏をできた人は後にも先にいない。 音色も金属的な
響きはまったくなく、本当に人が歌っている声を聴いているようなところも、この人だけのものだ。 "Embraceable You" や "Portrait Of Jenny" での
メロディーの歌わせ方は特に素晴らしくて、1度聴いたら忘れられなくなる。 どの曲もアドリブラインが一切なくメロディーを吹き流しているだけなので、
ジャズとしての面白味は皆無でそういう意味では退屈な内容だけど、これはアルバム制作上のコンセプトの問題だからそこを突いても仕方がない。
だから、殊の外、構成や音作りへの不満が強く残るのだ。 ジャズだからトランペットの演奏さえよければそれでいいじゃない、とはならない。
大学できちんと教育を受けたインテリらしく、どちらかと言えば制御系のトランペッターだったから、この後の展開がどうなっていくかをみんなが愉しみに
していたのに、道半ばで途絶えてしまったのは残念だ。 トランペットがサックスの後塵を拝してきたのは、この人を失ったからかもしれない。