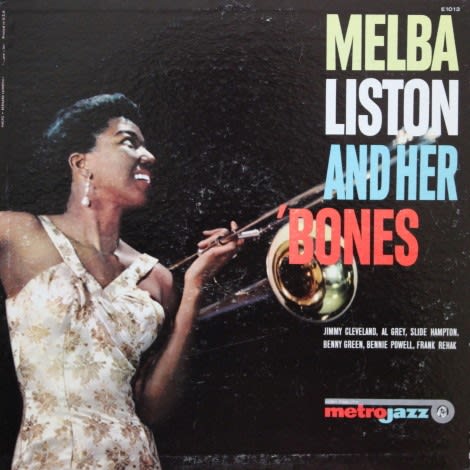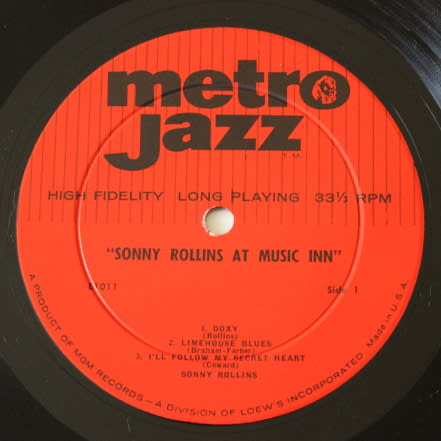The Jones Brothers / Keepin' Up With The Joneses ( 米 MetroJazz E1003 )
サド、ハンク、エルヴィンの3兄弟にエディー・ジョーンズを加えたワンホーン・カルテットがアイシャム・ジョーンズやサドの楽曲を
演奏する、というジョーンズ尽くしの洒落の効いたアルバム。単なるおふざけアルバムのように思われているかもしれないが、
私が最も好きなサド・ジョーンズのアルバムがこれである。
トランペットやフリューゲルホーンを持ち替えながらサドのプレイが最も堪能できるのがこのアルバムのいいところだ。
プレーヤーとして評価されることのない彼の演奏力がこんなにも素晴らしいということがとてもよくわかる。
アイシャム・ジョーンズは20世紀前半に活躍したミュージシャンで、"It Had To Be You"、"On The Alamo"、"There Is No Greater Love"
のような陽気なスタンダードを書いた人。サドはゴリゴリのハード・バップをやるようなタイプではないので、そういう意味でも
アイシャムの書いた曲は彼の音楽性に親和性がある。
ハンク・ジョーンズの上質なピアノが全編に渡って効いており、全体が非常に上品なジャズに仕上がっている。
エルヴィンのブラシが音楽を心地よく揺らしており、素晴らしい。全体的に音数が少なく、隙間感で聴かせる音楽になっている。
おまけに、このレコードは物凄く音がいい。ひんやりとした広い空間の中で、輪郭のくっきりとした彫りの深い楽器の音が心地いい。
内容、音質とも深い満足感に浸れる素晴らしいレコードである。