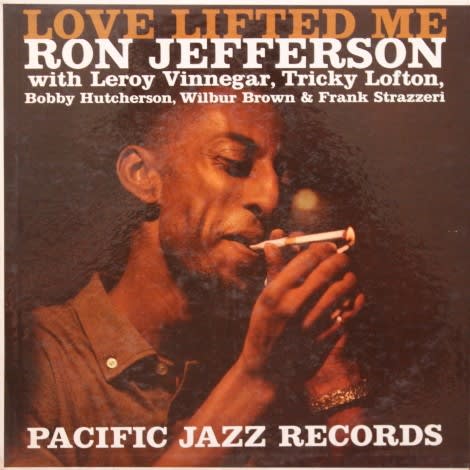Bud Shank / Bud Shank Plays Tenor ( 米 Pacific Jazz Records PJ-4 )
バド・シャンクのレコードはたくさん残っていていろいろ聴いてきたが、いいと思えたアルバムは非常に少ない。アルバム作りが下手だったという
ことなんだろうけど、そんな中でこのアルバムは出来がいいと思った数少ない一枚。
まず、楽器の持ち替えをせず、サックス1本でじっくりと吹いたところが何よりいい。正直言って、この人のフルートには良さは何もないと思う
けど、本人は気に入っていたのか、アルバムの中で多用した。でも、これが聴いていてまったく面白くない。早く次の曲に行ってくんねえかな、
と思いながら聴くことになり、面白くないからそのアルバムは聴かなくなるのだが、このアルバムにはそれがない。
そして、意外にもテナーの演奏に味わいがある。音色はズート・シムズに似ていて、フレーズはスタン・ゲッツによく似ている。イメージしやすい
ように説明するとそういうことになるが、それらの物真似をしているということではなく、この人独自の個性として演奏によく表れている。
音色に深みがあり、リズムによく乗る演奏で素晴らしいと思う。ズートやゲッツのワン・ホーンアルバムを聴いた時と同様の満足感が残る。
バックのトリオは当時の常設メンバーで "Quartet" と同じだが、こちらの演奏は悪くない。クロード・ウィリアムソンも別人のような陰影感のある
演奏をしており、音楽全体が上質な仕上がりになっている。このアルバムはワン・ホーン・テナーの傑作と言っていい。
でも、それがアルト奏者だったはずのバド・シャンクのアルバムだと言うところがなかなか複雑なのである。たくさんのアルバムを作る機会があり、
実力も十分あったはずなのに、なぜアルトでこれが出来なかったのかと文句の1つも言いたくなる。これは57年の録音で、彼は60年代に入っても
アルバムを作ったがイージーリスニングの色が濃くなり、ジャズの主流からは遠のいていく。渡欧せずアメリカに残って音楽で食っていくには
そうするしかなかったわけだが、おそらくそれは本意ではなかっただろう。50年代後半のごく限られた短い時期にどれだけの傑作を残せたかで
その後の評価が決まったこの世界で決定打が出なかったのは何とも惜しいことだった。