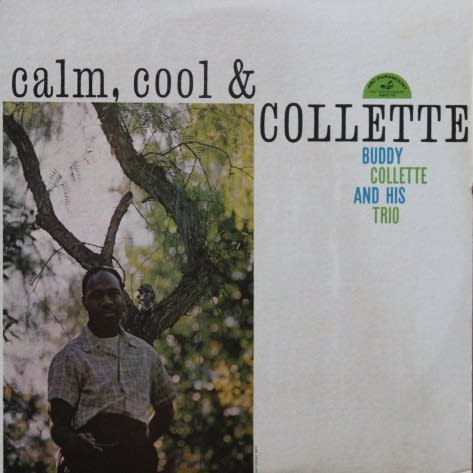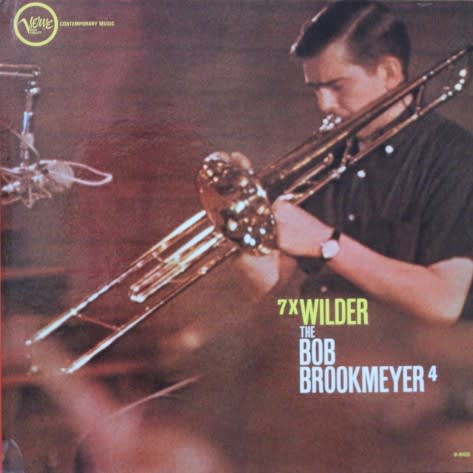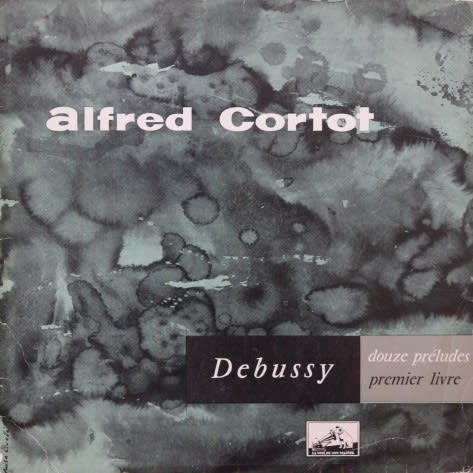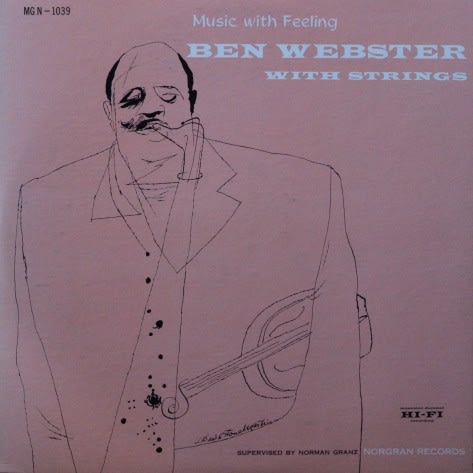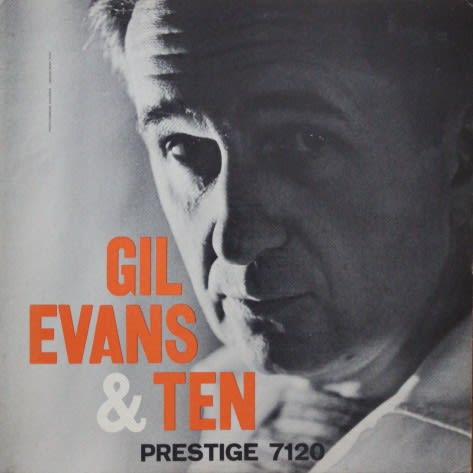

Gil Evans / Gil Evans & Ten ( 米 Prestige PRLP 7120 )
このアルバムを聴くと、写真でしか見たことのない50年代のニューヨークのモノクロの街並み、風景を想い出す。
ソフト・フォーカスでぼんやりと霞んだ建物の形、光と影の淡いコントラスト。
何とも言えないノスタルジックな雰囲気が漂う独特なハーモニーが圧倒的に素晴らしい。聴いていると、様々な心象風景が
目の前に浮かんでは消えていく。映像喚起力がハンパない。
10人で生み出す豊かなハーモニーの能率の高さは凄いとしか言いようがないが、そのデリケートでありながらリッチな色彩感は
クロード・ソーンヒル楽団の生き写し。ソーンヒルのハーモニーは正にギル・エヴァンスのハーモニーだったわけだ。
ギル・エヴァンスのラージ・アンサンブルではジミー・クリーヴランドのトロンボーン・ソロが頻繁にフィーチャーされるが、
ここでも彼の夢見るような伸びやかなソロが印象的だ。また、スティーヴ・レイシーの苦み走ったソプラノもよく効いている。
揺蕩うような霞みがかったギル・エヴァンスのハーモニーが通奏低音のように流れ続ける、至福の時間を味わうことができる。
ある意味、ジャズの生命線とも言うべきスイングやアドリブよりも、ハーモニー優先でジャズを構成することを宣言した作品で、
その穏やかなラディカルさに、マイルスをはじめ、多くのミュージシャンが夢中になったというのはよくわかる。