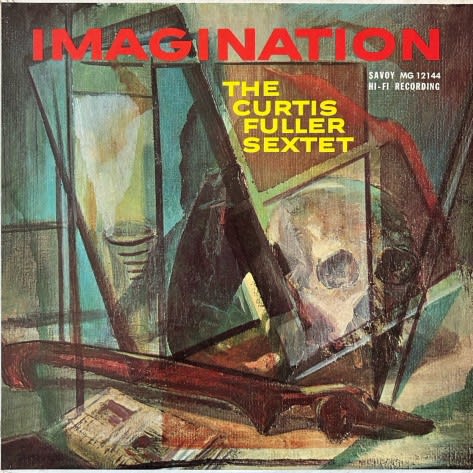Kenny Clarke / Bohemia After Dark ( 米 Savoy MG 12017 )
1955年7月14日に初リーダー作を作ることになった1ヵ月前に、キャノンボールはレコーディング・デビューをサヴォイで果たしている。
ケニー・クラーク名義になっているが、このレコーディングが行われたのはキャノンボールが契機になっていて、この時の話はシンデレラ・
ストーリーとして今に語り継がれている。
1955年6月のある夜、オスカー・ペティフォードは自身のバンドを率いてカフェ・ボヘミアで演奏することになっていたが、メンバーの1人、
ジェローム・リチャードソンが行方不明でバンドに欠員が出た。ちょうど観客の中にチャーリー・ラウズがいたので、彼にバンドに参加するように
声を掛けたが、ラウズはテナーを持っていなかった。この時、偶然にも店内にアダレイ兄弟が楽器を携えてライヴを観に来ていて、
ラウズはフロリダで共演経験があって彼らとは顔見知りだったため、キャノンボールにステージに上がってみないか、と声を掛けたのだ。
彼は二つ返事でステージに上がったが、オスカーはどこの誰かも分からない素人が加わったことにムッとし、1曲目の "I'll Remenber April"
を通常よりもずっと速いテンポで始めた。このド素人をステージから引きずり降ろそうとしたわけだ。ところが、パーカーのレコードで
この曲を勉強していたキャノンボールはこれを楽々とやってのけてしまう。
2曲目は自身が夜の帳が降りたカフェ・ボヘミアの光景を想って作曲した "Bohemia After Dark" で、この曲のテーマ部は吹くのが難しい
メロディーラインだったが、ここでもキャノンボールのアルトが火を吹いた。これにはオスカーもすっかり感激してしまい、
キャノンボールにライブの最後まで残るように頼み、彼の演奏で観客が熱狂することになった。
この時のギグの噂はまるで山火事のようにニューヨーク界隈に伝わることとなり、ケニー・クラークがすぐにオジー・カデナに連絡を取って、
レコーディングが用意されることとなった。この年の3月にパーカーが死去し、誰もが第2のパーカーの登場を心待ちにしていたのだ。
ある晩、フィル・ウッズがクラブで演奏したら、ジャッキー・マクリーンが血相を変えてやってきて「凄いやつが現れたぞ」と言って
ウッズをカフェ・ボヘミアへと引っ張って行くと、そこではキャノンボールが演奏していて、2人は固唾を飲んでそれを聴いていたという。
このギグの後、キャノンボールはオスカーのバンドに加わり演奏していたので、レコーディングはこのバンドのメンバーを採用することに
なったが、オスカーがメンバーだったホレス・シルヴァーを外すように要求したので(理由はよくわからない)、オジー・カデナがこれを
拒否して逆にオスカー自身をレコーディングから外すことに決めた。じゃあ、ということで、ケニー・クラークが代わりにカフェ・ボヘミアで
ピアノ・トリオのベースを担当していたまだ無名の20歳の痩せた若者を連れて来た。これが、あのポール・チェンバースだったのだ。
更に、ここに22歳の無名の新人トランペッターだったドナルド・バードを加えることになった。つまり、このアルバムは当時はまったくの
無名で、やがてはジャズ界を背負って立つことになる4名の新人(ジュリアン、ナット、チェンバース、バード)を世間にお披露目するために
先輩たちの粋な計らいで制作されたものだったのだ。こういう話になると日本ではアルフレッド・ライオンのことばかり取り上げられるけど、
実はそうではない。マイルスやロリンズを育てたワインストックにしろ、エヴァンスやウェスを育てたキープニュースにしろ、当時のジャズ・
レーベルのオーナーたちにはそういう熱い志があった。だからこそ、私たちは今、こうして素晴らしいレコードを聴くことができる。
このレコードは、ポール・チェンバースとドナルド・バードのレコーディング・デビュー作にもなった。
オスカーを外したことに後ろめたさが残ったメンバーたちは、予定していた "Sweet Georgia Brown" のメロディーに一部手を加えて、
"With Apologies To Oscar" というタイトルを付けて、B-2へ収録した。なんだか、これも泣かせる話である。
こういう経緯から生まれた内容なので、ここでの演奏はみんな活き活きとした勢いはあるけど、まだまだ個性の発芽は見られず、
平均的なジャム・セッションの域を出ていない。やはり、キャノンボールの演奏が頭一つ跳び抜けているけど、管楽器が多いので、
それぞれの見せ場を設ける設定だから、これはまあ仕方ない。そんな中、アルバム最後に置かれた "We'll Be Together Again" では
ナット・アダレイがワン・ホーンで切々と歌い上げて、アルバムの幕は閉じられる。それはまるでタイトルが示すように
「いずれまたどこかで、みんなで集まって演奏しよう」と言っているかのようで、切なく心に響き、深い余韻を残す。