深まる秋の日に、モーツァルトのピアノ協奏曲を聴きながら通勤しています。お天気の良いときなどにはまことに喜ばしく、雨模様の時には慰められながら、ハンドルを握っています。今回は、第11番ヘ長調、K.413(387a) を取り上げます。アンネローゼ・シュミットのピアノ、クルト・マズア指揮のドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏による全集の Disk-2 にあたります。
たいへん充実した添付リーフレットによれば、ザルツブルグを離れたモーツァルトは、1782年の秋から1783年はじめにかけて作曲された三曲(第11番、第12番、第13番)で、ウィーンにおける新しい活動を始めたとのことです。なるほど、映画「アマデウス」で、多くの人々がピアノを担ぎ、ついでにヴォルフガング君も肩車して演奏会場に運んでいき、予約演奏会を開催する場面がありましたが、あんなイメージでしょうか。もっとも、実際にはまだ市民向けのコンサートホールなどは普及せず、貴族の館の広間などが会場となっていたことでしょうが。
楽器編成は、Ob(2), Fg(2), Hrn(2), 弦5部 というもので、管と弦楽四重奏にても可、とされているそうです。なるほど、山響のモーツァルト定期でときどき聴くことができる、曲の途中で管のトップと弦楽トップだけのアンサンブルを聴かせる場面は、そうした想定を実際にやっているわけですね。
第1楽章:アレグロ、ヘ長調、4分の3拍子。協奏曲の形式によるソナタ形式。弦楽による序奏から。「後宮からの誘拐」のような華やかさと、ワクワク感があります。独奏ピアノも、低音を大胆に使っています。現代ピアノによる録音だけあって、どきっとするほど効果的です。
第2楽章:ラルゲット、変ロ長調、4分の4拍子。ソナチネ形式。低音弦のピツィカートをバックにヴァイオリンが穏やかな旋律を奏します。これを独奏ピアノが引き継いだのち、さらに夢見るように演奏が展開されます。
第3楽章:テンポ・ディ・メヌエット、ヘ長調、4分の3拍子。ロンド形式。優雅なメヌエットのテンポで、あまり速くなく始まると、独奏ピアノが入ってきます。こちらは華やかで、けっこう力強さも感じさせながら演奏されます。モーツァルト自身の言葉を借りれば、あまり難し過ぎず、また易しすぎず、ちょうど中間だそうで、音楽だけでなく、そのあたりの配慮にも、当時のモーツァルトが持っていた社交性を感じさせます。
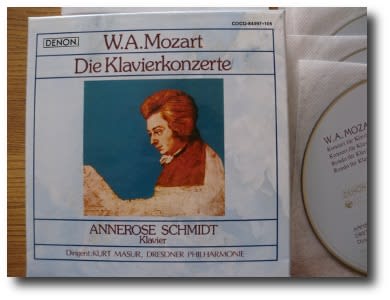
録音は、アリオラ・オイロディスク原盤で、1974年の2月に東独ドレスデンのルカ教会で収録されています。録音は良好です。
■アンネローゼ・シュミット盤
I=9'16" II=5'54" III=5'14" total=20'24"
たいへん充実した添付リーフレットによれば、ザルツブルグを離れたモーツァルトは、1782年の秋から1783年はじめにかけて作曲された三曲(第11番、第12番、第13番)で、ウィーンにおける新しい活動を始めたとのことです。なるほど、映画「アマデウス」で、多くの人々がピアノを担ぎ、ついでにヴォルフガング君も肩車して演奏会場に運んでいき、予約演奏会を開催する場面がありましたが、あんなイメージでしょうか。もっとも、実際にはまだ市民向けのコンサートホールなどは普及せず、貴族の館の広間などが会場となっていたことでしょうが。
楽器編成は、Ob(2), Fg(2), Hrn(2), 弦5部 というもので、管と弦楽四重奏にても可、とされているそうです。なるほど、山響のモーツァルト定期でときどき聴くことができる、曲の途中で管のトップと弦楽トップだけのアンサンブルを聴かせる場面は、そうした想定を実際にやっているわけですね。
第1楽章:アレグロ、ヘ長調、4分の3拍子。協奏曲の形式によるソナタ形式。弦楽による序奏から。「後宮からの誘拐」のような華やかさと、ワクワク感があります。独奏ピアノも、低音を大胆に使っています。現代ピアノによる録音だけあって、どきっとするほど効果的です。
第2楽章:ラルゲット、変ロ長調、4分の4拍子。ソナチネ形式。低音弦のピツィカートをバックにヴァイオリンが穏やかな旋律を奏します。これを独奏ピアノが引き継いだのち、さらに夢見るように演奏が展開されます。
第3楽章:テンポ・ディ・メヌエット、ヘ長調、4分の3拍子。ロンド形式。優雅なメヌエットのテンポで、あまり速くなく始まると、独奏ピアノが入ってきます。こちらは華やかで、けっこう力強さも感じさせながら演奏されます。モーツァルト自身の言葉を借りれば、あまり難し過ぎず、また易しすぎず、ちょうど中間だそうで、音楽だけでなく、そのあたりの配慮にも、当時のモーツァルトが持っていた社交性を感じさせます。
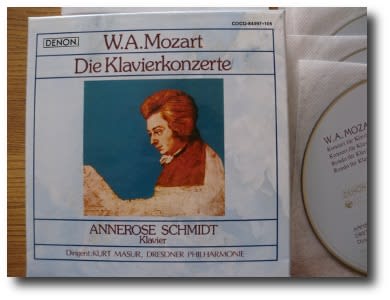
録音は、アリオラ・オイロディスク原盤で、1974年の2月に東独ドレスデンのルカ教会で収録されています。録音は良好です。
■アンネローゼ・シュミット盤
I=9'16" II=5'54" III=5'14" total=20'24"

















