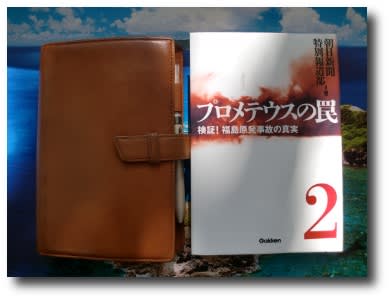福島原発事故を追跡検証する朝日新聞特別報道部の『プロメテウスの罠』(*1)の続巻、『プロメテウスの罠2』を読みました。なぜか、朝日新聞社本体からではなく、学研パブリッシングから刊行されているところに、大手広告主への遠慮を想像したりしながらも、内容的には朝日新聞社らしいものです。前巻に続く本書の構成は次のとおり。
このうち、第7章で「原子村」ではなく「原始村」に住むことにした元原子力技術者の理由が注目されます。原子力のエネルギー面でのすごさに注目し、それをゆっくり利用しようと考えるのと、原子核反応によって生成する放射性核種の増加、すなわち「死の灰」の不可避的蓄積に注目するのとでは、態度は大きく変わるでしょう。この場合は、放射性廃棄物の処理方法が決まっていないのに廃棄物だけが増えていくという現実の異常さに気づいてしまったこと、でしょうか。
第9章「ロスの灯り」では、下北半島の「むつ小川原開発」の歴史的な経緯を、はじめて認識しました。なんと、会津処分の斗南藩まで遡る怨念のようなものが、バックにあったとは。虐げられた者が権力の座についたときどういう振る舞いをするかは、歴史上多くの例がありますが、その青森版と言って良いのかもしれません。
第11章の津波警報のあり方については、軽々に論じることはできませんが、例えば「これまでにないほどの大津波」というような表現が、選択肢の中にあれば良かったと感じます。水圧計のデータを採用しなかった点の指摘は大切ですが、定量的な扱いをすることができる前提を超えているならば、定性的な表現で巨大さを伝えるしかないと思うからです。
第12章「脱原発の攻防」も、政治ベースで動く数字の決まり方に、あらためて驚きます。
いずれにしろ、意欲的な取材、編集です。新聞の連載記事では断片的にしかわからない事柄も、書籍の形になるとある程度全体像が想像できるように思います。
(*1):朝日新聞特別報道部『プロメテウスの罠』を読む~「電網郊外散歩道」2012年8月
第7章 原始村に住む
第8章 英国での検問
第9章 ロスの灯り
第10章 長安寺の遺骨
第11章 遅れた警報
第12章 脱原発の攻防
このうち、第7章で「原子村」ではなく「原始村」に住むことにした元原子力技術者の理由が注目されます。原子力のエネルギー面でのすごさに注目し、それをゆっくり利用しようと考えるのと、原子核反応によって生成する放射性核種の増加、すなわち「死の灰」の不可避的蓄積に注目するのとでは、態度は大きく変わるでしょう。この場合は、放射性廃棄物の処理方法が決まっていないのに廃棄物だけが増えていくという現実の異常さに気づいてしまったこと、でしょうか。
第9章「ロスの灯り」では、下北半島の「むつ小川原開発」の歴史的な経緯を、はじめて認識しました。なんと、会津処分の斗南藩まで遡る怨念のようなものが、バックにあったとは。虐げられた者が権力の座についたときどういう振る舞いをするかは、歴史上多くの例がありますが、その青森版と言って良いのかもしれません。
第11章の津波警報のあり方については、軽々に論じることはできませんが、例えば「これまでにないほどの大津波」というような表現が、選択肢の中にあれば良かったと感じます。水圧計のデータを採用しなかった点の指摘は大切ですが、定量的な扱いをすることができる前提を超えているならば、定性的な表現で巨大さを伝えるしかないと思うからです。
第12章「脱原発の攻防」も、政治ベースで動く数字の決まり方に、あらためて驚きます。
いずれにしろ、意欲的な取材、編集です。新聞の連載記事では断片的にしかわからない事柄も、書籍の形になるとある程度全体像が想像できるように思います。
(*1):朝日新聞特別報道部『プロメテウスの罠』を読む~「電網郊外散歩道」2012年8月