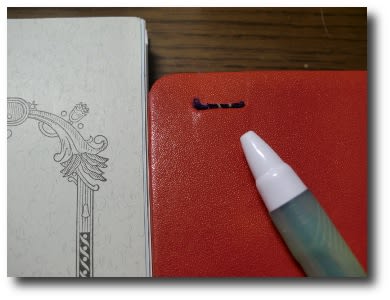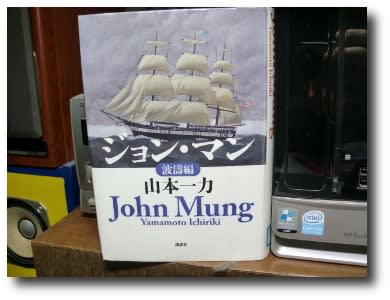過日、近所に葬儀があり、帳場を依頼されました。年齢的に、葬儀で帳場を頼まれる場面が増えたように思います。備忘のために、当地での慣習を整理してみると、図のようになります。

寺まで葬列を組んで歩いた昔は、喪主が位牌を持ち、近親者や親族で遺影や遺骨などを分けて持つしきたりがあり、その葬列の順序も記載していましたが、近年はその習慣も薄れてきております。セレモニー・ホールでの葬儀・告別式は、宗教的意味合いが薄れ、故人との別れの儀式が主体に変化しつつあるようです。
それでも、帳場の様子はあまり変わらず、筆ペンで和紙を綴った帳簿に書いています。紙の質があまり良くないのか、それとも筆ペンのインクの性質なのか、すぐにかすれて書けなくなってしまいます。贅沢をいえば、ニカワの入った墨汁のように、滲みにくくたっぷりとした書き味だと良いのですが、葬儀屋でお仕着せのものに文句を言っても仕方がありません(^o^;)>poripori
まずは、書き手が4人に受付との連絡係(運び屋)が2人、計六人くらいのチームワークで、手早く正確に作業を終え、一式を間違いなく喪主に引き渡すことが大切です。
○
これをパソコンで行うというやり方もあるでしょう。確かに、表計算を使えば集計は楽になりますが、実際には入力する業務が一人に集中し、他の人が手持ち無沙汰になります。それまで複数の人に分散していた作業が一人の人に集中する形になりますので、時間的にはあまり変わらないのでは。平準化よりも、業務に携わる人数を減らすのには有効かもしれませんが。
和紙を綴じた帳簿と比較して、入力した結果の保存も曖昧になる懸念もあります。実際は、データを再利用することもまずありませんし、電子化する意味があるのかどうか、ですね。

寺まで葬列を組んで歩いた昔は、喪主が位牌を持ち、近親者や親族で遺影や遺骨などを分けて持つしきたりがあり、その葬列の順序も記載していましたが、近年はその習慣も薄れてきております。セレモニー・ホールでの葬儀・告別式は、宗教的意味合いが薄れ、故人との別れの儀式が主体に変化しつつあるようです。
それでも、帳場の様子はあまり変わらず、筆ペンで和紙を綴った帳簿に書いています。紙の質があまり良くないのか、それとも筆ペンのインクの性質なのか、すぐにかすれて書けなくなってしまいます。贅沢をいえば、ニカワの入った墨汁のように、滲みにくくたっぷりとした書き味だと良いのですが、葬儀屋でお仕着せのものに文句を言っても仕方がありません(^o^;)>poripori
まずは、書き手が4人に受付との連絡係(運び屋)が2人、計六人くらいのチームワークで、手早く正確に作業を終え、一式を間違いなく喪主に引き渡すことが大切です。
○
これをパソコンで行うというやり方もあるでしょう。確かに、表計算を使えば集計は楽になりますが、実際には入力する業務が一人に集中し、他の人が手持ち無沙汰になります。それまで複数の人に分散していた作業が一人の人に集中する形になりますので、時間的にはあまり変わらないのでは。平準化よりも、業務に携わる人数を減らすのには有効かもしれませんが。
和紙を綴じた帳簿と比較して、入力した結果の保存も曖昧になる懸念もあります。実際は、データを再利用することもまずありませんし、電子化する意味があるのかどうか、ですね。