〈リバイバル・アーカイブス〉2021.8.9.~8.23.
原本:2015年3月5日
涙垂(なみだれ)の梅

戦で国が乱れていたむかしの話―。
京の都に花笠という、匂うように美しい娘がおりました。

ある年の祇園まつりの日、花笠は1人のりりしい若者と知り合いました。若者は、花笠のあまりの美しさに心をうばわれ、近づいて話しかけました。
「わたしは河内の国、喜志の里にあるお宮さまにつかえる正祐という者、神官の修業のために京へ出て来たのです。」
「わたしは花笠の内侍。修業に励むあなたのお噂は女官たちから聞いています。」

二人は山鉾の鉦や太鼓やお囃を楽しみ、祭りの火の消えるまで一緒に過ごしました。それから逢瀬を重ねるうちに、一年がすぎ、二年がすぎ、互いに忘れられんようになったのです。


ところが三年目の祇園まつりの夜、正祐は花笠の手をにぎり、
「喜志の里のお宮が戦で焼かれてしまいました。私が元通りに建てなおさなねばなりません。これから喜志へ旅立ちますが、あなたのことはけっして忘れません。」
と言い、大切にしていたお守り袋を花笠に渡しました。そして泣きすがる花笠をふりきり、遠い河内の国へ帰ったのです。
花笠は悲しみはつのるばかり、すっかりやつれてしまいました。眠れぬ夜、いつものように正祐を思い星空を眺めていると、一瞬、矢のような光が山の向こうにとんで消えました。
「そうだ、あの山越えて正祐さまに逢いに行けばいい。」
そう思いついた花笠の心は急に明るくなり、肌身離さず持ち続けているお守り袋を、頬におし当てました。
いつしか秋も過ぎ、木枯らしが都大路を吹きすさぶころ、花笠は宮中にいとまをつげ、喜志の里へと旅立ちました。

若い娘の一人旅は、それはそれは苦しいものでしたが、正祐に逢えるよろこびを胸に、じっと耐えて歩きつづけました。
やがてはるかな山なみに、ひときわ美しい二上山が見えました。




花笠は、最後の力をふりしぼってやっとの思いでたどりついた喜志の里、そして宮の大鳥居、とうとう恋しい正祐のいる美具久留御魂神社についたのです。



焼けあとの仮社殿で正祐は、遅くまでお祈りをしていました。しかし、今夜はなぜか胸さわぎがするのです。ふと自分の名を呼ばれた気がして外へ出ました。
目を疑いました。そこに見たものは、月を背にして立っている花笠の姿だったのです。
「正祐さま、お逢いしとうございました。一人でいるのがとてもつらくて・・・」
「花笠・・・」
同じ思いの正祐は走り寄ろうとしました。けれど「正祐、お宮の再興を頼む。」と言って死んだ父の言葉が、頭をかすめたのです。恋しさのために、父との約束を破ってはならないと、心を鬼にして身をひるがえし、社殿に走りこみました。二人とも、つらい夜でありました。
夜が明けて、境内を歩く正祐の目にしたものは、息絶えた花笠の白い顔だったのです。

正祐は泣きながら、お守り袋をしっかりにぎっている花笠を、いつまでも胸に抱きしめていました。
「ゆるしてくれ。来世はきっと夫婦になろうぞ。」

くり返しそう言いながら、花笠を社殿の近くに手厚く葬りました。
冬が去り、春がおとずれました。
ふしぎなことに、花笠の墓のそばに小さな梅の木がはえました。その木はどんどん大きくなり、やがて、毎年春になると、白い花がいっぱい咲きました。

そして、風もないのにホロロン、ホロロンと、花びらがこぼれるのです。・・・まるで、花笠の涙のように・・・。いつしか里の人びとは、この梅のことを、「なみだれ(涙垂)の梅」と呼ぶようになりました。

「涙垂の梅」記念碑は、市内宮町の美具久留御魂神社の森の中にある。

出典:「富田林の民話・総集編」富田林民話研究クラブ 平成11年3月
撮影:「梅の花」2015.3.4. 錦織公園
「祇園まつり」 2009.7.17.
「美具久留御魂神社」 2014.4.10.ほか
「喜志の宮 だんじり祭」 2013.10.20.
2015.3月5日 ( HN:アブラコウモリH )















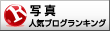
















≪涙垂れの梅≫伝説。
喜志の神社に伝わる「涙垂れの梅」の恋を偲ぶ伝説。
ご当地、富田林の小池氏のCD(歌:令和元年)に、誕生し、披露されました。