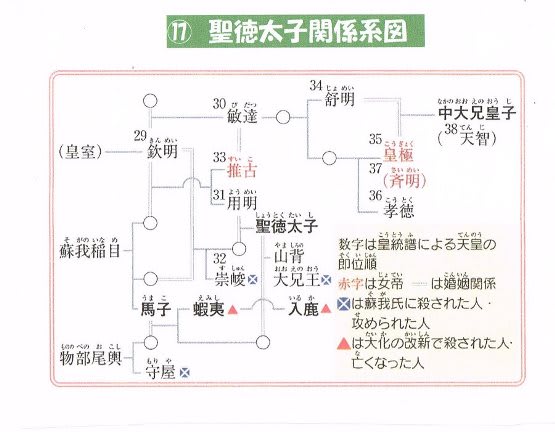文芸春秋十月号に≪「慰安婦検証記事」、朝日OBはこう読んだ≫という特集があり、その中にある元主筆若宮啓文氏の寄稿に次の一節がある。
そもそも慰安婦が「強制的に狩り出された」というのは、吉田証言があろうがなかろうが、韓国では基本的な認識です。何をもって強制連行というかには議論がありますが、河野談話が認めたように、総じて強制性があったことは否定できない。
慰安婦問題が韓国における反日イデオロギーの主要な武器になったのは、故吉田誠治氏の歴史捏造に朝日新聞がお墨付きを与えたからである。吉田氏の捏造以前には、「強制連行」なる情報は存在しなかった。したがって、この3行は若宮氏の思い込みに過ぎない。
さて、日本や朝鮮では昔から公娼が存在した。ウィキペディアにある妓生(キーセン)の項目をご覧いただく。妓生には、私も1970年代にずいぶんお世話になったので、懐かしいかぎりです(笑い)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%93%E7%94%9F
第二次大戦当時は(その後もしばらくは)、売春婦の存在は日韓社会の常識だった。貧困のために身を売る女性はたくさんいたし、女性が不足した時は新聞広告で募集した。そして広告が掲載された朝鮮の新聞も残されている(6~7年前に保守派の雑誌で広告実物を見たことがある)。強制連行など必要なかったのである。朝日新聞は第三者による調査委員会をつくるそうだが、調査すればするほど「強制連行はなかった」という結論に到達するはずである。公明正大な調査に期待する。
また、「強制性があったことは否定できない」と若宮氏は主張するが、「強制性」とは日韓両政府が韓国内の反日世論を和らげるために作った玉虫色の表現にすぎない。いまさら「強制性」とは何かを論ずることは無意味である。
若宮氏の論文には次のような一節もある。
朝日が過去の報道を訂正しても、慰安婦問題の本質とはまったく関係がなく、問題は存在しつづけるのです。…当時の価値基準では問題なかったという人がいますが、だましたり脅したり、人身売買したりして女性を集めることが、果たして当時に基準でも許されただろうか…
若宮氏は、女衒(ぜげん)の非倫理性を日本政府または日本軍の責任にしたいようだが、それは筋違いである。それでも日本政府は大乗的見地からあえて慰安婦を救う基金を設けたが、反日派の反対(もしくは妨害)で慰安婦たちが受け取ることがなかったと聞いている。人道問題はそこで終わっているはずだ。
若宮氏の主張は、論点をすり替えることで、朝日の責任をできるだけ薄めようとしている感がある。