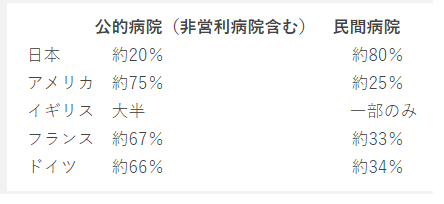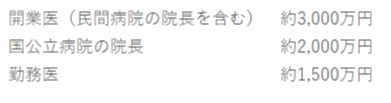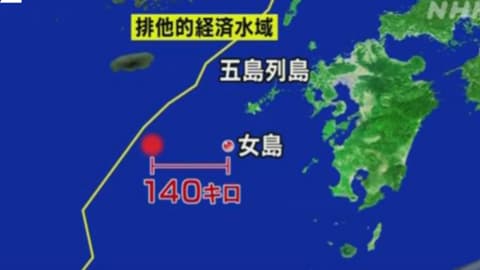今回はロンドンにおける旭日旗騒動をテーマにする予定だったが、朗報が飛び込んできたので、急遽切り替えることにする。
その朗報とは、米国ハーバート大学の教授であるJ・マーク・ラムザイヤー教授による慰安婦に関する学術論文Contracting for sex in the Pacific Warが、3月に刊行されるというニュースである。この論文の要約が本日の産経新聞に掲載されており、そのキモの部分は次の通り(青字)。
慰安婦とは、性病蔓延を恐れた日本軍が、業者に軍事拠点近くに設置させた半公式の売春宿において、兵士への売春行為を行わせた女性のことである。その大部分は日本人と朝鮮人で、年期奉公で売春を行う契約を結んだ。内地ではすでに売春婦になっていた女性が慰安婦になったケースが多いが、朝鮮半島では業者が募集を実施した。そして、その募集の過程で業者による欺瞞行為もあった。
要するに、本論文では、日本軍が女性を拉致したのではないことが明らかにされている。朝日新聞による“拉致”の誤報は、その後同紙が誤報と認め謝罪したにもかかわらず、韓国の市民団体はその謝罪を無視し、世界中に“韓国女性が日本軍に拉致された”という嘘をまき散らして、日本を貶めてきた。
日本政府は1993年における河野談話により拉致を認めた形になり、さらに2015年に当時の安倍首相が謝罪し、10億円の和解金を支払ってまとめた“慰安婦合意”でも、“拉致”を撤回したわけではない。
この不名誉なトラウマが残っているために、米国やドイツで慰安婦像が続々と設置され、さらに韓国で元慰安婦が訴訟し、勝訴するという結果を招いている。数年前、韓国人の学者による「反日種族主義」が韓国と日本で出版されベストセラーになり、真実が明らかになったが、韓国の市民団体は無視している。
問題は、「反日種族主義」が韓国語と日本語で出版されたため、真実が国際社会には伝わっていないことである。その点で、このラムザイヤー論文の出版は、日本にとって濡れ衣を晴らす絶好の材料になる。
しかし、国際社会が学術論文にどのように反応するかは未知数であり、日本としてはこのラムザイヤー論文をどう生かすかが課題となる。
一方、韓国のマスコミの日本特派員も産経新聞を読んでいるはずだから、このニュースを本社に伝えるだろう。しかし、それでは文大統領も慰安婦訴訟に関わった裁判官も迷惑するから、無視する可能性がある。注目されるところである。