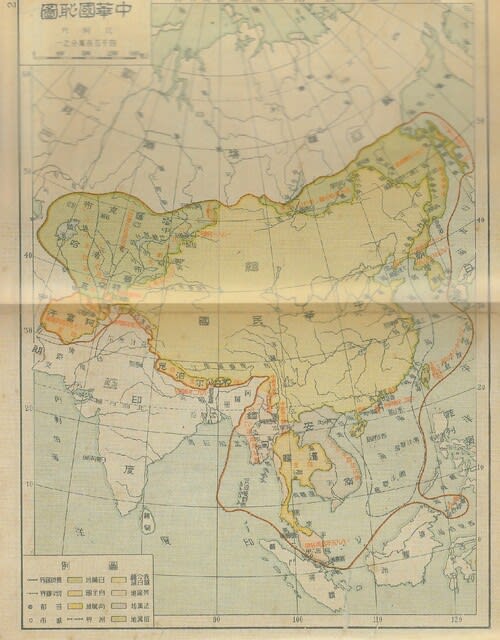11月27日の産経新聞で、<脱炭素加速へ 電動車導入の支援強化>という見出しの記事に、「日本は電動車に関して、欧州や中国などに比べて普及が遅れているのに加え、政府は2035年までに新車販売を電動車のみとする方針を打ち立てた。このため…電動車導入拡大に弾みをつけたい考えだ」とあるのを読んで疑問を抱いた。
疑問の理由は、政府の方針が自動車業界の意見と矛盾するからである。2020年12月17日にトヨタ自動車の豊田章男社長がオンライン記者会見で次のように発言した。(赤字)
夏の電力使用のピークの時に全部EVであった場合は、電力不足に陥ります。解消には発電能力を10~15%増やさなくてはなりません。この10~15%というのは実際にどんなレベルかというと、原発でプラス10基、火力発電であればプラス20基必要な規模です。
(出所:「EV推進の罠」ワニブックス 2021年11月刊)
日本の電力供給は現在、火力発電が77%で、残りの23%が再生可能エネルギー(水力、太陽光、風力)と原子力である。そして、日本政府は2030年までに温室効果ガスを2013年対比で46%削減し、2050年までにゼロにするという目標を掲げた。つまり、この目標は2050年までに電力供給の3分の2を占める火力発電をやめることを意味する。
再生可能エネルギーによる発電には限界があることは明らかになっており、火力発電をゼロにするなら、原子力発電(原発)を増やさなくてはならない。その一方で、政府は原発をもう増やさないという方針を掲げているから、現在休止している原発を再稼働させなくてはならない。
ところが、福島原発の事故により、国民に原発アレルギーがあり、原発再稼働は遅々として進んでいない。こうした状況の中で、EV車を普及させることで必要になる電力はどのようにして賄うのか。
さらに、EVはエンジンの代わりに電池を動力源にするのだから、現在の車とはコンセプトがまったく異なる。もしも、車がすべてEVになったら、エンジンを製造している人々はいらなくなるから、数百万人の失業が発生する。今エンジンを製造している人々が電池を製造すればいいのだが、エンジンと電池の製造は全く異なる業種であり、そう簡単に業種変更ができるはずがない。
要するに、<2035年までに新車販売を電動車のみとする>方針は自動車業界の合意を得たものではないことは明白である。ことによって、産経新聞の記事は間違いではないかと思い、同日の読売新聞に関連記事を探したら、次の記事があった。
<EV補助金拡充>と言う見出しの小さな記事に「政府は30年に乗用車でEV、PHV(プラグインハイブリッド車)を20~30%とする普及目標を立てているが・・・」とある。
これなら<2035年以降、新車販売は電動車に限る>よりはましだが、それでもEVの普及は電力供給の増加と同時に進めなくてはならない。読売新聞が報じる「2030年」は僅か8年後であり、電力供給増加への青写真はすでに出来上がっていなくてはならないが、まだそんな状況にはなっていないはずだ。
結論として、政府が掲げるEVの普及は、絵に描いた餅のような状況にあると考える。
蛇足だが、米欧中の各首脳は2050年までに温室効果ガス排出をゼロにする(中国は2060年)と宣言したが、彼らがその時点で生きていることはないだろう。死後のことを約束しているわけで、無責任な話である。そして、日本政府の脱炭素宣言は欧米諸国に同調しただけであり、国益を無視していると考える。