前回は古田武彦氏の「九州王朝説」を紹介し、私なりの疑問点を述べた。では専門家はどう言っているか。安本美典氏の反論(『虚妄の九州王朝』梓書院 H7年4月)を紹介する。
◆広開土王(好大王)が戦った相手は?
高句麗の広開土王の石碑によれば、高句麗が倭軍と闘ったことは間違いないが、古田氏は「当時の大和朝廷には、半島に出兵した記録がないから、広開土王が交戦した相手は九州王朝の倭軍である」と主張する。これに対し、安本氏は次のように反駁する。
広開土王が戦った相手は神功皇后が率いる大和朝廷の軍勢である。神功皇后の活躍が記された『記紀』では、信じがたい童話的記述もあるが、『常陸国風土記』、『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『万葉集』、『続日本書紀』、『古語拾遺』(斎部広成807年)、『新撰姓氏録』 (815年)等に息長帯日売(神功皇后)の新羅征討に関する記述があり、神功が実在の人物であり、その新羅征伐は疑いない史実である。
神功皇后が活躍した時代について、これまで360-390年とする説が多かったが、安本氏の「天皇の平均在位十年説」によれば、神功の活躍した時代は390-410年と推定され、広開土王の石碑の記述に合致する。
さらに、安本氏は「新羅の皇子、未斯欣が倭国に人質となった(402)のち、見張りを欺いて本国に逃げ帰った話(418)は、『紀(神功皇后紀)』と『三国史記』の両方に記載されているから、史実であること間違いない」から、広開土王の戦った相手が大和朝廷であることが裏付けられると主張する。
◆倭の五王とは?
古田氏は「5世紀に晋や宋に朝貢した倭の五王すなわち讃(413、421、425年)、珍(438年)、済(443、451年)、興(462年)、武(479年)とは大和朝廷の天皇ではなく、九州王朝の王である。『記紀』に五王の朝貢に関する記述がないのは、それが九州王朝の事績だからで、大和朝廷の天皇に比定しようとしても無理があるのは当然である」と主張する。
これに対し、安本氏は「倭の五王とは大和朝廷の天皇である」として、次のように論証する。
倭王武の上表文「東は毛人を征すること55ヶ国、西は衆夷を服すること66ヶ国」にある毛人に関し、『旧唐書』に「東北の隅は隔てつるに大山を以てす。山外は即ち毛人国なり」という記述があり、関東以北を毛人の領域としている。また『上宮聖徳法王帝説』には、「蘇我豊浦毛人大臣児入鹿臣」という記述があり、この毛人は明らかに蝦夷であって、蝦夷のことを毛人と呼ぶ伝統があったことがわかる。また、『記紀』には日本武尊が陸奥の国で蝦夷を討ったという記述がある。すなわち、「毛人を征すること55ヶ国」は、中国と日本の史書において合致している。
また、「西は衆夷を服すること66ヶ国」における「衆夷」については、安本氏は「畿内から見れば、西の衆夷とは『記紀』に記される熊襲や土蜘蛛を指すのだろう。しかし、北九州から見れば、西には北九州内の国しかない。九州王朝は九州を治めていたはずで、自分の領域である北九州の国々を衆夷と呼ぶのは解せない」と主張する。
◆隋書との不一致:
古田氏の主張「『隋書』によれば、最初の遣隋使は開王20年(推古8年、600年)だが、『紀』では推古15年となっている。また、『隋書』では、608年の遣隋使が最後となっているが、『紀』では614年にも遣使の記録がある。『隋書』と『記紀』の記録が食い違うのは、九州王朝と大和朝廷の両方から遣隋使が派遣されたことを示す」
これに対し、安本氏は「中国側の史書と日本側の史書が一致しない例は数多い。不一致をもって九州王朝が存在した証にすることはできない。中国の史書には間違いが多いのである」と主張する。
◆白村江の戦い:
663年、白村江で日本・百済連合軍は唐・新羅連合軍がと戦い、日本・百済は敗れ、百済は滅亡した。古田氏はこの戦いにおける日本軍を大和朝廷軍ではなく、九州王朝軍であると説く。
安本氏はこれについて、「古田説によれば、九州王朝は531年の磐井の乱によって叩き潰されていたはずだ」と指摘する。
◆九州年号:
古田氏は、李氏朝鮮で編纂された『海東諸国記』(1471年成立)に載っている善化、正和、発倒、僧聴などの年号を九州年号と称し、九州に王朝があった証拠である、と主張する。
この点について、安本氏は次のように批判する。
九州年号という呼称は鶴嶺戊申の『襲国偽僭考』に使われているだけである。同書には「今本文に引所は、九州年号と題したる古写本によるものなり」とあるが、その古写本なるものは現存しない。すなわち、九州年号という呼称には疑問があり、そうした古代年号が実在したかどうかの確証はない。
結論:安本氏の「九州王朝説」批判は次のように要約される。
古田氏の九州王朝説の最大の問題点は、九州王朝の存在を示す直接的な文献的証拠がなにもないことである。古田氏は、『記紀』は誤りに満ちているが、中国や朝鮮の文献にはまったく誤りがないという前提で自説を展開するが、それはあまりにも一方的な態度である。九州王朝説は根拠がない妄想にすぎない。
安本氏の批判は大筋において的を射ていると思うが、安本氏は古田氏の主張をすべて論破しているわけではない。例えば、『隋書』に、600年に隋が倭国に使節を遣し、国王に面接したという記述があり、国王の名前は姓が阿毎(あめ)、名が多利思北孤、阿輩鶏弥(おおきみ)、皇后の名は鶏弥とある。明らかに国王は男性だが、当時の大和朝廷の天皇は推古で女性。これをもって、大和朝廷以外にも王権が存在した証拠とすることは論理の飛躍であるが、だからといって単純に『隋書』の誤りとして看過するには、矛盾があまりにも具体的のように感じられる。
私は安本氏の主張に分があると思うが、古田氏の主張の一部には傾聴すべき点がいくつかあり、古田氏も論破されたとは思っていないようだ。1973年に「失われた九州王朝」(朝日新聞社)を発表して以来、あまたの批判を受けたが、同書の復刻版が2010年に出版されていることからしても、古田氏は自説を曲げていないようだ。
そして、「九州王朝」説を唱えるのは、古田氏ばかりではない。次回はその説を紹介する。










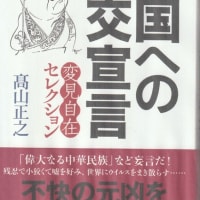








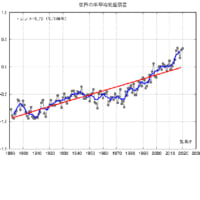
ですがそもそも安本氏は専門家(考古学)ではないですよね?寧ろ趣味人かと。
安本氏の主張は単に後からの主張なので分があるように見えるだけだと思いますよ?
吉田氏が論破されたと思っていないのは当然で、安本氏は吉田氏が広げた枝葉を否定しているにすぎず、根幹を否定するに至っていませんから。
枝を切った所で幹は切れません。
安本氏にしても自分の説にかからない部分はどうでもよい話ですしね。
なのでこれは「九州王朝説」への批判とは言えず、吉田氏の論点に対する批判ではないでしょうか。
>■広開土王(好大王)が戦った相手は?
>■倭の五王とは?
>■隋書との不一致
これは何の根拠もなく言い張っているだけですよね。
一つ一つの否定の為に「あの説」「この説」と立場がバラバラです。専門家ではないからかもしれませんね。
ちなみに倭王武の件ですが、熊襲等なら反発勢力ですので、毛人と同じ「征する」になります。「服する」とは反発しないものなので、自国の領域を指すと考えて正しいでしょう。
自らの支配規模を誇示する文章に於いて、自らに忠実な国の数を含めない理由などありませんよ。
多い方が良いのですから。
>◆白村江の戦い
>◆九州年号
これは吉田氏が本来の中国の史書からという論点からそれて想像を広げた話なので、九州に王朝があったかどうかとは関係が無くどうでもよい話でしょう。
物的証拠も「一つの前提」を作られては機能しません。
教科書などの古代史は、物証の発掘が乏しく年代測定も出来ない未熟な時代に考えられたものを土台として組み上げてきていますから、平衡のとれたものになっていないのです。
日本古代史も妙な「前提」無く物的証拠からくみ上げて冷静に検討される日が来ることを願っています。
・広開土王の石碑のとおりなら、倭軍は度々撃退されており、神功皇后が三韓を征伐するどころの話じゃないですよね?これについてはどう思いますか?
・倭の五王ですが、多くの研究者らは大王の在位年数とか漢風名と和風名の対応、大型古墳の事を取り上げます。でもそれだけじゃないですよね。王らが名乗った、使持節都督や開府儀同三司。都督府・太宰府との関連性や記紀に記述されない神籠石山城群。また、豪奢な副葬品を伴う装飾古墳や石人・石馬の存在。これらについてはどう思いますか?
・隋書との不一致ですが、例えば、倭国人は大人・子ども・身分の上下などに関わらず、刺青をしていた。同姓不婚だった等。今の日本に通じるものがありますかね?
・白村江の戦いですが、国の存亡に関わる戦いで主力を率いる天智天皇が軍勢を渡海させないってどう思いますか?筑紫君や毛野君が軍勢を渡海させているにも関わらずですよ。
・九州年号ですが、実際に木簡に記されたものが発見されましたよ。どう思いますか?
古田氏が中国史書のみに依拠した研究を行っていると思いますか?何でも否定できるとは思えませんが。実際に彼の著作を全て目を通してみてはどうでしょうか。
卑弥呼や壱与の魏への遣使が、なぜ神功皇后一人の行為に日本書紀ではすり替えられているんですか?二人が大和朝廷の女王なら、許されることじゃないですね。それに、すり替えはこれだけですか?
中国の史書は平気で嘘を書きます。但し、それは自分たちの利害に関わる場合。
蛮夷の状況など、動物の生態記録のように書きます。
かなり前の投稿を見つけて頂き、嬉しく存じます。
有難うございました。
>http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1396067238
神武天皇の親衛隊みたいな男が入れ墨を目の周りにしてたってありますが。
古い投稿にコメント頂き、有難うございます。
刺青の話、拝読しました。面白いですね。