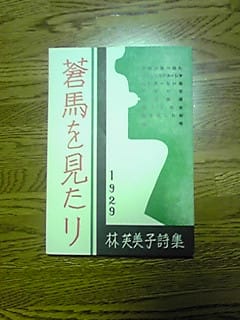へそ曲がりは旦那様によく似たのか、この本がはやっていた頃も読んでいない。古本屋で出てくるのを待って、手に入れた。それから時折とりだしては読み返している。とても楽しい本だ。内容は、みなさんのほうが熟知されていると思う。東工大生協のひとことカードに、担当の白石さんが生協として返事を書かれた問答集だ。
生協の担当者として、どんな質問にも気まじめに答えているのだが、その誠実な答えが的外れのような外れていないような、そんな「微妙な」受け答えが笑える。白石昌則さんというかたの人柄もそうだが、東工大の学生さん達が素晴らしい。白石さんの返答を楽しむゆとりがある。ぼけとつっこみを見事に演じている。白石さんも信州大学を卒業されているという、相手に不足なしというところなのだろう。
長男が高三でセンター試験を終えたときに、あまり点数がとれていなかった彼は学校の進路指導で第一志望の大学は無理だと太鼓判を押された。「○○は教育大。総合大学が希望なら、秋田か信州」と言われた。秋田大や信州大が悪いとかそういうことはないのだが、今まで己が通う大学と言う目で見てこなかったのにいきなり名前が飛び出してきて、息子が混乱してしまった。信州大学と聞いて、あの時の息子の様子を思い出した。「ダメでもいいから受けたい」という息子の希望を優先し、信州大学に挑戦することはなかったのだが、白石さんのような方を育てた大学だったのかと、何も信州大学にイメージを持たなかった自分に形が少しできました。
今、白石さんはどうされているのかとネットで検索したら、2008年に東京インカレコープの店長さんになられて東工大にはいらっしゃらないようだ。加えてNHKのラジオ第一放送に「こたえて!生協の白石さん」と題するコーナーを持っているらっしゃるようだ。HPを観に行った。生協というくくりが無くなってしまったせいか、何でも聞けそうで、そうでもなく、質問される内容が偏っているように感じるのが不思議だが、白石さんは淡々と答えていらっしゃる。やはり、東工大の学生さん達に軍配が上がるように感じる。あの白石さんの問答は、東工大の学生さん達が相手だったからこそ生まれたのだなあ・・・。
ご存知だろうが、楽しい本の中からいくつか問答を
生協への質問・意見、要望・・・8月になったので、約束のプールに行きましょう♪
生協からのお答え・・・涼しげなお誘い、ありがとうございます。しかし、生協一同のだれもが、上記の約束を思い出せずにいます。このままでは待ち合わせの場所にすら行けそうにありませんが、どうぞ気にせず先に行ってください。(担当・白石)
生協への質問・意見、要望・・・牛を置いて!
生協からのお答え・・・ご要望ありがとうございます。本日丁度職場会議が開かれたのですが、結果、牛は置けない、と決議されました。即決でした。申し訳ございません。(担当・白石)