20日(火).わが家に来てから722日目を迎え,なぜか倒れ込んでいる白ウサちゃんを発見し,動揺するモコタロです

白ウサちゃん どうしたの? この子犬たちにやられたの?

なに ぼくたちじゃない 犬当違いだって?

こらこら 白ウサちゃんを気絶したまま置いていくなってば!

 閑話休題
閑話休題 

昨日「サントリーホールのオルガン・カフェ #3」を聴きました プログラムは①メンデルスゾーン「交響曲第4番イ長調”イタリア”」から第1楽章,②ニーノ・ロータ「映画:ゴッドファーザー」から,③マスカー二「歌劇:カヴァレリア・ルスティカーナ」から「間奏曲」,④タルティーニ「トランペット協奏曲ニ長調」から「第3楽章」,⑤ヴィエルヌ「オルガン交響曲第1番」から「終楽章」です
プログラムは①メンデルスゾーン「交響曲第4番イ長調”イタリア”」から第1楽章,②ニーノ・ロータ「映画:ゴッドファーザー」から,③マスカー二「歌劇:カヴァレリア・ルスティカーナ」から「間奏曲」,④タルティーニ「トランペット協奏曲ニ長調」から「第3楽章」,⑤ヴィエルヌ「オルガン交響曲第1番」から「終楽章」です オルガン独奏は山口綾規,トランペット独奏は高見信行,ナビゲーターは川平慈英です
オルガン独奏は山口綾規,トランペット独奏は高見信行,ナビゲーターは川平慈英です

自席は1階10列16番,センターブロック左通路側です.会場は最初から空けてあるP席を除いてほぼ満席状態です 祝日の昼間で低料金(指定2,000円)が受けているのでしょうか
祝日の昼間で低料金(指定2,000円)が受けているのでしょうか ステージ上方のパイプオルガンの他に,1階のステージ右サイドに演奏台が設置されています.組込式と移動式の両方の演奏台を使用するようです
ステージ上方のパイプオルガンの他に,1階のステージ右サイドに演奏台が設置されています.組込式と移動式の両方の演奏台を使用するようです
ところで,サントリーホールのパイプオルガンですが,プログラムに掲載された解説によると,メーカーはオーストリアのリーガー社,演奏台は2台(4段手鍵盤,足鍵盤),ストップ数74,パイプ数5898本となっています.5898本ですよ,奥さん 来年2月からサントリーホールは全面的な改装工事に入りますが,このパイプオルガンはどうなるんでしょうね? 解体してフル・メンテをするのでしょうか? 興味があります
来年2月からサントリーホールは全面的な改装工事に入りますが,このパイプオルガンはどうなるんでしょうね? 解体してフル・メンテをするのでしょうか? 興味があります
2階の正面バルコニーに山口綾規が登場,オルガンに向かいます この人は早稲田大学政経学部を卒業後,東京藝大大学院でオルガンを学んだという変わった経歴の持ち主です
この人は早稲田大学政経学部を卒業後,東京藝大大学院でオルガンを学んだという変わった経歴の持ち主です 早速1曲目のメンデルスゾーン「交響曲第4番イ長調”イタリア”」の第1楽章の演奏に入ります.メンデルスゾーンは21歳から22歳にかけて約半年間イタリア旅行に出ました(資産家の息子ですから)が,その時の印象を基に書いた曲の一つがこの交響曲です
早速1曲目のメンデルスゾーン「交響曲第4番イ長調”イタリア”」の第1楽章の演奏に入ります.メンデルスゾーンは21歳から22歳にかけて約半年間イタリア旅行に出ました(資産家の息子ですから)が,その時の印象を基に書いた曲の一つがこの交響曲です
1台のオルガンで「イタリア」を聴くのは今回が初めてですが,太陽の輝きに満ちたイタリアを旅したメンデルスゾーンの浮き浮きした楽しい気分が手に取るように伝わってきました 聴く前はもっと重い演奏になるかと予想していましたが,演奏は軽快そのものでした
聴く前はもっと重い演奏になるかと予想していましたが,演奏は軽快そのものでした
ここで,サッカー解説の「ゴオオオオオ~ル!!」の絶叫でお馴染みの川平慈英が上下黒のソムリエ・スタイルで登場,自己紹介し,次いで山口氏を紹介しました そして「これからコンサートのキック・オフを開始します
そして「これからコンサートのキック・オフを開始します 」と,あくまでもサッカーにこだわった開会宣言をしました
」と,あくまでもサッカーにこだわった開会宣言をしました
2曲目はニーノ・ロータ作曲による映画「ゴッド・ファーザー」のパート1,パートⅡから数曲がメドレーで演奏されました
ここで,2階正面バルコニーにトランペット奏者・高見信行が登場します.この人は東京藝大卒業後ドイツの音楽大学で学び,ドイツ国家演奏家資格(マイスター)を取得しています オルガンとの共演で演奏するのはマスカー二のオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」から「間奏曲」です
オルガンとの共演で演奏するのはマスカー二のオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」から「間奏曲」です オルガンの前奏に続いてトランペットが入ってきてメイン・メロディーを奏でますが,オーケストラで聴いても,特定の楽器で聴いても,感動的です
オルガンの前奏に続いてトランペットが入ってきてメイン・メロディーを奏でますが,オーケストラで聴いても,特定の楽器で聴いても,感動的です こんなに美しい音楽があるのか,と思うほどです
こんなに美しい音楽があるのか,と思うほどです
次いで,タルティーニの「トランペット協奏曲ニ長調」から「第3楽章」がトランペットの輝かしい演奏で奏でられました
プログラム前半の最後はJ.S.バッハの「パッサカリアとフーガ ハ短調BWV582」です 山口綾親が再登場しオルガンに向かいます.鍵盤に手を置くかと思いきや,この曲は足から入ります
山口綾親が再登場しオルガンに向かいます.鍵盤に手を置くかと思いきや,この曲は足から入ります パイプオルガンの低音部は足によって演奏されます.正面のパイプオルガンの一番太いパイプを通じて重低音が会場いっぱい響き渡ります
パイプオルガンの低音部は足によって演奏されます.正面のパイプオルガンの一番太いパイプを通じて重低音が会場いっぱい響き渡ります この曲や,有名な「トッカータとフーガ」を聴くと,敬虔な気持ちになり,にわかクリスチャンになります
この曲や,有名な「トッカータとフーガ」を聴くと,敬虔な気持ちになり,にわかクリスチャンになります

後半の部は,1階のステージで演奏されるようです.ステージ右サイドのオルガン演奏台に山口氏が,左サイドにトランペットの高見氏がスタンバイします
いったい何が始まるのかと思って見ていると,ナビゲーターの川平が仲間をステージに呼び,二人で傘を持って「雨に歌えば」を歌いながらタップ・ダンスを披露しました.これは博品館劇場で二人が上演するステージの宣伝でした.したがってここでは詳細を冷たく割愛します
プログラム後半の最初はグノ―の「マリオネットの葬送行進曲」です グノ―と言えばバッハの平均律のプレリュードをアレンジして「アヴェ・マリア」を書いた人です.どうやらこの曲は1950年代から放送されたテレビ番組「ヒチコック劇場」のテーマ音楽に使われていたそうです
グノ―と言えばバッハの平均律のプレリュードをアレンジして「アヴェ・マリア」を書いた人です.どうやらこの曲は1950年代から放送されたテレビ番組「ヒチコック劇場」のテーマ音楽に使われていたそうです 聴いてみると,所々聞き覚えのあるメロディーが出てきました
聴いてみると,所々聞き覚えのあるメロディーが出てきました
プログラムの最後はフランスの作曲家ルイ・ヴィエルヌの「オルガン交響曲第1番」から最後の「第6楽章」です 山口氏は再度2階に上がり,パイプオルガンに向かいます.この曲を聴いてみて初めて,彼がなぜ「交響曲」という名前を付けたのかが分かりました
山口氏は再度2階に上がり,パイプオルガンに向かいます.この曲を聴いてみて初めて,彼がなぜ「交響曲」という名前を付けたのかが分かりました パイプオルガン1台で まるでフル・オーケストラの豊穣な響きを再現するのですから,その迫力には圧倒されます
パイプオルガン1台で まるでフル・オーケストラの豊穣な響きを再現するのですから,その迫力には圧倒されます まさに音の大伽藍が構築されるようです
まさに音の大伽藍が構築されるようです 聴き終わって,会場いっぱいの拍手を受け,誇らしげな表情の山口氏を見ながら,「この人は今日,大観衆の面前でこの曲が弾きたかったんだろうな」と思いました
聴き終わって,会場いっぱいの拍手を受け,誇らしげな表情の山口氏を見ながら,「この人は今日,大観衆の面前でこの曲が弾きたかったんだろうな」と思いました
これで終わりかと思いきや,再度トランペットの高見氏が登場し,アンコールにプッチーニのオペラ「トゥーランドット」から「誰も寝てはならぬ」を感動的に演奏し,コンサートの幕を閉じました
休憩を挟んで2時間弱のコンサートでしたが,とてもリラックスした良い公演でした.また来年も聴きに来ようと思います

さて,「今日こそは何もありませんように!」と密かに願いながらコンサートに臨んだのですが,この日もダメでした 自席に座る時,右隣の高齢女性のバッグの持ち手がこちら側にはみ出して垂れ下がっていたのです
自席に座る時,右隣の高齢女性のバッグの持ち手がこちら側にはみ出して垂れ下がっていたのです どうやらバッグを左側に置いたまま座っていたようです.私が座ろうとすると,はみ出しに気が付いたらしく,持ち手をひっこめたので一安心しました.しかし,しばらくすると,またこちらに垂れ下がっているのです
どうやらバッグを左側に置いたまま座っていたようです.私が座ろうとすると,はみ出しに気が付いたらしく,持ち手をひっこめたので一安心しました.しかし,しばらくすると,またこちらに垂れ下がっているのです また気が付いたらしく引っ込めました.「この人は,自分が迷惑をかけているのは分かっているんだな
また気が付いたらしく引っ込めました.「この人は,自分が迷惑をかけているのは分かっているんだな 」と,心を許したのが大間違いでした
」と,心を許したのが大間違いでした 休憩後,またこちらに垂れ下がっているのです.他人に迷惑をかけているのが分かっているのなら,バッグを膝の上に乗せるか,床に置けば済む問題です.私には,同じ過ちを何度も繰り返す人の神経が理解できません
休憩後,またこちらに垂れ下がっているのです.他人に迷惑をかけているのが分かっているのなら,バッグを膝の上に乗せるか,床に置けば済む問題です.私には,同じ過ちを何度も繰り返す人の神経が理解できません しかし,今度はまったく気が付く気配さえありません
しかし,今度はまったく気が付く気配さえありません 音楽に集中するのは良いけれど,その前に他人の迷惑を考えろ
音楽に集中するのは良いけれど,その前に他人の迷惑を考えろ と叫びたい気持ちでした
と叫びたい気持ちでした 他国の領土に 自国の領土の如く土足で乗り出してくる某覇権国家と同じではないか
他国の領土に 自国の領土の如く土足で乗り出してくる某覇権国家と同じではないか コンサートを聴きに行くたびにこういう唯我独尊的自己チューに悩まされるのもいい加減イヤになってきます
コンサートを聴きに行くたびにこういう唯我独尊的自己チューに悩まされるのもいい加減イヤになってきます このブログにコメントをくださった みなみさん が指摘されているように,コンサートで最低限のマナーも守れない状況は「どんどんひどくなっている」としか言いようがありません
このブログにコメントをくださった みなみさん が指摘されているように,コンサートで最低限のマナーも守れない状況は「どんどんひどくなっている」としか言いようがありません
唯一の救いは,アンケートに協力したら,先着50人がもらえる「サントリーホール30周年クリアファイル」を手に入れることが出来たことです こういう時,通路側席は圧倒的に有利です
こういう時,通路側席は圧倒的に有利です

今週は25日(日)まで今日を含めてあと5回のコンサートが控えています このうち3回は「定期演奏会」なので隣席は”いつもの人”なので大丈夫だと思いますが,残りの2回が問題です
このうち3回は「定期演奏会」なので隣席は”いつもの人”なので大丈夫だと思いますが,残りの2回が問題です いったいどんな隣人が座るのか,今から不安にかられています
いったいどんな隣人が座るのか,今から不安にかられています
















 ラインアップは次の通りです
ラインアップは次の通りです








 ヴィオラには首席・篠崎友美の隣に,8月から正団員となったフォアシュピーラー・脇屋冴子がスタンバイしています.正団員おめでとう
ヴィオラには首席・篠崎友美の隣に,8月から正団員となったフォアシュピーラー・脇屋冴子がスタンバイしています.正団員おめでとう



 圧倒的なフィナーレでした.拍手とブラボーの嵐です
圧倒的なフィナーレでした.拍手とブラボーの嵐です

 私にはこういう人の神経が理解できません.休憩時間があったのですから,なぜ,演奏前に口に入れることをしなかったのでしょうか
私にはこういう人の神経が理解できません.休憩時間があったのですから,なぜ,演奏前に口に入れることをしなかったのでしょうか 考えがアメーと思います.もし,この人が定期会員だとすれば,毎回隣の席で聴くことになるわけで,先が思いやられます
考えがアメーと思います.もし,この人が定期会員だとすれば,毎回隣の席で聴くことになるわけで,先が思いやられます 新シーズンを迎えて事務局にも人事異動があったのでしょうか
新シーズンを迎えて事務局にも人事異動があったのでしょうか







 プログラムは①モーツアルト「オーボエ協奏曲ハ長調K.314」,②同「フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299」,③ベートーヴェン「交響曲第7番イ長調」です
プログラムは①モーツアルト「オーボエ協奏曲ハ長調K.314」,②同「フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299」,③ベートーヴェン「交響曲第7番イ長調」です


 親としては無事に帰ってくることを祈るばかりです
親としては無事に帰ってくることを祈るばかりです



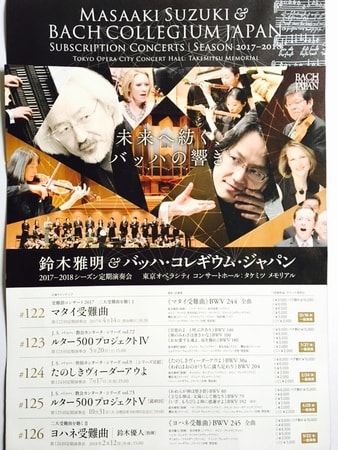
 このエッセイ集は1997年に講談社エッセイ賞を受賞しています
このエッセイ集は1997年に講談社エッセイ賞を受賞しています 著者の紹介はもういいですね.何度も紹介したので
著者の紹介はもういいですね.何度も紹介したので
 』
』 ブレジネフは思わず身震いしたほどだ.ところが,なんと向こうの方では,フルシチョフがマリリン・モンローと抱き合っているではないか
ブレジネフは思わず身震いしたほどだ.ところが,なんと向こうの方では,フルシチョフがマリリン・モンローと抱き合っているではないか



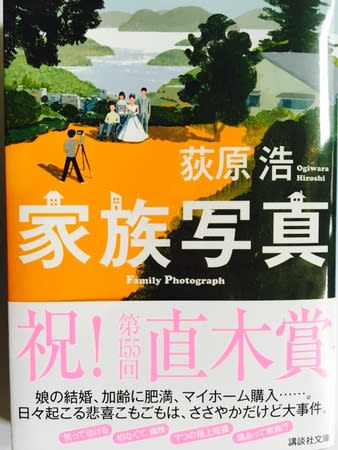






 しかし,よく考えると変です.ヴィオラが1人でチェロが3人います
しかし,よく考えると変です.ヴィオラが1人でチェロが3人います



 グラスは彼に対する怒りを生きる力に代え,奇跡的に死の淵から蘇りを果たす
グラスは彼に対する怒りを生きる力に代え,奇跡的に死の淵から蘇りを果たす



 ちなみに娘は小型船舶2級免許を持っています(自動車の免許は持っていないのに
ちなみに娘は小型船舶2級免許を持っています(自動車の免許は持っていないのに





 エリヤはイスラエルの神ヤハウエに仕えて,紀元前9世紀に生きた人で,混乱の最中にあったイスラエルで,神の言葉を代弁する預言者として劇的な生涯を送りました
エリヤはイスラエルの神ヤハウエに仕えて,紀元前9世紀に生きた人で,混乱の最中にあったイスラエルで,神の言葉を代弁する預言者として劇的な生涯を送りました

 取るに足らないことなので詳細は割愛します
取るに足らないことなので詳細は割愛します




 それは,50年前に氷山で行方不明になったジェフの元カノの遺体が発見されたという内容だった
それは,50年前に氷山で行方不明になったジェフの元カノの遺体が発見されたという内容だった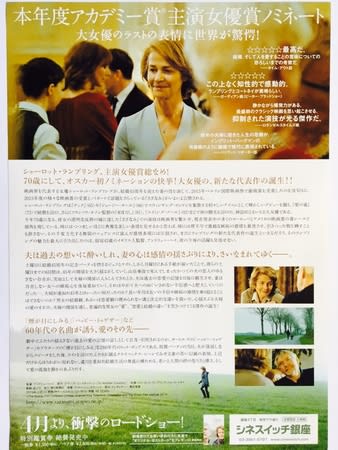
 そして現在,ジェフとケイトの間には子供はいない
そして現在,ジェフとケイトの間には子供はいない そうしたこともあって,男は,結婚前の元カノとのことは,本人が死亡していることもあって,「済んだこと」と割り切るけれど,女はそう簡単には割り切れない
そうしたこともあって,男は,結婚前の元カノとのことは,本人が死亡していることもあって,「済んだこと」と割り切るけれど,女はそう簡単には割り切れない



