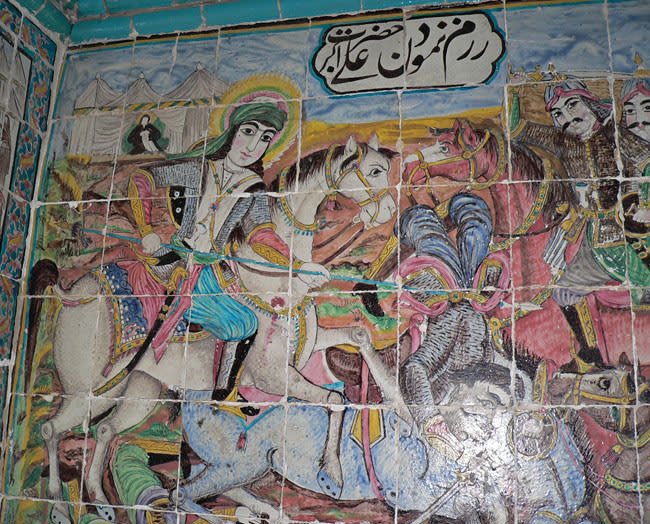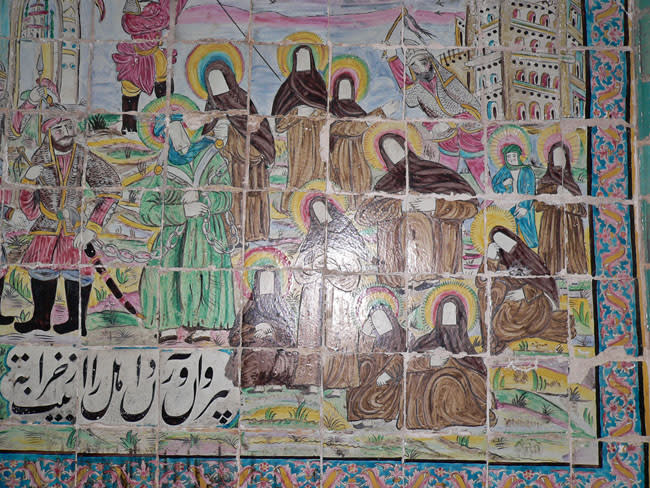一言、書かせて
来賓が100人!!!! 8000人の高齢者を「無料招待」 東京中央区 年間1億円の税金が、この意味不明な催し物につぎ込まれていることになる。 現代ビジネス
今年4月の統一地方選挙を前にして、目を疑うような高齢者(中心は、団塊の世代)への大盤振る舞いが発覚した。
実施されたのは、2022年9月8日(木)・9日(金)・13日(火)~15日(木)で、場所は歌舞伎座(東京都中央区銀座4-12-15)だ。
歌舞伎座を貸し切って、8000人超の高齢者が無料で招待された模様だ。
中央区議会議員高橋まきこ議員のブログ(9月21日)
<先日、5日間に渡る中央区敬老大会が開催されたと報告を受けましたので、中央区の高齢者に向けたお祝いについて、調べてみました。基本的に毎年、実施されています>
<コロナで久しぶりの同日に集まる「大会」となったそうです。今年は歌舞伎座を5日間、午前中に貸し切り、定員を超える申し込み希望があったそうです。例年、歌舞伎座、新橋演舞場、明治座を交替で会場にしているそうです。今年は、来賓が100人を含み、5日間で8,800人が観覧する、大規模なものでした>
なんと8800人と来賓100人が無料で歌舞伎を観劇した模様だ。
他観覧者のブログによると
「夫婦単位で申し込んだので、女房も1階席で私の隣だった。この席の料金は通常価格で『1万6000円』である」という入場料に加えて、豪華な幕内弁当が配布され、さらに「8月末に歌舞伎座のチケットを受け取った少し後に、また中央区からプレゼントがあった。
それは『買物券と食事券』が兼用のチケットで、3000円分が封筒に入っていた」のだという。
2万円を超える「大盤振る舞い」
歌舞伎座での豪華(無料)敬老大会では、「歌舞伎公演が始まる前に、今回から新らしく選出された中央区長の山●氏の挨拶である。
区長は日本橋の『山本海苔店』の副社長だった人である。
その次に中央区議会議長の挨拶が続き、更にいつものように警察署からの『詐欺』と『交通事故』の話があった」という。
この山●泰●区長は、現在、区長をしながら、株式会社山本海苔店相談役をしている人物だ。
今年、4月26日に改選を迎える。
実質的に2万円を超える大盤振る舞いをし、また、大盤振る舞いをした相手に歌舞伎座で挨拶をすることができて、今年の選挙も盤石といったところであろう。
オンラインのブログ上でも、招待を受けた高齢者(団塊の世代が中心)たちの喜びの声で溢れている。
敬老大会に関するお問い合わせ先としてオンライン上で公開されている中央区の福祉保険部高齢者福祉係(電話番号03-3546-5354。
午前8時30分から午後5時まで、土曜日・日曜日を除く)が、つくった「事業別行政評価シート」(令和4年度・令和3年度分)に、この歌舞伎座での高齢者接待について述べられている。
詳細が知りたい人は、気軽に問い合わせてみるのがいいだろう。
この乱痴気騒ぎの事業目的は、「『敬老の日』にちなみ、敬老買物件及び賀寿状の贈呈や、高齢者を区内劇場(歌舞伎座・明治座・新橋演舞場)に招待して敬老大会を開催することにより、高齢者の長寿を祝うとともに敬老の意を表し、福祉の増進を図る」のだという。
チケット代が8079万8400円が計上されていて、他にも全国共通すし券等の購入費に681万円、人件費1374万5752円などが計上されていて、年間1億円の税金が、この意味不明な催し物につぎ込まれていることになる。
税金をばら撒かず、必要なところに予算を使おうよ!
若者が切磋琢磨して働いているというのに。
一方若者の雇用問題は改善されず、若者の年金問題は暗雲状態。
一般人の福祉問題、税金値上げ
公共料金、食品などの値上げ
1/10の貧困
1/3が離婚
大学退学
奨学金利息、支払い困難
松竹株式会社って、そういう会社だったのね
バブル前の大手の予備校じゃあるまいし、、、
歌舞伎って自分で調べて自分で払って自分で楽しむものじゃなかったんだ、、、
だから、この冬の南座顔見世も、笑いに走っちゃったのね、、、
とはいえ
江戸時代から、團十郎が根付や小道具を使って宣伝をして、お互いに儲けちゃったりしてて、、、
歌舞伎ってそういう世界ですよね^^
芝居や筋書きは好きだけど、、、
海苔屋さんの名前まで出ちゃってさ、、
いい宣伝になってますね(爆笑)
山本さん^^
とかなんとか、
どなたかがおっしゃっていたような狗!?ような、、、
そんな気がいたしまする、はい!
せめて
せめて高齢者ではなく、
感性が研ぎ澄まされていて、
後に見る可能性がある
小学生か中学生に
見せてあげて!
伝統芸能の将来のためにも!
BUT
それでは、票が集まらないのね、はっはっは!
みなさま、
ありがとうございます^^
感謝いたします。