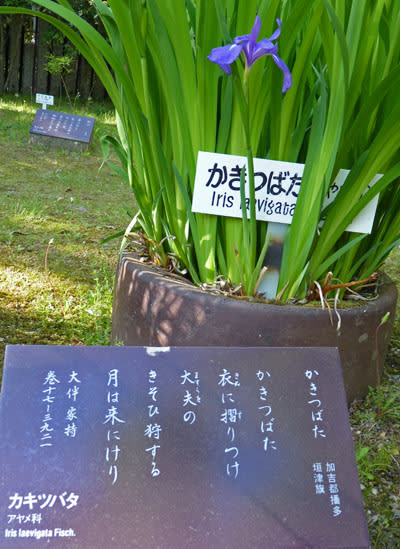先日植え付けたキューリとニガウリが一苗づつ、枯れましたでごじゃリまする。
おそらく連日の暑さと風によるものと思われます。
ぎゃふ~ん!
ぎゃふ~ん!で、ごじゃりまする。
おまけに十日以上もたつというのに、一行につるなしインゲンの芽が出てこないのでございまする。
はてさて、どうしてよいものか…。弱り果てておりまする。
ぎゃふ~ん!
ぎゃふ~ん!で、ごじゃりまする。
残るは トマト 四苗、キューリ 一苗、スイカ 二苗、カボチャ 一苗、ニガウリ 二苗
ところが今年は一向に大きくならないのでございまする。
ほんに今年は ぎゃふ~ん!
ぎゃふ~ん!で、ごじゃりまする。

おつきあい下さいまして、ありがとうございます。
とても嬉しいです☆