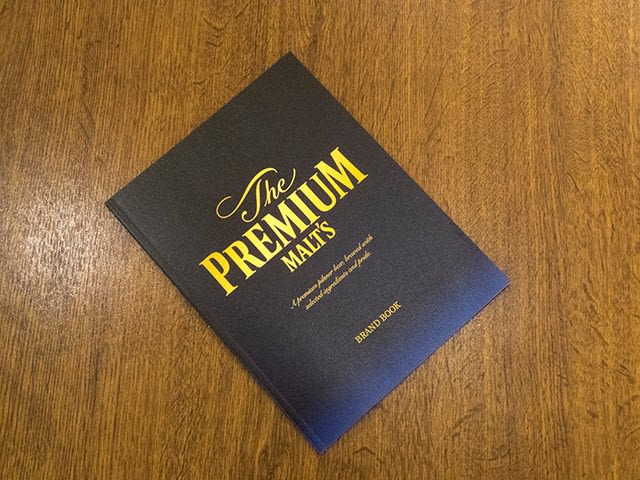♪中央フリーウェ~イ 調布基地を追~い越し…♪
(中略)
♪右に見える競馬場~、左はビール工場~♪
♪この道は、まるで滑走路、夜空に続く~♪
(後略)
ご存じ、ユーミンの『中央フリーウェイ』です。
今日、ここに出てくる『ビ-ル工場』サントリー東京・武蔵野ブルワリーに行ってきました。
行きたい行きたいと思いながら、それも冒頭の歌詞にある調布基地(今は調布飛行場)に37年も勤務していながら、一度も行ったことがなかったんです。
今回は私が以前「一度行ってみたいな~。」と言っていたのを覚えていて予約してくれた飲み友達(?)の家族と私達夫婦、計5人で出かけてきました。
説明付きの見学は1日2回、午後は14時時半からなので13時半前にJR中央線の武蔵小金井で待ち合わせ。
西国分寺経由、JR武蔵野線の府中本町から徒歩10分ちょっとです。
(JR南武線の分倍河原からだと送迎バスがあります。)
予定通り2時30分から説明が始まりました。
カメラ:OLYMPUS TG-4
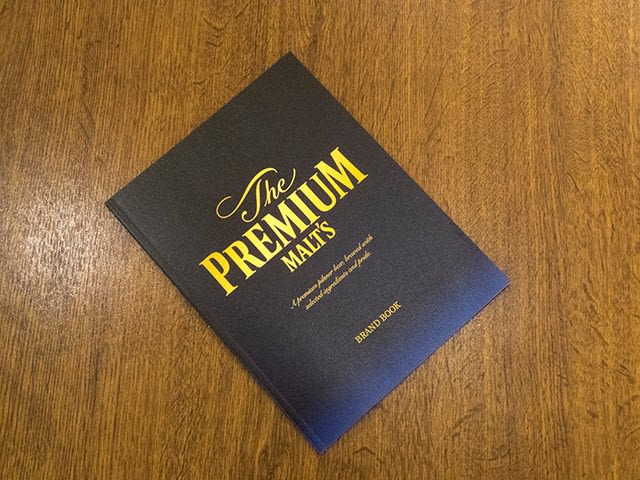
一通り簡単な説明があった後、まず小さなグラスでちょっとだけ試飲タイム。
おなじみのプレミアムモルツと今年新発売のプレミアムモルツ〈香る〉エールの飲み比べでした。

正直言って、この時点では〈香る〉エールの香りがやや鼻に付き、あまり好みじゃ無いな…と言う感想でした。
比較試飲後、工場見学です。


今日は機械が皆動いていたので、ビールが出来る課程をじっくり見せていただけました。
私はワイン工場とウィスキー工場を見学したことはありますがビール工場は初めてだったので、その規模の大きさには驚かされました。
1時間の見学を終え、いよいよお楽しみの試飲タイムです。(待ってました!)

まずはオリジナルのプレモルから…。
良い泡、出てますね~。

乾き物のおつまみが3点付き。
まずは一口…。
「こ、これは旨い!」(*^_^*)
出来たてで、つぎ方もパーフェクトなんでしょうね~。
とにかく泡がクリーミー。
これは自宅で缶ビールを注いだのではちょっと出来ない泡ですね。
味もスッキリしていながら丁度良い苦みとコクがあり、文句なし!
続いて先ほど香りがちょっと気になったプレミアムモルツ〈香る〉エールを試飲。
あれっ、先ほどに比べてずいぶん飲みやすく、これはこれでかなり好印象です。

もう一杯おかわり可能でしたので、もう一度オリジナルのプレモルをいただき、これにて終了。(全部で3杯飲めます。)
お土産(自分への)にオリジナルのビアグラスを買って帰りました。
説明をしてくれた女性に、今日撮った写真をブログに載せて良いか聞いたところ、「問題ありません。」とのことでしたので、今日の記事になりました。
最後においしいビールのつぎ方の見本を見せていただきましたので、明日は新しいグラスで試してみたいと思います。
明日、プレミアムモルツ買ってこなくっちゃ。(^_^)v