 物語イギリスの歴史(下) - 清教徒・名誉革命からエリザベス2世まで (中公新書 2319)の感想
物語イギリスの歴史(下) - 清教徒・名誉革命からエリザベス2世まで (中公新書 2319)の感想下巻はイングランドの議会政治の定着がメインテーマ。「大英帝国」の形成とその解体については他書に譲るということであっさり端折られていますが、イングランドの王室史・政治史としてはかなりまとまったものとなっています。
読了日:6月2日 著者:君塚直隆
 風と共に去りぬ 第4巻 (新潮文庫)の感想
風と共に去りぬ 第4巻 (新潮文庫)の感想南北戦争後の現実を受け入れ、とにかく状況に適応しようともがく人々、敗戦という現実を受け入れられずになすすべもないまま流されていく人々、そして黒人に対する北部人の視点と南部人の視点、このあたりの描写がリアル。我らがスカーレットは状況に適応しすぎてブラック企業の創業者みたいになってますが……
読了日:6月4日 著者:マーガレットミッチェル
 古代の女性官僚: 女官の出世・結婚・引退 (歴史文化ライブラリー)の感想
古代の女性官僚: 女官の出世・結婚・引退 (歴史文化ライブラリー)の感想日本の女官は中国・朝鮮半島のそれとは異なって君主の側妾ではなく、まさしく女性の官僚であったこと、男官との婚姻が普通に行われていたこと、親兄弟や夫の七光りで出世したというわけではなく逆に女官の七光りで出世した男性がいたこと、女官が平安中期の清少納言・紫式部ら女房につながつていくことなど、非常に興味深く読んだ。比較対象としての中国・朝鮮の女官の把握が少々洗いような気もするが、それは中国史なり朝鮮史なりの分野の研究者のやるべき仕事ということになるだろうか。
読了日:6月7日 著者:伊集院葉子
 軍国日本と『孫子』 (ちくま新書)の感想
軍国日本と『孫子』 (ちくま新書)の感想近代日本で『孫子』がどのように読まれ、あるいは読まれなくなったのかという話。終章の、戦後になって『孫子』がビジネスのための啓蒙書として読まれるようになっていく過程をもう少し丁寧に追ったら面白いのではないかと思った。
読了日:6月11日 著者:湯浅邦弘
 海洋帝国興隆史 ヨーロッパ・海・近代世界システム (講談社選書メチエ)の感想
海洋帝国興隆史 ヨーロッパ・海・近代世界システム (講談社選書メチエ)の感想海洋帝国としてのポルトガルの再評価、イギリスがヘゲモニー国家となるうえで電信が果たした役割など、読みどころは多い。第四章で触れられている三角貿易とアヘン戦争との関係について、アヘンの取り引きが当時の中国の貿易赤字の原因のすべてというわけではないのではないかという指摘が注目される。今後更なる研究の進展を期待したいところ。
読了日:6月13日 著者:玉木俊明
 古代中国を読む (岩波新書 青版 908)の感想
古代中国を読む (岩波新書 青版 908)の感想中国古代史に関して研究成果をまとめた本ではなく、研究の過程や『論語』『左伝』などの史料に対する見方をまとめた本。必然的に著者による『中国古代政治思想研究』所収の諸論考などのダイジェストにもなっています。中国古代史の研究とはどういうものかを知るには良い本かもしれません。
読了日:6月15日 著者:小倉芳彦
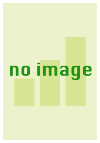 木簡と中国古代 (京大人文研漢籍セミナー)の感想
木簡と中国古代 (京大人文研漢籍セミナー)の感想冨谷至・目黒杏子・土口史記の三氏による講演録。土口氏による漢代木簡の長官署名の話が最も興味深かった。
読了日:6月17日 著者:富谷至,目黒杏子
 歴史と私 - 史料と歩んだ歴史家の回想 (中公新書 2317)の感想
歴史と私 - 史料と歩んだ歴史家の回想 (中公新書 2317)の感想日本近現代史の大家による回顧録。研究者による史料の発掘と保管、研究に対する同時代の影響、政治家等への聞き取り調査等々、ふんだんに盛り込まれている個別のネタに関して興味は尽きない。ただ、著者の「新しい歴史教科書を作る会」への関与については多少言及されているという程度。著者にとってはあまり触れたくない「黒歴史」事項ということなのだろうか。
読了日:6月19日 著者:伊藤隆
 教育という病 子どもと先生を苦しめる「教育リスク」 (光文社新書)の感想
教育という病 子どもと先生を苦しめる「教育リスク」 (光文社新書)の感想組体操、2分の1成人式、部活など学校での教育リスクについて論じている。根幹にあるのは無闇に感動と頑張りを求める日本の社会の問題ということになりそうだ。衝撃的だったのは、「柔道発祥の地」である日本の学校で死亡・重傷といった柔道事故が多発してきたのに対して、欧米では安全指導がはかられ、そのような事故がほとんど起きていないということ。もっとも、柔道事故に関しては日本でも改善がはかられているとのことだが…
読了日:6月20日 著者:内田良
 完訳 楊家将演義 上巻の感想
完訳 楊家将演義 上巻の感想待望の楊家将演義(正確には『北宋志伝』)の翻訳だが、序盤の呼延賛がメインのあたりはかなり話がグダグダだなと。楊家の話がメインとなり、楊大郎が太宗の身代わりとなって死ぬあたりから安心して読めるようになります。楊家将に関してはちゃんと起承転結をつけて、各バージョンから有名エピソードを過不足なくまとめた編訳版の刊行が望まれるのかもしれない。(北方謙三の『楊家将』は残念ながらその役割を果たしていません。)
読了日:6月22日 著者:
 楊家将演義 読本の感想
楊家将演義 読本の感想楊家将を題材とした演劇、映像メディアでの展開、物語に登場する神仙など、楊家将に関する興味深い話題が盛り込まれている。ただ「楊家将演義の舞台となった時代」の章については、同章の論考が所定の役割をあまり果たせておらず、かつ本書の他の章や、同時刊行の訳本の巻末の解説がその役割を果たしているので、この章自体が不要であったと思う。
読了日:6月26日 著者:
 中国史(下) (岩波文庫)の感想
中国史(下) (岩波文庫)の感想上下巻通読してみて、通史としては「尖っている」分、21世紀の今になって読み返すと問題意識の古さが目に付く。却ってこれ以前に書かれた貝塚茂樹の『中国の歴史』の方が現在でも通用するすんなり読める部分が多いのではないか。その反面、現代史(最近世史)に関しては、外モンゴル問題の部分以外はそれほど外したことを書いてないなと感じたが……
読了日:6月29日 著者:宮崎市定















