檜山に住んでいた頃 サマーキャンプ
サマーキャンプ といえば鴎島、熊石、乙部、奥尻・・・そして瀬棚にテン泊した。いまではどこのキャンプ場も綺麗に整備されてワイルドな環境ではなくなってしまった
といえば鴎島、熊石、乙部、奥尻・・・そして瀬棚にテン泊した。いまではどこのキャンプ場も綺麗に整備されてワイルドな環境ではなくなってしまった が、瀬棚町の立象山(標高95m)近くにあるキャンプ場「せたな青少年旅行村」からの絶景は今でも忘れられない
が、瀬棚町の立象山(標高95m)近くにあるキャンプ場「せたな青少年旅行村」からの絶景は今でも忘れられない 。立象山は「巨大な象が立っている姿に似ていることから」名付けられたそうだ(そうは見えない)が、山頂からは360度のパノラマが広がり、狩場山や遊楽部岳、日本海に浮かぶ奥尻島まで望める
。立象山は「巨大な象が立っている姿に似ていることから」名付けられたそうだ(そうは見えない)が、山頂からは360度のパノラマが広がり、狩場山や遊楽部岳、日本海に浮かぶ奥尻島まで望める 夜は、漁り火が点り幻想的な眺めだ
夜は、漁り火が点り幻想的な眺めだ 久しぶりに登ったら
久しぶりに登ったら 景勝・三本杉岩とともに発電用・風車群に目を引く。日本初の洋上風力発電風車で「風海鳥(かざみどり)
景勝・三本杉岩とともに発電用・風車群に目を引く。日本初の洋上風力発電風車で「風海鳥(かざみどり) 」と名付けられ「新エネ100選」に選ばれている。
」と名付けられ「新エネ100選」に選ばれている。 山頂から見下ろす三本杉岩に沈む夕日は言葉を失うほどの美しさだ。
山頂から見下ろす三本杉岩に沈む夕日は言葉を失うほどの美しさだ。 奥尻を眺めながら走る海岸線はいつみても美しいが、平成5年の「北海道南西沖地震」は絶対忘れてはならない
奥尻を眺めながら走る海岸線はいつみても美しいが、平成5年の「北海道南西沖地震」は絶対忘れてはならない 。奥尻島を中心に、火災や津波で大きな被害を出し、死者202人、行方不明者28人を出している。その年、社会人1年生で故郷を思い胸が痛んだ。帰省などで用があって瀬棚町を通る際
。奥尻島を中心に、火災や津波で大きな被害を出し、死者202人、行方不明者28人を出している。その年、社会人1年生で故郷を思い胸が痛んだ。帰省などで用があって瀬棚町を通る際 は「事平羅神社」「姥神大神宮」などに寄って参拝する
は「事平羅神社」「姥神大神宮」などに寄って参拝する 露国軍艦アレウト号乗組員遭難慰霊碑で参拝をする勘違いの人もいるが
露国軍艦アレウト号乗組員遭難慰霊碑で参拝をする勘違いの人もいるが ・・・。瀬棚には津波防水と関連して、狩場渓谷の馬場川下流には防潮水門がある
・・・。瀬棚には津波防水と関連して、狩場渓谷の馬場川下流には防潮水門がある 津波が川から進入するのを防ぐために整備されたもので、震度4以上のときなどには自動的にゲートが下がる仕組みになっている。ユニークな形状で、土木景観としても楽しめる。展望テラスから、三本杉岩、立象山などが見える。また、過去に数回、広報コンクールの審査に携わったことがあるが、瀬棚の観光ポスターは実に面白い
津波が川から進入するのを防ぐために整備されたもので、震度4以上のときなどには自動的にゲートが下がる仕組みになっている。ユニークな形状で、土木景観としても楽しめる。展望テラスから、三本杉岩、立象山などが見える。また、過去に数回、広報コンクールの審査に携わったことがあるが、瀬棚の観光ポスターは実に面白い 町民をモデルに起用するなどユニークなアイデアで知られる観光ポスターだ。韓国ドラマの「冬のソナタ」ではなく「夏のセタナ」や「やぁせたな」「この夏、せたなでヴィクトリー」など予算が苦しい中で町職員による手作りポスターはテレビなどにも取り上げられ反響が大きかった。「また、せたな(待たせたな)」「幸せた(だ)な」とか親父ギャグみたいのもあって面白い。ポスターで笑うのもいいが、「せたな観光協会」自賛のフットパスコースを歩いてみるのもいい
町民をモデルに起用するなどユニークなアイデアで知られる観光ポスターだ。韓国ドラマの「冬のソナタ」ではなく「夏のセタナ」や「やぁせたな」「この夏、せたなでヴィクトリー」など予算が苦しい中で町職員による手作りポスターはテレビなどにも取り上げられ反響が大きかった。「また、せたな(待たせたな)」「幸せた(だ)な」とか親父ギャグみたいのもあって面白い。ポスターで笑うのもいいが、「せたな観光協会」自賛のフットパスコースを歩いてみるのもいい
 立象山かけ降りる
立象山かけ降りる 全部で567段
全部で567段
 沈む夕日に~
沈む夕日に~ また津波がことを祈る
また津波がことを祈る
函館市内に実家はあるが住んだことはない。子供の頃は、木古内町や江差町の函館市近隣町村(いわゆる道南)に住んでいたため、函館はデパートや映画、コンサートを楽しむ都会的イメージが幼少の心の中にある 。両町からJR等
。両町からJR等 で2時間以内で行けたが、はじめて函館山の山頂まで行ったのは18歳のときだ。近くに住んでいると、観光地というものは何かの機会がなければ、足を向けないものだ。さて、小学生の頃だったか函館市内に祖父母の生家があり、遊びに行ったとき、「函館どっぐ」で働いていた祖父から「函館山は、日露戦争前に構築した要塞の山だ。津軽海峡と函館港を守るため、日本陸軍が造った。砲台や発電所、観測所の施設がいまでもたくさんある。軍事機密地帯で一般人の立ち入りは禁止
で2時間以内で行けたが、はじめて函館山の山頂まで行ったのは18歳のときだ。近くに住んでいると、観光地というものは何かの機会がなければ、足を向けないものだ。さて、小学生の頃だったか函館市内に祖父母の生家があり、遊びに行ったとき、「函館どっぐ」で働いていた祖父から「函館山は、日露戦争前に構築した要塞の山だ。津軽海峡と函館港を守るため、日本陸軍が造った。砲台や発電所、観測所の施設がいまでもたくさんある。軍事機密地帯で一般人の立ち入りは禁止 され、当時は地図上も空白だった。そのため、貴重な小動物、昆虫、植物がいつまでも残されている」と聞かされた。実際、函館山には、約600種の植物
され、当時は地図上も空白だった。そのため、貴重な小動物、昆虫、植物がいつまでも残されている」と聞かされた。実際、函館山には、約600種の植物 に、約150種の野鳥が観測されている。函館に年数回、登山や所用で帰省することがあるが、大沼のトンネルを抜け、大野平野越しに函館山が見えると、「函館山要塞」からいまにも弾が飛んできそうな感じがしてしまう。既に全10コースを8回ほど踏破しているが、春の連休前後や紅葉
に、約150種の野鳥が観測されている。函館に年数回、登山や所用で帰省することがあるが、大沼のトンネルを抜け、大野平野越しに函館山が見えると、「函館山要塞」からいまにも弾が飛んできそうな感じがしてしまう。既に全10コースを8回ほど踏破しているが、春の連休前後や紅葉 の10月、元旦の初日の出が一番のおすすめである。山頂から駒ヶ岳、下北・津軽半島、大千軒岳、植物には、ナナカマドに観音山のツルリンドウ、アキノギンリョウソウ、薬師山のダイモンジソウ、フユノハナワラビ、フクジュソウ、キクザキイチゲ、エンレイソウ、ネコノメソウ、シラネアオイ・・・頭が悪いのでガイドさんから説明を受けないと、いまでも花名と一致しないが、年中、軽ハイクに適した山である。追伸:実は、新しくなった「函館山ロープウェイ」をまだ乗ったことがない
の10月、元旦の初日の出が一番のおすすめである。山頂から駒ヶ岳、下北・津軽半島、大千軒岳、植物には、ナナカマドに観音山のツルリンドウ、アキノギンリョウソウ、薬師山のダイモンジソウ、フユノハナワラビ、フクジュソウ、キクザキイチゲ、エンレイソウ、ネコノメソウ、シラネアオイ・・・頭が悪いのでガイドさんから説明を受けないと、いまでも花名と一致しないが、年中、軽ハイクに適した山である。追伸:実は、新しくなった「函館山ロープウェイ」をまだ乗ったことがない 。これは最後の未踏コースとしてとっておきたいと思う。 函館山ハイキング地図
。これは最後の未踏コースとしてとっておきたいと思う。 函館山ハイキング地図
 昭和初期の函館
昭和初期の函館 厳冬期の函館
厳冬期の函館 夏夜景(懐中電灯のみで登れる)
夏夜景(懐中電灯のみで登れる) 上空からの函館山
上空からの函館山 戦斗指令所跡
戦斗指令所跡 千畳敷砲台跡
千畳敷砲台跡 地下砲側庫のニョロニョロ氷柱
地下砲側庫のニョロニョロ氷柱 観音コース
観音コース
長沼町にある馬追丘陵は札幌市内からのアクセス も良く積雪期の快晴の日に何度か登っている。丘陵に広がる広大な秋の田園風景も最高だ。長沼温泉から馬追山頂を経て長官山までの縦走が一番楽しい。自衛隊のミサイル基地
も良く積雪期の快晴の日に何度か登っている。丘陵に広がる広大な秋の田園風景も最高だ。長沼温泉から馬追山頂を経て長官山までの縦走が一番楽しい。自衛隊のミサイル基地 もある山だが、馬追丘陵の山麓には「馬追の名水
もある山だが、馬追丘陵の山麓には「馬追の名水 」や、長官山の山頂付近には馬追文学台(222.5m)がある。辻村もと子の小説「馬追原野」
」や、長官山の山頂付近には馬追文学台(222.5m)がある。辻村もと子の小説「馬追原野」 の文学碑だ。長沼の開村前夜を描いた作品で、昭和19年に第1回樋口一葉賞を受賞している。学生時代に木村真佐幸教授の授業で「たけくらべ」「にごりえ」で有名な樋口一葉を勉強した記憶があるが、いまでは女性作家だったことしか記憶にない
の文学碑だ。長沼の開村前夜を描いた作品で、昭和19年に第1回樋口一葉賞を受賞している。学生時代に木村真佐幸教授の授業で「たけくらべ」「にごりえ」で有名な樋口一葉を勉強した記憶があるが、いまでは女性作家だったことしか記憶にない 。それはさておき、これを機に新しい町づくりの始まりを告げようと建てられた文学碑である。馬追山頂は瀞台ともいわれ、1986年に内田瀞が地籍調査で登り、その功労をたたえて命名されている。一等三角点の頂上からは長沼の市街地や、日本海、手稲山から樽前山まで大パノラマである。馬追の名水は一年を通じて冷たい水が出てくるが濁ることもある。維持管理のための募金は忘れずに。また、馬追山には、かつてオオムラサキ
。それはさておき、これを機に新しい町づくりの始まりを告げようと建てられた文学碑である。馬追山頂は瀞台ともいわれ、1986年に内田瀞が地籍調査で登り、その功労をたたえて命名されている。一等三角点の頂上からは長沼の市街地や、日本海、手稲山から樽前山まで大パノラマである。馬追の名水は一年を通じて冷たい水が出てくるが濁ることもある。維持管理のための募金は忘れずに。また、馬追山には、かつてオオムラサキ が数多く生息していたようだが、長沼町の「馬追野花の会」が、国蝶・オオムラサキの人工繁殖に成功し、初夏、成虫を放していた。たくさんのオオムラサキが舞う馬追丘陵を見たいと早く願っている。(オオムラサキは栗山町も有名)栗山の御大師山(114.8m)と長沼の靜台(273m)と北広島の椴山(97m)でウオーミングアップ
が数多く生息していたようだが、長沼町の「馬追野花の会」が、国蝶・オオムラサキの人工繁殖に成功し、初夏、成虫を放していた。たくさんのオオムラサキが舞う馬追丘陵を見たいと早く願っている。(オオムラサキは栗山町も有名)栗山の御大師山(114.8m)と長沼の靜台(273m)と北広島の椴山(97m)でウオーミングアップ
第4話に掲載した「江差町」の隣町にある乙部町。この町に乙部岳(1017m)通称「九郎岳」がある。江差町の元山や高台などからもよく見える、子供の頃から見慣れた山である。道南の山にしては雪解けが遅く6月上旬まで雪が残る。渡島半島の分水嶺の山 である。山名は牛若丸の九郎判官源義経に由来している。道内には義経が生き延びて蝦夷地に渡ったとのいくつかの伝説があるが、江差町や上ノ国町など道内各地に義経伝説は多い。本別町の義経山(294m)も有名だ。学生の頃に一度、車道を経て姫待峠から乙部岳に登った記憶があるが、昨年、乙部岳町民山開きに参加し二日酔いの中、同僚らと正規のルートで登った。さすがに前日の深夜までの深酒は急登にこたえたが、途中、霧が晴れ、最高の天気となった。乙部町登山愛好会の萬木英光会長が「行者穴ルート」と「祠ルート」の車道歩きを車で送ってくれて、時間短縮できた。たったそれだけでも気分的に嬉しかった。登り3時間半、下り2時間の、のろまなカメ歩き登山となってしまったが。九郎岳神社奥宮本殿を訪れるなど歴史巡りも楽しめた。いつか残雪期には、隣接の九郎岳(969.7m)まで歩いてみたい。さて、この山を機に同僚のA氏は登山にはまり、毎週末どこかに出かけている山男となってしまった。
である。山名は牛若丸の九郎判官源義経に由来している。道内には義経が生き延びて蝦夷地に渡ったとのいくつかの伝説があるが、江差町や上ノ国町など道内各地に義経伝説は多い。本別町の義経山(294m)も有名だ。学生の頃に一度、車道を経て姫待峠から乙部岳に登った記憶があるが、昨年、乙部岳町民山開きに参加し二日酔いの中、同僚らと正規のルートで登った。さすがに前日の深夜までの深酒は急登にこたえたが、途中、霧が晴れ、最高の天気となった。乙部町登山愛好会の萬木英光会長が「行者穴ルート」と「祠ルート」の車道歩きを車で送ってくれて、時間短縮できた。たったそれだけでも気分的に嬉しかった。登り3時間半、下り2時間の、のろまなカメ歩き登山となってしまったが。九郎岳神社奥宮本殿を訪れるなど歴史巡りも楽しめた。いつか残雪期には、隣接の九郎岳(969.7m)まで歩いてみたい。さて、この山を機に同僚のA氏は登山にはまり、毎週末どこかに出かけている山男となってしまった。
幼少の頃、江差町に13年間住んでいたことがある。住居はもう老朽化し取り壊されて存在していない。子供の頃、通学していた江差小学校の校歌「 笹山晴れて風爽やかに光り輝く江差の街よ~
笹山晴れて風爽やかに光り輝く江差の街よ~ 」は今でもはっきりと歌える。江差の町民に親しまれて来た「笹山さん」の頂上には「笹山稲荷神社」がある。今でも続いているのだろうか?年2回ほど例大祭には多くの人たちが山に登る。「笹山」は漁の神様だよ
」は今でもはっきりと歌える。江差の町民に親しまれて来た「笹山さん」の頂上には「笹山稲荷神社」がある。今でも続いているのだろうか?年2回ほど例大祭には多くの人たちが山に登る。「笹山」は漁の神様だよ と教えられられたが、笹山から流れる豊部内川ではウグイ
と教えられられたが、笹山から流れる豊部内川ではウグイ しか釣った記憶しかない。昔のニシン漁での港の繁栄を祈った山だと思うが、探検に釣り、山菜取りなどよく遊んだテリトリーだ。また、住んでいた住居の裏山に「蝦夷舘山」(62mほど)があって、こちらも年中良く遊んでいた低山である。「蝦夷舘山」の山麓には回船問屋を営んでいた「旧関川家」がある。いまでは「えぞだて公園」という名称になっている。頂上には「蝦夷館山観世音菩薩」が祭られ、300年以上も地域の人たちを守り続けている。秋や冬には鴎島と日本海が見えるいいところだ。春の桜もいい。江差町の話題になると豊川町東山の風景を思い出す
しか釣った記憶しかない。昔のニシン漁での港の繁栄を祈った山だと思うが、探検に釣り、山菜取りなどよく遊んだテリトリーだ。また、住んでいた住居の裏山に「蝦夷舘山」(62mほど)があって、こちらも年中良く遊んでいた低山である。「蝦夷舘山」の山麓には回船問屋を営んでいた「旧関川家」がある。いまでは「えぞだて公園」という名称になっている。頂上には「蝦夷館山観世音菩薩」が祭られ、300年以上も地域の人たちを守り続けている。秋や冬には鴎島と日本海が見えるいいところだ。春の桜もいい。江差町の話題になると豊川町東山の風景を思い出す 。
。
 笹山稲荷神社
笹山稲荷神社  蝦夷館山
蝦夷館山
前日記参照 http://blog.goo.ne.jp/yoshikatsuisobemirimiri1018/e/5117f45cfba4bdccd7c8679a3429d337










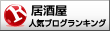


 馬追山頂
馬追山頂 長官山頂(冬)
長官山頂(冬) 山麓での芋掘り(秋)
山麓での芋掘り(秋) 国蝶オオムラサキ
国蝶オオムラサキ 長沼ジンギスカンも格別な味
長沼ジンギスカンも格別な味
 登山口
登山口 馬追の名水
馬追の名水

 山開き拝礼
山開き拝礼 行者洞
行者洞 頂上
頂上 遠くに遊楽部山塊
遠くに遊楽部山塊 九郎嶽社
九郎嶽社





