関西、北陸を車で巡回して昨夜帰還しました。
最近の石油業界は、ようやく投資意欲が盛んになってきました。
ガソリン中心のSS店頭販売中心の企業では閉鎖がかなりの勢いで進行中ですが、
そんな動きを尻目に
中間溜分などの販売比率が高い企業はかなり収益が上向いてきたようです。
減販動向とはいえ、全国的には1993年~95年の頃のボリュームをキープしているわけです。
一方では、SSの閉鎖がこれだけ進行していますので、
当然のことながら、一社当たりの販売数量はかなり増えているということになります。
中間溜分の販売比率が高い企業は栄養のバランスが良好な「健康優良児」といった感じですね。
SS店頭オペレーション中心でガソリンの販売比率が高い企業は栄養が偏っている子供のようで、ガソリン比率が異常に高い企業はさしずめ「肥満児」で、金額の割に企業としての「租利益率」が引くような感じです。
今年は、どこも外販オペレーションと配送体制の強化が中心です。
「SS店頭」を飛び出して、外販強化が盛んです。
特に、灯油配送を起点とする「新たな外販ビジネス」
軽油のパトロール給油などの専門的な業務は専門業者が減少しており、
機動力を持った企業の一社当たりの売上はかなり上向いてきそうです。
卸売り、や中間流通における価格設定動向についても、
適正値取りの意識が強くなっているようです。
すでに直売体制が構築されている大手特約店レベルでは
無理な拡販をしなくても、ある程度の収益が見込める収益体制が完成しつつあり、
焦って拡販して「不良債権」を発生させる必要はないという考え方が定着しそうです。
これからは、CODなどで札びらを切られて、安売りというパターンは減ってくるのでしょう。
節度のある価格設定意識が出てきて、ようやく
石油業界の「次の時代」が薄らと見えてきたような気がしています。
最近の石油業界は、ようやく投資意欲が盛んになってきました。
ガソリン中心のSS店頭販売中心の企業では閉鎖がかなりの勢いで進行中ですが、
そんな動きを尻目に
中間溜分などの販売比率が高い企業はかなり収益が上向いてきたようです。
減販動向とはいえ、全国的には1993年~95年の頃のボリュームをキープしているわけです。
一方では、SSの閉鎖がこれだけ進行していますので、
当然のことながら、一社当たりの販売数量はかなり増えているということになります。
中間溜分の販売比率が高い企業は栄養のバランスが良好な「健康優良児」といった感じですね。
SS店頭オペレーション中心でガソリンの販売比率が高い企業は栄養が偏っている子供のようで、ガソリン比率が異常に高い企業はさしずめ「肥満児」で、金額の割に企業としての「租利益率」が引くような感じです。
今年は、どこも外販オペレーションと配送体制の強化が中心です。
「SS店頭」を飛び出して、外販強化が盛んです。
特に、灯油配送を起点とする「新たな外販ビジネス」
軽油のパトロール給油などの専門的な業務は専門業者が減少しており、
機動力を持った企業の一社当たりの売上はかなり上向いてきそうです。
卸売り、や中間流通における価格設定動向についても、
適正値取りの意識が強くなっているようです。
すでに直売体制が構築されている大手特約店レベルでは
無理な拡販をしなくても、ある程度の収益が見込める収益体制が完成しつつあり、
焦って拡販して「不良債権」を発生させる必要はないという考え方が定着しそうです。
これからは、CODなどで札びらを切られて、安売りというパターンは減ってくるのでしょう。
節度のある価格設定意識が出てきて、ようやく
石油業界の「次の時代」が薄らと見えてきたような気がしています。














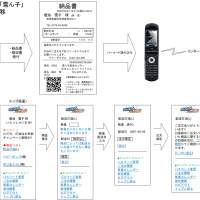



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます