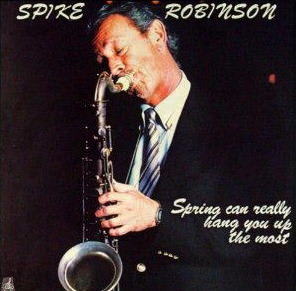長年、?マークの本作にメスを。途中、辛気臭くなり止めようと思いましたが・・・・・・・・・
所有するレコードはワナー・パイオニアから1972年に日本でオリジナル・リリースされたP-6109A(ATLANTIC)で、「幻の名盤読本」(1974年)に掲載されたものと同じナンバー。
ところが、「幻の名盤読本」に書かれている内容と本体と(に書かれいる)内容が違う。
まず、「幻の名盤読本」では‘INSIDE HI-FI’のセッション時の未発表3曲を含めすべて「未発表もの」とされているが、本体には‘INSIDE HI-FI’で既に発表されている1曲が入っている。
確かに本体のライナー・ノーツの冒頭にその旨がサラッと書かれていて、ディコグラフィーをコピペしたデータもそうなっている。ただ、ディコグラフィーも見慣れているベテランならともかく、初めてディコグラフィーを見る人には暗号を解読するようなものかもしれない。かって自分がそうでした。また、直接、本作と関係ないLP 1217(WITH WARNE MARSH)のデータも記載されており、ちょっと煩わしい。
ま、この種のレコードを買う人は、かなり詳しいファンなのでライナー・ノーツも予備知識を前提に書かれたフシがあります。
問題となるダブっている一曲は‘Nesuhi's Instant’ですが、「幻の名盤読本」では代わりに‘ブルース’が入っている。
しかし、‘INSIDE HI-FI’のセッション時に‘ブルース’という未発表テイクは存在しない。
それと、メンバーが違います。とにかくややこしいですね。
「幻の名盤読本」では‘INSIDE HI-FI’のメンバーは省略?され、コニッツ(as)、ディック ・カッツ(p)、ルロイ・ヴィネガー(b)、ロニー・フリー(ds)、1956年録音と記載されてる。
また同読本のディック ・カッツの‘PIANO &PEN’でもカッツが本作に参加している、とコメントされています。
一方、本体では、3曲は‘INSIDE HI-FI’ の1956年9月26日のセッション・メンバー、コニッツ、モスカ、インド、スコット、残りの6曲はコニッツを除き「不明」となっています(1956年12月21、22日N.Y.Cで録音となっている)。
で、上述の‘ブルース’は実はこの「不明」のセッション時のテイクの一つ。
ただし、本体のライナー・ノーツの左下に虫めがねが要る位、細かい字でレコーディング・データが載っていますが、side2-4(未発表テイク)が欠落している。校正ミスですが意外に読み手を迷わせます。
更に、後年の資料では、この「不明」セッションは、コニッツの他、J・ロウルズ(p)、L・ヴィネガー(b)、S・マン(ds)、録音はロサンジェルスとなっている。
ここまでくると、もう、どうでもいいです。
ただ、言える事は「幻の名盤読本」にupされた内容のレコードが、実在したのでしょうか?
なお、本作を掲載しているジャズ本がありますが、中には「このアルバムが大好き」と書きながらメンバーを、全てコニッツ、モスカ、インド、スコットとイージーに片付けている本もありました。これは論外です。
ま、どうでもよろしいですが。
内容は、コニッツ自ら「何かに取り憑かれていたようだ」と回想する時期に比べれば確かに緩みはありますが、どんな大打者でも毎回、ホームランを打てるワケでもなく、右中間に流し打ち二塁打といったところでしょうか。
‘You'd Be So Nice To Come Home では‘Kary's Trance’のフレーズを織り込むなど、余裕あるプレイを聴かせます。
‘Don't Blame Me’、片想いの心模様をasに乗せ、さりげなく語り掛けるコニッツのプレイに耳が固まる。
本作のリリースに当たり、関係者の尽力も米国の企業体質に翻弄された感が強いけれど、「WORTH WHILE 」(聴く価値ある)のタイトル、間違っちゃいません。