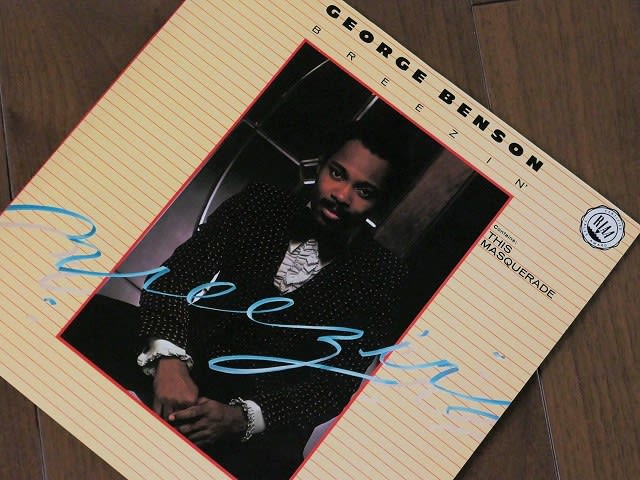その昔、ジャズ喫茶全盛時(1960年代)にコアなファンから熱烈な支持を受けた一枚。
インパルスと3年間・5万ドルという破格の条件で契約し、「アフリカ」を既に録音した後、アトランティックに置き土産?としてレコーディングしたもの(1961.5.25)。恐らく3者の間で円満解決した結果だろう。
A面に配されたタイトル曲のエキゾチックな香りと「マイ・フェイヴァリット・・・・」と同じ3/4拍子、そして2ベースからなる重厚なサウンドは正に当時のジャズ喫茶の空間にピッタリと嵌る。GEORGE LANEとクレジットされているas・fl奏者はE・ドルフィーで契約上の縛りがあったのだろう。
B面の”Dahomey Dance”、”Aisha”を含め本作の特長はややもするとコルトレーンのソロに偏重されがちな所がなく、コルトレーン、ドルフィー、ハバード、マッコイのソロがバランス良く収められている点です。
今回、フォーカスを当てた曲は、LPの収録時間の制限でオリジナル盤から外され、1970年に未発表集としてリリースされた”THE COLTRANE LEGACY”のなかで初めて日のを見た曲でCD化の際にボナース・トラックとして追加された。当初は”Untitled Original Ballad”とされていたが、後にビリー・フレイジャーという人物の”To Her Ladyship”と判明しています。
気品を漂わす魅力的なメロディを曲想に沿い三管が粛々と奏でていく展開は聴き終えた後、カタルシスに似たものを覚える。
聴きものはコルトレーン(ss)とドルフィー(fl)に挟まれながら、まだ23歳に成り立てとは思えぬコクのあるバラード・プレイを綴るハバードのtp、一年前、BNに初リーダー作を吹き込んだばかりだが早くも頭角を現している。一歩も二歩も二人の後に控えながら、第三の男を完璧に熟している。大したものですね。
また、ハバードと同い年で先月、惜しくもこの世を去ったマッコイは余程、この曲の流れに気分が乗ったのか、鼻歌交じりでpを弾いている。思いの外、図太い神経の持ち主ですね、70年代もこの味を貫けば良かったのに・・・・・・
もう一つ、注目する点があります。総じてコルトレーンのアトランティック盤の音はあまり芳しくないと言われていますが、本作は例外で、唯一、エンジニアがPHIL RAMONEに代わっている。PHIL RAMONEと言えば、直ぐJ.J.ジョンソンの名作”J.J.' BROADWAY”(VERVE)の好録音を思い出しますが、他にゲッツ/ジルベルト等々も担当している。わが国ではエンジニアと言えばRVG一辺倒に近いが、RAY HALLとかPHIL・RAMONE等々の優れたエンジニアにもっと目が向けられても良いのではないかな。後年はむしろプロデューサーとしての名声が高く、B・ジョエルの「ニューヨーク52番街」などを手掛けている。
話を戻すと、エンディングでコルトレーンがasに持ち替えたとの情報がありますが、自分の耳では定かに解りません。ただ、ssともtsとも違う感じも受けます。
本作に集まったメンバー全員、上昇気運に乗った人達ばかりで、過激さはないけれどモチベーションは頗る高い。
”OLE”を聴くなら”To Her Ladyship”が加えられたCDがベストと思います。