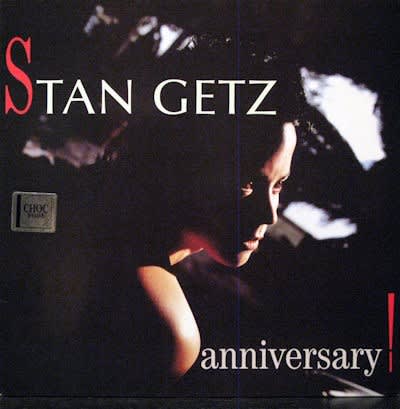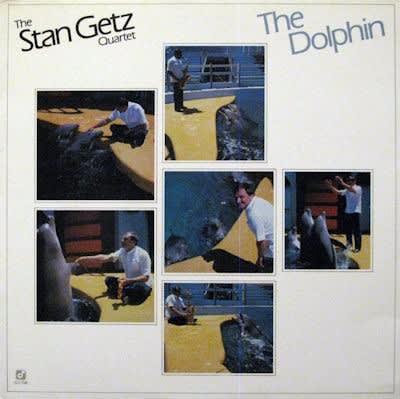Getzのレコードを全て聴いたわけではないが、ガイド・ブック等でよく紹介されている初期の作品より、晩年期と言うにはちょっと長いけれど、80年代のアルバムの方が好き。
Jazzを聴き始めた60年代後半、当時のジャズ・シーンの中でゲッツの存在は、乱暴な言い方をすれば「蚊帳の外」で‵SWEET RAIN’と言った秀作もあまり話題に上らず、ボサノヴァ・ジャズのイメージが強かったし、ゴシップも多かった。それが影響していたわけではないけれど、若手メンバーを積極的に取り入れた作品に、いま一つ核心的な姿を見出せず縁遠くなっていたのは事実。
ところが、期待もせず手に入れた‵VOYAGE’(1986年)に「これだ!」と確信し、この頃の作品を中心に時代を遡った。だから、一般的なジャズ・ファン、ひょっとして多くのゲッツ・ファンとも聴く支点が違うかもしれない。
1987年7月6日、あのお馴染み「クラブ・モンマルトル」でライブ・レコーディングされた‛ANNIVERSARY’。
メンバーは‛VOYAGE’とbがR・リードに替わっただけ。J・マンデルの‵El Cahon’、‵I Can't Get Started’、‵Stella By Starlight’、‵Stan's Blues’、全4曲、各10~12分と充分、時間を掛けている。聴き所は、耳の肥えたファンの前で、さんざん手垢がが付いている‵I Can't Get Started’、‵Stella By Starlight’をどう料理するか?
書道の「草書体」と言えばいいのか、天才的崩し、外しに言葉が出ません。それと、作品を通して各メンバーに必ずスポット・ライトが当たるよう気遣っている点が素晴らしい。巷では「ジャズ界で最も性格が悪い」と誹謗されているけど、本当かどうか、聴けば分りますよ。
それにしても、バロンとの相性は抜群ですね。また、リードのbソロが上手く録られて、聴きものです。
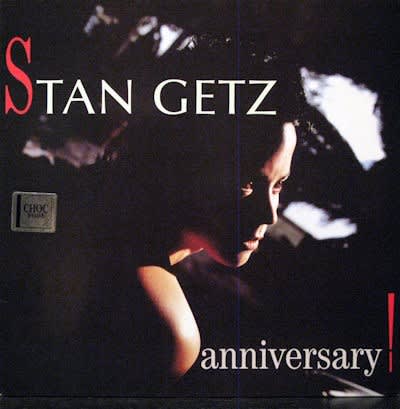
CONCORD JAZZレーベルの第一弾、‵THE DOLPHIN’、シスコの「キーストーン・コーナー」でのライブ(1981年5月)。
pがL・LEVYなので、後の作品と比べややコンサバ感が否めないけれど、逆にリラックスの中に一本背筋が通った上質のライブとなっている。カヴァのダサさは気にしない。
ここでの、注目点は、‵A Time For Love’、‵Close Enough For Love’、J・MANDELの2曲も取り上げている所。‵A Time For Love’、この繊細でラヴリーな世界、もうゲッツしか出せません。また、‵Close Enough For Love’ではゲッツの入り方が絶妙で、途中から、まるでシムスが吹いているのでは、と錯覚させるほどシムスのお得意フレーズを織り込み、ライブならではのゲッツ流ファン・サービスですね。聴衆に受けている(笑)
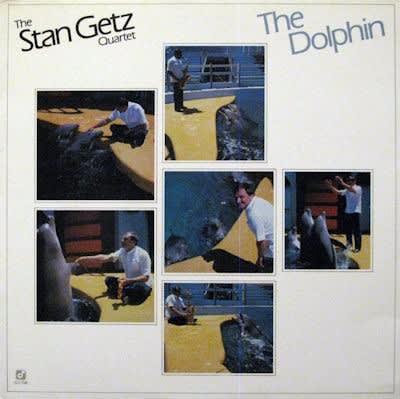
2作目は翌、1982年1月・シスコ、2月・NYでスタジオ録音された‵PURE GETZ’。
前作と打って変わりシビアなカヴァが本作に懸ける心の内を暗示している。恐らく、こちが本番と考えていたのでは。J・マクニーリー(p)、M・ジョンソン(b)という俊英を新たに加え、dsをV・ルイス、B・ハートが分けている。TOPにマクニーリーのオリジナル‵On The Up And Up’を取り上げるほどメンバーに対する気配りと同時に自信の大きさが窺われる。ゲッツが如何にピアニストを大事にしているか、よく解りますね。全7曲、硬軟、剛柔を織り交ぜ、隙らしい隙は全く見せなくゲッツ会心の出来。
マクニーリーのコンテンポラリーなpもイイ、そしてジョンソンの張りのあるbソロが信じ難いほど上手く録られている。B面の‵I Wish I Knew’~‵Come Rain Or・・・・・’、そして‵Tempus Fugit’でビシッと着地を決めるゲッツに揺るぎ無し。

1991年6月6日没、享年64。
ミュージシャンの「ピーク、全盛期はいつ?」なんて話は、あまり好きではありませんが、最後の10年間、キャリアの中で「極み」に達した稀有な、そして偉大なジャズ・マンでした。