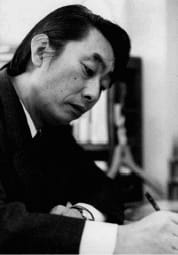私個人的な好みとして、大人数のオーケストラより少人数のオーケストラ編成の方が好きだ。古典派の音楽やバロック音楽さえ演奏出来れば何の不満も無い。だから所属している山形響の規模は満足している。
大は小を兼ねるというが、オーケストラでも社会の中で経済生活をしなくてはご飯を食べられないので、大きいオーケストラの場合、モーツァルトの演奏会をやって休みになってしまう余剰の団員さんを有給休暇扱いにして、なおかつオーケストラを小規模という理由から安く売っていては会社としてはやっていけないものである。だからなるべく大規模な編成のオーケストラを高い値段で買い取ってもらった方が良いという事になる。ただこの手の曲を振る事が出来る指揮者は、大抵ベテランでギャラも高い。経験が無い若い指揮者にはなかなかまわってこない演目という事になる。練習日数が多くなるのも、ネックになる。依頼演奏会というより定期演奏会の演目と言えるかもしれない。
山形響に対して、依頼演奏会の場合はマーラーやブルックナー、ショスタコーヴィチ、R.シュトラウスなど大規模編成の曲を演奏して欲しいという依頼はまずない。これらの作曲家の作品を演奏するには大量のエキストラを必要として、かえって大人数のオーケストラより高くついてしまうという事情もある。
定期演奏会などでもこれらの作曲家の作品を演奏する事は何年に一回である。(最近はブルックナーに関しては、少人数で演奏しているが)。
~~~~~~~~~~~~
私はR.シュトラウスという作曲家が大好きだ。山形響では入団してから約10年演奏していない。もちろんその大規模な編成のせいである。
フリー奏者の時は大人数が必要なため色々なオーケストラで年に何回も演奏していた。思い出すと小澤征爾&新日本フィルでアルペン交響曲を演奏する九州ツアーに参加した事もあった。毎日エキサイティングで楽しかった思い出である。最終日の打ち上げで小澤さんのおごりで全楽団員の飲み会があって、盛り上がり過ぎだとベテラン団員さんに怒られたような記憶が。笑。今は演奏する機会が無いので、少し寂しい。
R.シュトラウスの管弦楽曲の中に「ドン・キホーテ」という曲がある。チェロとビオラのソロがある大規模なオーケストラの曲だ。副題は「大管弦楽のための騎士的な性格の主題による幻想的変奏曲」とついていて、所謂変奏曲である。
今日あげたCDは、カラヤンとロストロポーヴィチという大物同士の共演で有名な一枚で、仏ADFディスク大賞、モントルー国際レコード賞受賞等々を受賞した名盤と言われている。
カラヤン&ベルリンフィルの全盛期の録音で、ドン・キホーテ役のロストロポーヴィチのチェロが雄弁に歌う。
演奏は大変素晴らしいものだが、それだけならフルニエ盤でもマイスキー盤でもシュタルケル盤でも同じように良い演奏なので、私の特別な思い入れはないだろう。
このCDをあげた最大の理由は、サンチョ・パンサ役でソロヴィオラを担当しているのが、私の音大時代の恩師ウルリヒ・コッホ先生なのだ。
先生の若い頃の演奏だが、先生特有の音色がたまらなく良い。
学生時代のレッスンで見本を示してくれた音色そのものだ。暗くなりがちなヴィオラの音色なのに先生の音色は明るい。彼の人柄が現れている音色なのだ。真似しようとしても誰も真似が出来ない特別な音色!!
先生が亡くなって10年以上経つが、いつでもCDを聴けばそこに先生が存在する感覚がよみがえる。
レッスン中にこのCDの事を会話した事があった。
「私にとってカラヤンと沢山の弟子達と共演出来た事は本当に良い思い出だよ。あっロストロとも共演したんだよね。本当に良いチェリストだ。チェロソロの方がヴィオラソロより目立つしね。ただあいつは禿げていて、俺には今だにたっぷり髪がある。俺の勝ちだね。笑。」と櫛を出して、髪の毛を整えるふりをした。
上の言葉はもちろんドイツ語の会話だったので保証はしないが、こんな感じだったような・・・・・。
学生時代の貴重な先生との思い出だ。

大は小を兼ねるというが、オーケストラでも社会の中で経済生活をしなくてはご飯を食べられないので、大きいオーケストラの場合、モーツァルトの演奏会をやって休みになってしまう余剰の団員さんを有給休暇扱いにして、なおかつオーケストラを小規模という理由から安く売っていては会社としてはやっていけないものである。だからなるべく大規模な編成のオーケストラを高い値段で買い取ってもらった方が良いという事になる。ただこの手の曲を振る事が出来る指揮者は、大抵ベテランでギャラも高い。経験が無い若い指揮者にはなかなかまわってこない演目という事になる。練習日数が多くなるのも、ネックになる。依頼演奏会というより定期演奏会の演目と言えるかもしれない。
山形響に対して、依頼演奏会の場合はマーラーやブルックナー、ショスタコーヴィチ、R.シュトラウスなど大規模編成の曲を演奏して欲しいという依頼はまずない。これらの作曲家の作品を演奏するには大量のエキストラを必要として、かえって大人数のオーケストラより高くついてしまうという事情もある。
定期演奏会などでもこれらの作曲家の作品を演奏する事は何年に一回である。(最近はブルックナーに関しては、少人数で演奏しているが)。
~~~~~~~~~~~~
私はR.シュトラウスという作曲家が大好きだ。山形響では入団してから約10年演奏していない。もちろんその大規模な編成のせいである。
フリー奏者の時は大人数が必要なため色々なオーケストラで年に何回も演奏していた。思い出すと小澤征爾&新日本フィルでアルペン交響曲を演奏する九州ツアーに参加した事もあった。毎日エキサイティングで楽しかった思い出である。最終日の打ち上げで小澤さんのおごりで全楽団員の飲み会があって、盛り上がり過ぎだとベテラン団員さんに怒られたような記憶が。笑。今は演奏する機会が無いので、少し寂しい。
R.シュトラウスの管弦楽曲の中に「ドン・キホーテ」という曲がある。チェロとビオラのソロがある大規模なオーケストラの曲だ。副題は「大管弦楽のための騎士的な性格の主題による幻想的変奏曲」とついていて、所謂変奏曲である。
今日あげたCDは、カラヤンとロストロポーヴィチという大物同士の共演で有名な一枚で、仏ADFディスク大賞、モントルー国際レコード賞受賞等々を受賞した名盤と言われている。
カラヤン&ベルリンフィルの全盛期の録音で、ドン・キホーテ役のロストロポーヴィチのチェロが雄弁に歌う。
演奏は大変素晴らしいものだが、それだけならフルニエ盤でもマイスキー盤でもシュタルケル盤でも同じように良い演奏なので、私の特別な思い入れはないだろう。
このCDをあげた最大の理由は、サンチョ・パンサ役でソロヴィオラを担当しているのが、私の音大時代の恩師ウルリヒ・コッホ先生なのだ。
先生の若い頃の演奏だが、先生特有の音色がたまらなく良い。
学生時代のレッスンで見本を示してくれた音色そのものだ。暗くなりがちなヴィオラの音色なのに先生の音色は明るい。彼の人柄が現れている音色なのだ。真似しようとしても誰も真似が出来ない特別な音色!!
先生が亡くなって10年以上経つが、いつでもCDを聴けばそこに先生が存在する感覚がよみがえる。
レッスン中にこのCDの事を会話した事があった。
「私にとってカラヤンと沢山の弟子達と共演出来た事は本当に良い思い出だよ。あっロストロとも共演したんだよね。本当に良いチェリストだ。チェロソロの方がヴィオラソロより目立つしね。ただあいつは禿げていて、俺には今だにたっぷり髪がある。俺の勝ちだね。笑。」と櫛を出して、髪の毛を整えるふりをした。
上の言葉はもちろんドイツ語の会話だったので保証はしないが、こんな感じだったような・・・・・。
学生時代の貴重な先生との思い出だ。