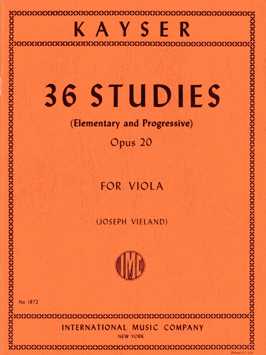風邪からの復活!!昨日は38度5分前後あった熱が今日はすっかり落ちました。
有言実行ですな!!体調は万全です。
さて、本日から山形弦楽四重奏団第36回定期演奏会にむけた練習が始まりました。今までは初回の練習では楽しく所謂「初見大会」的な面もありましたが、スケジュ~ルが立て込んでいて定期的に練習日をとれなくなってきているので、1回1回無駄なく積み上げていかなければならない、というのはメンバ~個々も自覚をしていたようで、少し安心しました。
この弦楽四重奏団では初の演目となるB.Bartokの弦楽四重奏に他メンバ~は恐れおののきすぎていて、ものすごく高い山として設定しすぎている感じがしました。私見ですが、前回の定期演奏会に演奏したL.v.BeethovenのOp.127の方が、比べようもない高い山だったので、今回は幾分余裕がある気がするのです。
もちろんB.Bartokも難しいですが、手が届かない曲ではないと思いますし・・・。10年続いた団体ならチャレンジ出来うる曲だと思っています。これからもう少し曲の中身が分かってくると個々のBartokが出来上がってくるので、その調整の方が大変そうです。
F.J.Haydnはもう全曲演奏企画も半ば過ぎの38曲目なので、手慣れた感じで練習が進んでいきます。W.A.Mozartの新曲は久しぶりなので、演奏していて楽しいです。スマ~トで格好いいイメージの作曲家なので、軽さがあるともう少し良いかもしれません。そこが課題ですかね。
初日の練習から録音し始めました。普段はもう少し練習がすすんでから録音して聴き始めますけど、本番近くなってから方針転換出来なくなる箇所も少なからず出てきてしまうので、今回は練習初期の時から録音して聴いて勉強します。
今回の演奏会は今まで一番良い演奏会になりそうな予感を持つことにします。
有言実行ですな!!体調は万全です。
さて、本日から山形弦楽四重奏団第36回定期演奏会にむけた練習が始まりました。今までは初回の練習では楽しく所謂「初見大会」的な面もありましたが、スケジュ~ルが立て込んでいて定期的に練習日をとれなくなってきているので、1回1回無駄なく積み上げていかなければならない、というのはメンバ~個々も自覚をしていたようで、少し安心しました。
この弦楽四重奏団では初の演目となるB.Bartokの弦楽四重奏に他メンバ~は恐れおののきすぎていて、ものすごく高い山として設定しすぎている感じがしました。私見ですが、前回の定期演奏会に演奏したL.v.BeethovenのOp.127の方が、比べようもない高い山だったので、今回は幾分余裕がある気がするのです。
もちろんB.Bartokも難しいですが、手が届かない曲ではないと思いますし・・・。10年続いた団体ならチャレンジ出来うる曲だと思っています。これからもう少し曲の中身が分かってくると個々のBartokが出来上がってくるので、その調整の方が大変そうです。
F.J.Haydnはもう全曲演奏企画も半ば過ぎの38曲目なので、手慣れた感じで練習が進んでいきます。W.A.Mozartの新曲は久しぶりなので、演奏していて楽しいです。スマ~トで格好いいイメージの作曲家なので、軽さがあるともう少し良いかもしれません。そこが課題ですかね。
初日の練習から録音し始めました。普段はもう少し練習がすすんでから録音して聴き始めますけど、本番近くなってから方針転換出来なくなる箇所も少なからず出てきてしまうので、今回は練習初期の時から録音して聴いて勉強します。
今回の演奏会は今まで一番良い演奏会になりそうな予感を持つことにします。