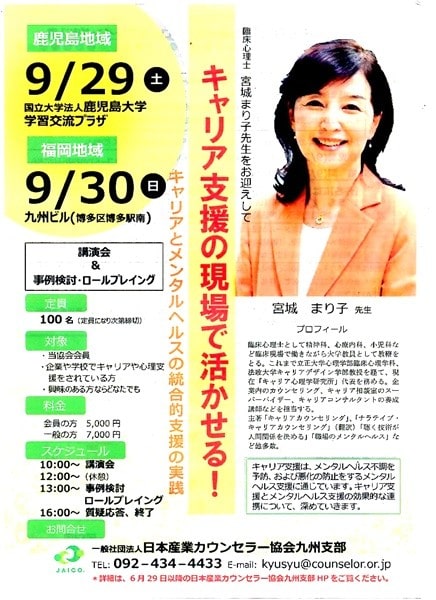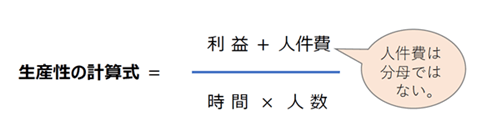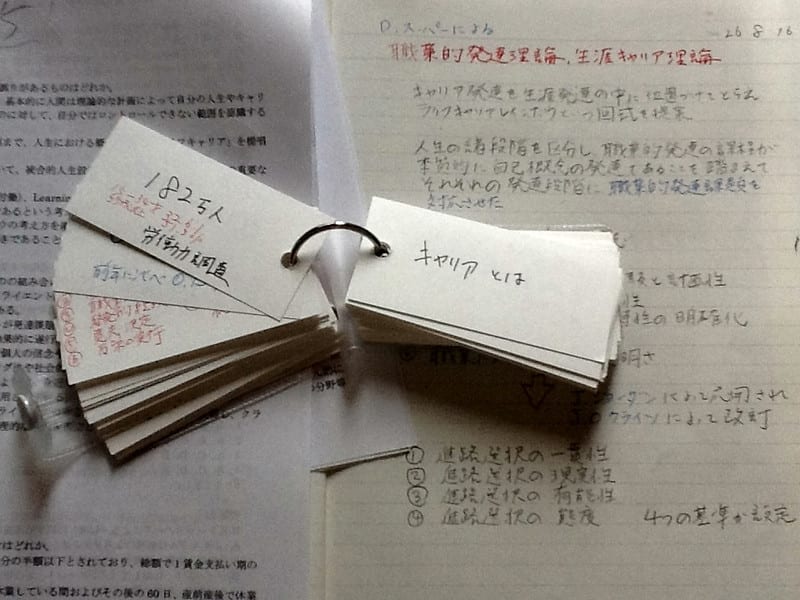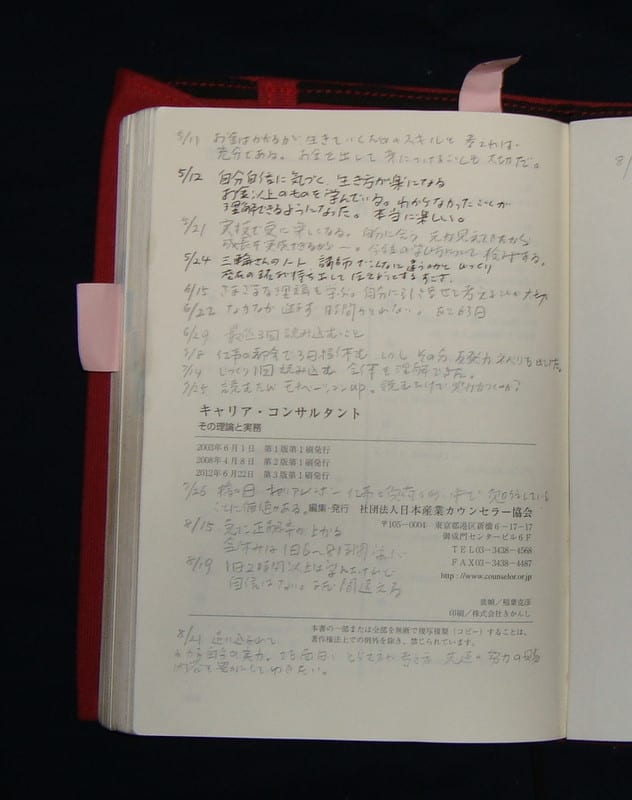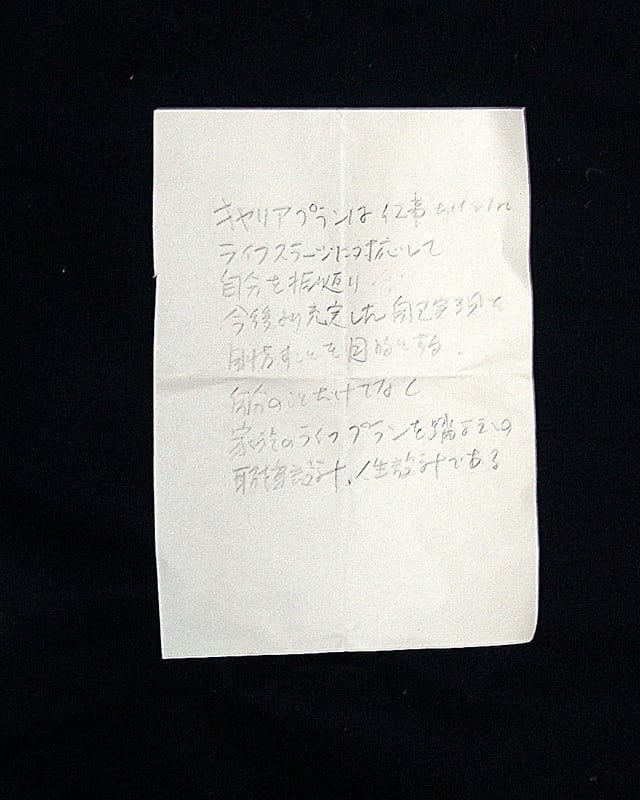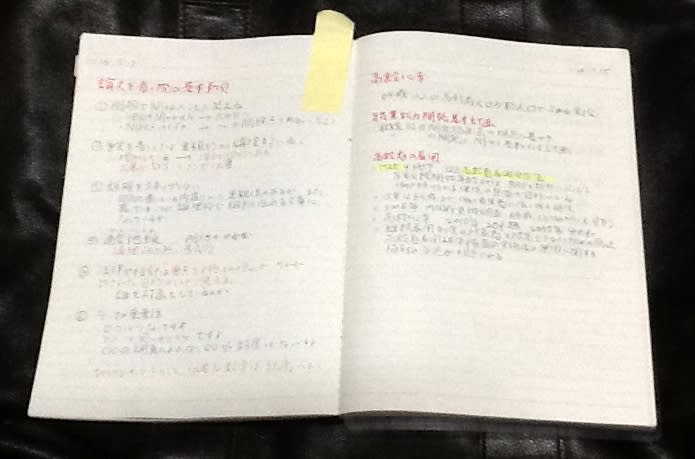キャリアコンサルタントとは、学生、求職者、在職者等を対象に職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門職である(ウィキペディアより)と記載されています。いろんな定義がありますが、自分の中でキャリアコンサルタントとしての理解を深めるために概念化してみようと考えました。その結果、キャリアコンサルタントのイメージは「お坊さん」に例えられると考えました。
理由は、3つあります。それは、じっくり相談者の声やこころに寄り添う。そして、その人の力で生きていけるよう背中を押すヒントを差し上げ、求められた時にはアドバイスをおこなう。座禅はしないけれど、自分と向き合う(生き方や考え方、まわりのこと)時間、そして質問によって、相談者自身を深めていくお手伝いをすることが、キャリア(人生)そのものを支援するキャリアコンサルタントとの類似点が多いからです。
お坊さんは他にも、いろんな仕事があるかと思います。各種法要。檀家さんのお世話は、支援先のフォローに例えられると思います。定期的な法要(節目)での催し。地域の方々(こども、わかもの、高齢者、弱者など)への支援として法話(セミナー)の実施など、私が幼い頃近くのお寺でいろんな話を聞かせてくれました。今思うと、お寺という歴史のある場所と独特の雰囲気だったからこそ、命の尊さも、そして人としてのあり方についても、こころに残っているように思います。
一方、人の死から見えてくることって、たくさんあると思います。そのひとつが命の大切さと感謝。現世に生きている人をよりその人らしく生きる、亡くなった方の生き方を通して、今生きる私たちに、それでいいのかと問いかけられるように感じます。
ちょっと固いかもしれませんが、こんなイメージです。さまざまなキャリアコンサルタントが活躍していますが、私はこういう存在でありたいと努力したいと考えています。