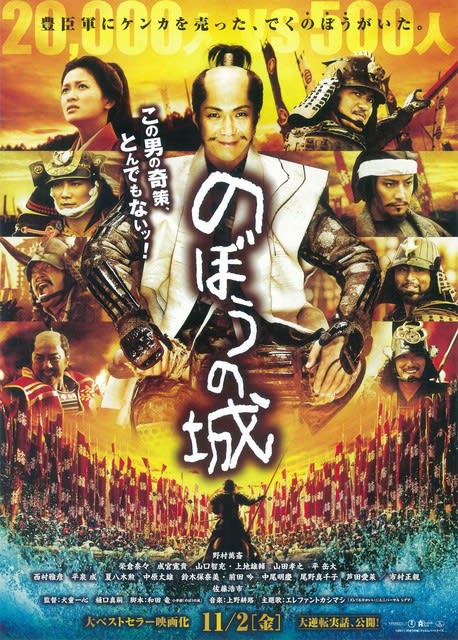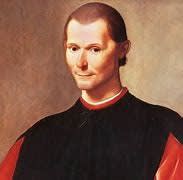今回は『組織』のお話です。

組織といってもね、べつにピラミッド型の組織ってだけではありません。
横のつながりが強いのもまた『連携』という『組織』ですし。

その中で、必ず起こる『引継ぎ』という問題です。

人間ね、いつまでも続けられるもんでもありませんし、次の世代への引継ぎってもんも考えなくてはなりません。
いつまでも自分はやりますよってのは、あくまでも個人商店などの個人事業主の世界。
家族経営であれ、経営やら考え、長期的な展望をしてみれば、引継ぎの大切さって理解できます。

でもね、案外とこれができてない『組織』って多いんですよ。
私が経験しただけでも『引き継ぐのに半年はかかる』と言ったり、1年近くも引継ぎ作業しているのに、ちゃんと引継ぎできてなくて、都度連絡していたり・・・。
通常、引継ぎなんて猶予期間は1週間程度。
もちろん、物理的にそんな短期間じゃ引継ぎなんてできません。
ではどうするのか?
江戸時代では、前もってマニュアルが作成されて、ある程度は誰が引き継いでも理解できるようにしておいたようです。
中央官庁などではそういうのもあるかもしれませんが、中小企業などではなかなかそこまでは準備できません。
もっとも、時間を割いて普段からマニュアルや引継ぎ時効をまとめることをしておけば、引継ぎはできると思います。
実際、以前の教育関連の仕事では前もって準備はしてましたし、その前の不動産の仕事でも準備はしてました。
これ、べつに特別なことはしてません。
担当している業務をとりまとめておいて、ちょっとしたマニュアル化しているだけですから。
でも、案外とこういうことってできてないケースが多いんです。
普段の忙しさにかまけてできないってのもあります。
あとは、そこまで求めてないんですよ。だから準備なんぞも後回しになるんです。
でも、異動やら退職でバタバタしたくなければ、できる範囲での準備はしておいたほうがいいです。
後で、根掘り葉掘り質問されて、最悪責任追及されたら面倒ですからね(笑)
そうならない為にも、『ここまで準備して引継ぎしたんだから、あとはできるよね?』と胸張って言えるようにしてください。
これがまさに『組織』なんですよ。
『誰でもできる』というならば、『素人でもすぐにできる』ってことを実証してこそ『組織』なんです。
そしてじつは『引継ぎ』ってのが現実はうまくできてないってのもまた実情なんです。
だからこそ、会社側は業務マニュアルもですけど、普段からの業務日誌などの日々の記録は記録しつつ引継ぎ用に残せるような資料を作るように習慣づけないと大変だなと思います。
これができれば、また一つの『働き方改革』になります。
当たり前にある『引継ぎ』、でも実態は『表面だけの引継ぎ』が多いのではないでしょうか?
情報共有などを推進していても、全てって無理だよと思われるかもしれませんが、それでも徹底させないと『組織』にならず、いつまでも『個人商店』状態なんです。
こういう引継ぎや説明をスマートにこなせれば、仕事のできる人ってことになるのでしょう。
私もそうありたいと精進してまいります。


大手上場企業や外資系企業など優良な求人多数|管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】

プレミアムな転職をサポート|管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】

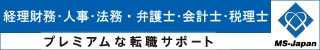


組織といってもね、べつにピラミッド型の組織ってだけではありません。
横のつながりが強いのもまた『連携』という『組織』ですし。

その中で、必ず起こる『引継ぎ』という問題です。

人間ね、いつまでも続けられるもんでもありませんし、次の世代への引継ぎってもんも考えなくてはなりません。
いつまでも自分はやりますよってのは、あくまでも個人商店などの個人事業主の世界。
家族経営であれ、経営やら考え、長期的な展望をしてみれば、引継ぎの大切さって理解できます。

でもね、案外とこれができてない『組織』って多いんですよ。
私が経験しただけでも『引き継ぐのに半年はかかる』と言ったり、1年近くも引継ぎ作業しているのに、ちゃんと引継ぎできてなくて、都度連絡していたり・・・。
通常、引継ぎなんて猶予期間は1週間程度。
もちろん、物理的にそんな短期間じゃ引継ぎなんてできません。
ではどうするのか?
江戸時代では、前もってマニュアルが作成されて、ある程度は誰が引き継いでも理解できるようにしておいたようです。
中央官庁などではそういうのもあるかもしれませんが、中小企業などではなかなかそこまでは準備できません。
もっとも、時間を割いて普段からマニュアルや引継ぎ時効をまとめることをしておけば、引継ぎはできると思います。
実際、以前の教育関連の仕事では前もって準備はしてましたし、その前の不動産の仕事でも準備はしてました。
これ、べつに特別なことはしてません。
担当している業務をとりまとめておいて、ちょっとしたマニュアル化しているだけですから。
でも、案外とこういうことってできてないケースが多いんです。
普段の忙しさにかまけてできないってのもあります。
あとは、そこまで求めてないんですよ。だから準備なんぞも後回しになるんです。
でも、異動やら退職でバタバタしたくなければ、できる範囲での準備はしておいたほうがいいです。
後で、根掘り葉掘り質問されて、最悪責任追及されたら面倒ですからね(笑)
そうならない為にも、『ここまで準備して引継ぎしたんだから、あとはできるよね?』と胸張って言えるようにしてください。
これがまさに『組織』なんですよ。
『誰でもできる』というならば、『素人でもすぐにできる』ってことを実証してこそ『組織』なんです。
そしてじつは『引継ぎ』ってのが現実はうまくできてないってのもまた実情なんです。
だからこそ、会社側は業務マニュアルもですけど、普段からの業務日誌などの日々の記録は記録しつつ引継ぎ用に残せるような資料を作るように習慣づけないと大変だなと思います。
これができれば、また一つの『働き方改革』になります。
当たり前にある『引継ぎ』、でも実態は『表面だけの引継ぎ』が多いのではないでしょうか?
情報共有などを推進していても、全てって無理だよと思われるかもしれませんが、それでも徹底させないと『組織』にならず、いつまでも『個人商店』状態なんです。
こういう引継ぎや説明をスマートにこなせれば、仕事のできる人ってことになるのでしょう。
私もそうありたいと精進してまいります。
大手上場企業や外資系企業など優良な求人多数|管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】
プレミアムな転職をサポート|管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】