先日、『三国志に見る『組織論』』とちょいマジメなことを書いてみましたが、今回は日本の戦国時代をテーマに考えてみました。
そのテーマの主役は北条氏。
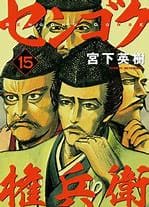

鎌倉幕府の執権、北条氏の末裔って名乗ってはいますが、始祖の北条早雲は備前の伊勢氏の出身だったそうです。
伊勢氏は室町幕府では高級官僚の家柄。
実務官僚かつキャリア組って感じの家柄だったのでしょう、組織運営などもおそらく京都の幕府で経験してきたのだと思います。
現場も経験しつつある種の理想と実験的な試みを持った人物が存在した場合にどのような行動をとるか?
これが『北条家』の行動になるのかもしれません。
北条早雲は生涯『伊勢』性であって『北条』を名乗ったのは息子の北条氏綱の代です。

おそらく、伊豆から関東の相模を手中にしつつも、更なる関東を支配下に置く際に、『伊勢』性では関西ではブランドでも関東ではブランドではなかったのでしょう。
で、関東でのブランドってなんだ?とマーケティングをしたのだと思います。
東国といえば『源氏』というブランドはあるとはいえ、いかんせん現政権を担っている『源氏』である足利政権がダメダメな状態。
そうなると人間ってその前を思い出すんですよ。
室町幕府の前だと建武の政権ですけど、これは被害者多数の政権なのですっ飛ばします(笑)
で、鎌倉幕府、それも『執権政治』という合議制を営んだ北条氏を思い出すわけです。
あの頃は平和で穏やかではなかったのか?と。
もっとも、実際は政変なども頻発していたので安定はしてませんが、それでも戦国時代に較べればまだ安定はしていたという時代。
ここで伊勢氏綱さんは決断するわけです。

よし!!今日から北条を名乗ります!!と。
伊勢氏は元々が室町幕府の中枢、現代でいえば官房長官クラスを排出するくらいの実務官僚の家柄です。
そのブランドを捨てて、あえてかつて関東にあったブランド『北条』を名乗ろうってんですから一大決心なわけです。
でも、そこには冷徹なマーケティングの答えで決めた決断だったんだと思います。
じつに合理的だと思うのは、自らのマーケットはどこなのか?
そしてそのマーケットが望むものはなんなのか?
当時の関東で求められるブランドは『足利』でも『上杉』でも、まして『伊勢』でもない。
そう『北条』だろうと、氏綱さんは気づいて実行に移したわけです。
で、こちらの『北条』の皆さんはおそらく理想があったんだと思います。
それは「どうやったら理想的な国造りができるのか?そしてそれには効率的な組織が構築できるのか?」ということ。
これ、北条早雲から北条氏直まで追求するのです。
代替わりには検地を実施しながらも減税をし、情報など雑務などは記録化して合議制にする。

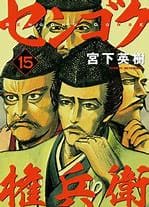
虎の印判などもこの頃。

それまでの花押ではなく印判で決裁をするという合理的な組織運営です。
小田原評定が長引いて何も決まらないというのは、べつに当時の北条氏が怠慢だったわけでもないと思います。
組織運営が充実して合議制が行き届いている状態ならあり得る話なんです。
要は非常時を常時の行政でやりくりしようとしたら決断が遅くなったというお話なわけです。
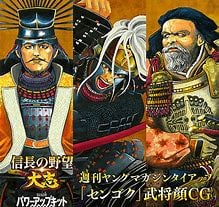
これって、幕末の幕府もそうでしょ。
もっといえば終戦時の政府も似ていると思いますよ。
組織力でいえば滅びるわけではないくらいに充実していた組織なんですから。
ではその後継はといえば
北条家が滅亡後に関東に入った徳川家はその前の今川家や武田家を含めて北条家の旧家臣団を多く雇用しました。
これが関東経営だけでなく江戸幕府の組織づくりに役立ったのだと思います。
江戸幕府の組織や官僚制はその前の幕府とは比べものにならないくらいに盤石ですから。
で、幕末から明治。
旧幕府から明治政府で実務を担った官僚はやはり旧幕府の官僚でした。
大久保利通など個人的な有能な人材はいるものの、それだけでは大規模な組織は運営できないものなのです。
ここで力を発揮したのが旧幕府関連の役人でした。
でも、そもそもかつて関東を支配した北条家の子孫達が江戸幕府を経て再び関東を護ろうとしてくれたのかと思わざるを得ません。
江戸幕府での合理的かつ大規模な組織運営方法はおそらく豊臣よりも北条での経験があったからだと個人的には思うからです。
そう考えると、かつて関東で実質的な『下剋上』をうまく国家運営までにして、明治政府まで実務の面で影響及ぼしたと考えれば、北条早雲の考えた夢なり理想って、たいしたもんだと思うのであります。


高速・多機能・高セキュリティ
美しいホームページを作るなら Z.com



そのテーマの主役は北条氏。
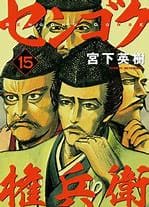

鎌倉幕府の執権、北条氏の末裔って名乗ってはいますが、始祖の北条早雲は備前の伊勢氏の出身だったそうです。
伊勢氏は室町幕府では高級官僚の家柄。
実務官僚かつキャリア組って感じの家柄だったのでしょう、組織運営などもおそらく京都の幕府で経験してきたのだと思います。
現場も経験しつつある種の理想と実験的な試みを持った人物が存在した場合にどのような行動をとるか?
これが『北条家』の行動になるのかもしれません。
北条早雲は生涯『伊勢』性であって『北条』を名乗ったのは息子の北条氏綱の代です。

おそらく、伊豆から関東の相模を手中にしつつも、更なる関東を支配下に置く際に、『伊勢』性では関西ではブランドでも関東ではブランドではなかったのでしょう。
で、関東でのブランドってなんだ?とマーケティングをしたのだと思います。
東国といえば『源氏』というブランドはあるとはいえ、いかんせん現政権を担っている『源氏』である足利政権がダメダメな状態。
そうなると人間ってその前を思い出すんですよ。
室町幕府の前だと建武の政権ですけど、これは被害者多数の政権なのですっ飛ばします(笑)
で、鎌倉幕府、それも『執権政治』という合議制を営んだ北条氏を思い出すわけです。
あの頃は平和で穏やかではなかったのか?と。
もっとも、実際は政変なども頻発していたので安定はしてませんが、それでも戦国時代に較べればまだ安定はしていたという時代。
ここで伊勢氏綱さんは決断するわけです。

よし!!今日から北条を名乗ります!!と。
伊勢氏は元々が室町幕府の中枢、現代でいえば官房長官クラスを排出するくらいの実務官僚の家柄です。
そのブランドを捨てて、あえてかつて関東にあったブランド『北条』を名乗ろうってんですから一大決心なわけです。
でも、そこには冷徹なマーケティングの答えで決めた決断だったんだと思います。
じつに合理的だと思うのは、自らのマーケットはどこなのか?
そしてそのマーケットが望むものはなんなのか?
当時の関東で求められるブランドは『足利』でも『上杉』でも、まして『伊勢』でもない。
そう『北条』だろうと、氏綱さんは気づいて実行に移したわけです。
で、こちらの『北条』の皆さんはおそらく理想があったんだと思います。
それは「どうやったら理想的な国造りができるのか?そしてそれには効率的な組織が構築できるのか?」ということ。
これ、北条早雲から北条氏直まで追求するのです。
代替わりには検地を実施しながらも減税をし、情報など雑務などは記録化して合議制にする。

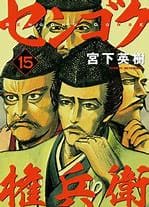
虎の印判などもこの頃。

それまでの花押ではなく印判で決裁をするという合理的な組織運営です。
小田原評定が長引いて何も決まらないというのは、べつに当時の北条氏が怠慢だったわけでもないと思います。
組織運営が充実して合議制が行き届いている状態ならあり得る話なんです。
要は非常時を常時の行政でやりくりしようとしたら決断が遅くなったというお話なわけです。
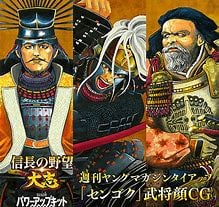
これって、幕末の幕府もそうでしょ。
もっといえば終戦時の政府も似ていると思いますよ。
組織力でいえば滅びるわけではないくらいに充実していた組織なんですから。
ではその後継はといえば
北条家が滅亡後に関東に入った徳川家はその前の今川家や武田家を含めて北条家の旧家臣団を多く雇用しました。
これが関東経営だけでなく江戸幕府の組織づくりに役立ったのだと思います。
江戸幕府の組織や官僚制はその前の幕府とは比べものにならないくらいに盤石ですから。
で、幕末から明治。
旧幕府から明治政府で実務を担った官僚はやはり旧幕府の官僚でした。
大久保利通など個人的な有能な人材はいるものの、それだけでは大規模な組織は運営できないものなのです。
ここで力を発揮したのが旧幕府関連の役人でした。
でも、そもそもかつて関東を支配した北条家の子孫達が江戸幕府を経て再び関東を護ろうとしてくれたのかと思わざるを得ません。
江戸幕府での合理的かつ大規模な組織運営方法はおそらく豊臣よりも北条での経験があったからだと個人的には思うからです。
そう考えると、かつて関東で実質的な『下剋上』をうまく国家運営までにして、明治政府まで実務の面で影響及ぼしたと考えれば、北条早雲の考えた夢なり理想って、たいしたもんだと思うのであります。
高速・多機能・高セキュリティ
美しいホームページを作るなら Z.com




















