「an und für sich」をどう訳すべきか
Die Wahrheit des Seyns ist das Wesen.
Das Seyn ist das Unmittelbare. Indem das Wissen das Wahre erkennen will, was das Seyn an und für sich ist, so bleibt es nicht beim Unmittelbaren und dessen Bestimmungen stehen, sondern dringt durch dasselbe hindurch, mit der Voraussetzung, daß hinter diesem Seyn noch etwas Anderes ist, als das Seyn selbst, daß dieser Hintergrund die Wahrheit des Seyns ausmacht. Diese Erkenntniß ist ein vermitteltes Wissen, denn sie befindet sich nicht unmittelbar beim und im Wesen, sondern beginnt von einem Andern, dem Seyn, und hat einen vorläufigen Weg, den Weg des Hinausgehens über das Seyn oder vielmehr des Hineingehens in dasselbe zu machen.Erst indem das Wissen sich aus dem unmittelbaren Seyn erinnert, durch diese Vermittlung findet es das Wesen.—Die Sprache hat im Zeitwort: Seyn, das Wesen in der vergangenen Zeit: gewesen, behalten; denn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vergangene Seyn.
(Wissenschaft der Logik, Erster Teil Zweites Buch. Das Wesen.Die Wahrheit des Seyns ist das Wesen.)
存在の真理は本質である。
存在は直接的なものである。知識とはその存在に本来的にあるところの真なるものを認識しようとするものであるから、知識は直接的なものとそれらの諸規定に留まってはいない。むしろ、存在の向こうには、なおその存在とは異なった何か他のものが、存在そのものとしてあるという、また、その背後には存在の真理が成立しているという前提をもって、知識は存在を掘り抜いてゆく。
この認識は媒介された知識である。なぜならこの認識は直接に本質のもとにあるものでなければ、また本質のなかに見出されるものではなくて、本質とは他者としての存在から出発して、あらかじめ一つの道を通って、つまり、その存在を超えて出てゆくか、あるいは、その存在へと入り込んでゆく道程をたどらなければならないからである。はじめに、知識は直接的な存在から自身を思い起こして、この道筋を通って本質を見出す。その言い回しは時制の動詞の中にある。過ぎ去った時間の中にある本質は、あったもの( gewesen)として保存されている。というのも、本質とは過去の、しかし時間を超越した過去としての存在であるから。
>> <<
先日ツイッターで大論理学の一節を訳したときに、気になった言葉があった。それはヘーゲル哲学では特に重要な概念である「an und für sich」をどのように訳すべきか、という問題に引っかかったからだった。
それでこれまで「an und für sich」がどのように訳されてきたか、少し調べてみると、ふつうは「即自かつ対(向)自的に」などと訳されている場合が多い。その他には「主観的かつ客観的に」とか「潜在的かつ顕在的に」などと訳されているようである。
「an und für sich」の原意を正確に理解するためには、ヘーゲルの概念観の核心を正しく理解している必要がある。ヘーゲルはすべての事物はその存在の根拠に概念を持っているとみる。そして、ある事物が事物であるのはすべてその概念によるのであって、概念がまだ事物に潜在的である段階は「an sich」として、そして概念がその姿を顕在化させてゆく自己反照の段階が「für sich」として捉えられる。
表象をたどって「思考」することは哲学することではないけれども、たとえて言えば「どんぐり」は樫の木の「概念」がまだ潜在的な時の姿であり、その「概念」が発展して顕在化すると、樹木としての「樫の木」が姿を現す。「どんぐり」のその成長は内発的であって他の力を必要とせず、必然的であることから、「an und für sich」は文脈においては「必然的に」とか「独立して」とか「絶対的に」と訳される場合もある。
「an und für sich」の原語の事柄をさらにもっと的確に捉えて言い現すことのできる日本語がないかと考えていて、「本来的に」とか「元来的に」という言葉に思い及んだ。それでツイッターの訳文では「an und für sich」を「本来的に」と訳した。「本」とは「もともと」の意味であり「元々に」はじめに潜在的に存在するものから「出て来た」概念は「出来あがって」その完全な姿を実現する。すべて生命のあるものは、もっとも概念的な存在である。
本来の日本語で言い現してこそ、借り物ではない独自の哲学が生まれて来る。










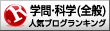

 review @myenzyklo
review @myenzyklo







