令和6年3月26日に、「同性パートナーは「犯罪被害給付金の支給を受けられる遺族」に該当するか。」をめぐって、最高裁において下記のような判決が下されました。
この最高裁の判決は、下級審である名古屋高等裁判所において、原告が「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請したところ、愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けたことに対して最高裁に上告していたものに対して下されたものです。
この最高裁の判決の多数意見に対する私の意見は、結論から言えば、当判決の中で反対意見を述べられている裁判官の今崎 幸彦氏の意見に同意するもので、さらに付け加えれば、以下の理由からも、私はこの最高裁結審における多数意見に反対するものです。
最高裁の審理差し戻し判決の主たる理由は「「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする」とするものです。要するに、「同性パートナー」関係が、事実上「婚姻関係と同様の事情にあった者に該当しない」と判断した名古屋高裁の判決に対して、問題があるからさらに審理を尽くせと差し戻したものです。
それでは最高裁は名古屋高裁の判決の何を問題としたのでしょうか。最高裁のこの多数意見は「「犯給法」が犯罪被害等 を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が、その改正によって、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られたことから、被害者給付金の対象を広く解釈すべきだ」と判断し、同性パートナーに対しても、被害者給付金の対象とすべきだとするものです。
しかし、この最高裁の判決による審理差し戻しによっては、「同性パートナー」を現行憲法の「婚姻関係」とみなすという、事実上の違憲判断を行なうことになります。「犯給法」という下位法の法改正目的などを理由として、憲法および民法の上位法の改正手続きも無視したまま、現行法の通説に反する誤った違憲判断を事実上行なわせることになるからです。
問題は最高裁判所の判事たちの「多数意見」が、事実上「違憲判断」であるとみられるとき、あるいは最高裁判所の判決が、国民多数の意見、意識、または常識などに反する場合にはどうすべきか、ということです。「違憲立法審査権」の申し立てや、最高裁判所裁判官に対する国民審査という制度もありますが、なかなか実効的な制度ではないようです。そうした事後的な制度ではなく、最高裁判所裁判官の選出にももっと事前に国民が参画できるような制度改革はできないものでしょうか。
以下引用
>> <<
言渡 令和6年3月26日
裁判所書記官
令和4年(行ツ)第318号
令和4年(行ヒ)第360号
判決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の名古屋高等裁判所令和2年(行コ)第23号犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件について、 同裁判所が令和4年8月26日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人〇〇〇〇ほかの上告受理申立て理由について
1 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「犯給法」という。)は、3条において、国は、犯罪被害者(2条3項所定の犯罪被害者をいう。以下同じ。)又はその遺族(所定の者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する旨を規定し、4条1号において、そのうち遺族給付金は、犯罪行為(2条1項所定の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為をいう。以下同じ。)により死亡した者の第一順位遺族に対し、一時金として支給する旨を規定している。
犯給法5条1項は、遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲について、犯罪被害者の死亡の時において、「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」(同項1号)、「犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(同項2号)、「前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(同項3号)のいずれかに該当する者とする旨を規定し、同条3項は、遺族給付金の支給を受けるべき遺族の順位について、上記各号の順序とする旨を規定している。
(2)上告人 (昭和50年生まれの男性)は、平成6年頃に昭和37年生まれの男性(以下「本件被害者」という。)と交際を開始し、その頃から同人と同居して生活していたところ、同人は、平成26年12月22日、第三者の犯罪行為により死亡した。
(3)上告人は、平成28年12月12日、本件被害者の死亡について、上告人は犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請したところ、愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付けで、上告人は上記の者に該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定を受けた。
2 本件は、上告人が、被上告人を相手に、上記裁定の取消しを求める事案である。
3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断した上で、犯給法5条1項1号が憲法14条1項等に反するとはいえないとして、上告人の請求を棄却すべきものとした。
犯給法5条1項1号は、一次的には死亡した犯罪被害者と民法上の婚姻関係にあった配偶者を遺族給付金の受給権者としつつ、死亡した犯罪被害者との間において民法上の婚姻関係と同視し得る関係を有しながら婚姻の届出がない者も受給権者とするものであると解される。そうすると、同号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」は、婚姻の届出ができる関係であることが前提となっていると解するのが自然であって、 上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得るものと解することはできない。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)犯給法は、昭和55年に制定されたものであるところ、平成13年法律第30号による改正により目的規定が置かれ、犯罪被害者等給付金を支給すること等により、犯罪被害等(犯罪行為による死亡等及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。以下同じ。)の早期の軽減に資することを目的とするものとされた(平成20年法律第15号による改正前の犯給法1条)。その後、平成16年に、犯罪等により害を被った者及びその遺族等の権利利益の保護を図ることを目的とする犯罪被害者等基本法が制定され(同法1条)、基本的施策の一つとして、国等は、これらの者が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとされた (同法13条)。そして、平成20年法律第15号による改正により、犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものとされた (1条)。また、平成13年法律第30号及び平成20年法律第15号による犯給法の各改正により、 一定の場合に遺族給付金の額が加算されることとなるなど、犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充が図られた。
以上のとおり、犯罪被害者等給付金の支給制度は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等 を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、同制度を充実させることが犯罪被害者等基本法による基本的施策の一つとされていること等にも照らせば、犯給法5条1項1号の解釈に当たっては、同制度の上記目的を十分に踏まえる必要があるものというべきである。
(2)犯給法5条1項は、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が上記(1)のとおりであることに鑑み、遺族給付金の支給を受けることができる遺族として、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられる者を掲げたものと解される。
そして、同項1号が、括弧書きにおいて、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を掲げているのも、婚姻の届出をしていないため民法上の配偶者に該当しない者であっても、犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み、事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからであると解される。しかるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。
そうすると、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当しないものとすることは、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて遺族給付金の支給を受けることができる遺族を規定した犯給法5条1項1号括弧書きの趣旨に照らして相当でないというべきであり、また、上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得ると解したとしても、その文理に反するものとはいえない。
(3)以上によれば、犯罪被害者と同性の者は、犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると解するのが相当である。
5 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 論旨は理由があり、上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官今崎幸彦の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官林道晴の補足意見がある。
裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。
私は、多数意見に賛同するものであるが、さらに以下の点を敷衍しておきたい。
犯給法5条1項1号括弧書きが遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲を規定するものであることからすれば、同号括弧書きにいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」の解釈は、その文理に加え、遺族給付金等の犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて行うことが相当である。多数意見が説示するとおり、同制度の目的は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することにあるのであり、犯罪被害者等基本法における同制度の位置付けや同制度が上記目的を達成するために拡充されてきた経緯等に照らしても、同制度の目的は重要というべきであって、これを十分に踏まえた解釈をすべきである。
そして、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的に照らせば、犯罪被害者と同性の者であっても、犯罪被害者との関係、犯罪被害者と互いに協力して共同生活を営んでいたという実態やその継続性等に鑑み、犯罪被害者との間で異性間の内縁関係に準ずる関係にあったといえる場合には、異性間の内縁関係にあった者と同様に犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けるものと考えられるから、上記文言に該当するものとして、遺族給付金の支給を受けることができる遺族に含まれると解するのが相当である。なお、反対意見が指摘するように、犯罪被害者等給付金は損害を填補する性格を有するものであるものの、それにとどまるものではなく、同制度が早期に軽減を図ろうとしている精神的、経済的打撃は、加害者に対して不法行為に基づいて賠償請求をすることができる損害と厳密に一致することまでは要しないものと解されるが、上記の場合には、少なくとも加害者に対する不法行為に基づく慰謝料請求はすることができるものと解してよいように思われる。
多数意見は、その説示から明らかなとおり、飽くまでも犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等への支援という特有の目的で支給される遺族給付金の受給権者に係る解釈を示したものである。上記文言と同一又は類似の文言が用いられている法令の規定は相当数存在するが、多数意見はそれらについて判断したものではない。それらの解釈は、当該規定に係る制度全体の趣旨目的や仕組み等を踏まえた上で、当該規定の趣旨に照らして行うべきものであり、規定ごとに検討する必要があるものである。
裁判官今崎幸彦の反対意見は、次のとおりである。
私は、多数意見と異なり、本件上告は棄却すべきであると考える。その理由は以下のとおりである。
1 犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため犯罪被害者等給付金を支給することとし(1条)、重傷病給付金、障害給付金と並べて遺族給付金を規定している(4条)。
遺族給付金の支給額は、政令により算定される基礎額に、「遺族の生計維持の状況を勘案して」政令で定める倍数を乗じて得た額とされている(9条1項)。このことは、遺族給付金が犯罪被害者遺族の生活保障を意識して設計されたものであることを示している。 他方、支給される遺族の範囲として、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたことを要件としていないこと(5条1項) など、必ずしも遺族の生活保障の性格とは整合しない規定も置かれている。
また、労働者災害補償保険法による給付等や損害賠償を受けたときはその価額の限度において支給しないとする一方(7条、8条)、犯罪被害者が死亡前に負担した療養費用等について支給額を加算する規定を置いている(9条5項) ところなどは、遺族給付金が損害の填補としての性格を有していることを示すものといえる。もっとも、前述のとおり支給額はあくまでも法及び政令に従って機械的に算出された額であり、実損害に一致させることとはしていない。
2 犯罪被害給付制度については、福祉政策、不法行為制度の補完、刑事政策の要素も含みながら、犯罪被害者の現状を放置しておくことによって生じる国民の法制度全体への不信感を除去することを本質とするなどと説明されている。
ややわかりにくい説明との印象をぬぐえないのは、犯罪被害給付制度が各種政策の複合的な側面を持つすぐれて政策的色彩の強い制度であり、それゆえに国の一般 会計に財源を求める給付金も特殊な意味付けがされていることによるものであろう。このように、厳密な意味での遺族給付金の性質となると一口ではいい表し難いものがあるが、上述した一連の規定をみる限り、必ずしも徹底してはいない部分はあるものの、犯給法は、遺族給付金が犯罪被害者遺族に対する生活保障と損害の填補という2つの機能を十全に果たすことを通じ、上述したような制度の趣旨、ひいては法の目的が達せられることを期待しているものといってよいと思われる。
3 以上を前提に、まずは生活保障という観点からみた場合について述べる。前述したとおり、犯給法は遺族給付金の支給対象となる遺族について、被害者によって生計を維持することを要件としていないが(5条1項)、「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」(以下「子ら」という。)については、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた者をそうでない者よりも先順位としている(2号)。
そのため、仮に1号にいう「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」に同性パートナー(「パートナー」の定義自体が一つの問題であるが、ここでは取りあえず「婚姻関係にある男女間と同様の事情にある共同生活者」という意味で用いる。) が含まれるとすると、それまで犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子らは同性パートナーに劣後し、支給対象から外れることとなる。なるほど多数意見は遺族給付金の支給対象となる遺族の範囲を広く解するものであり、その意味では犯罪被害者にとり歓迎されるべきものであろう。しかし、その一方で、犯罪被害者相互の間に、潜在的にせよ前述のような利害対立の契機をもたらすものでもある。こうした結果が遺族を含めた総体としての犯罪被害者の社会的ニーズに応えるものであるかは、犯給法の解釈上重要な考慮要素と思われる。事が犯罪被害者の収入に依存していた子らの生活保障にかかわることであってみればなおさらである。そうであれば、まずはこうした犯罪被害給付制度の視点に立った論証が求められるはずである。
4 遺族給付金には損害填補の性格があることについても前述した。犯給法上同性パートナーに遺族給付金が支給されるという解釈を採るのであれば、犯罪被害者の同性パートナーが加害者に対し損害賠償請求権を有することが前提となるはずである。
私は、同性パートナー固有の権利として、精神的損害を理由とした賠償請求権については、もとより事案によることではあるが、認める余地があると考えている。しかし、財産的損害、とりわけ扶養利益喪失を理由とする損害賠償請求権については、民法752条の準用を認めない限りにわかに考え難いというのが大方の理解であろう。そうであるとすれば、犯罪被害者の同性パートナーに認められる損害賠償請求権は、仮に認められるとしても異性パートナーに比べて限定されたものとなる。それにもかかわらず、多数意見の見解によれば、同性パートナーは異性パートナーと同視され、同額の遺族給付金を支給されることになる。遺族給付金が損害填補の性格を有することを考えると、前提となる民事実体法上の権利との間でこのようなギャップが生じることは説明が困難と思われる。
5 社会への影響という観点からは、多数意見による犯給法の解釈は、他法令の解釈運用への波及の有無という観点から更に難しい問題をはらむ。
犯給法5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は同趣旨の文言が置かれている例は少なくないが、そうした規定について、多数意見がいかなる解釈を想定しているかも明らかでない。個別法の解釈であり、犯給法と異なる解釈を採ることも可能と考えられるとはいえ、犯給法の解釈が他法令に波及することは当然想定され、その帰趨次第では社会に大きな影響を及ぼす可能性がある。現時点で、広がりの大きさは予測の限りではなく、その意味からも多数意見には懸念を抱かざるを得ない。
6 結論として、犯罪被害者と同性の者は犯給法5条1項1号括弧書き所定の者に該当し得るとする多数意見の解釈には無理があるといわざるを得ない。多数意見は、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受け、その軽減を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が異性であると否とで異なるものではないとしている。私は、これに異を唱えるつもりはないが、そのことと、犯給法の規定がそうした理念を矛盾なく取り込める造りになっているかは別問題である。
7 なお、多数意見は、上告人が本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて審理を尽くさせるために原審に差し戻すとする一方で、「事実上婚姻関係と同様の事情」という要件の中身については何も語らない。しかし、単なる同性同士の共同生活と何が異なるのかと考えてみたとき、それは決して自明ではないように思われる。婚姻は男女間のものとして歴史的にも法的にも観念されてきたのであり、同性同士の関係にも同様の法的保護を及ぼすという考えは最近のものである。同性同士の関係において何をもって 「事実上婚姻関係と同様の事情」と認めるかは、私はそれほど簡単に答えの出せる問題ではないと考えている。
この懸念が当たっているか否かはさて措くとしても、同性同士の関係における「事実上婚姻関係と同様の事情」は、多数意見によって新たに提示された概念であって、その中身を明らかにすることは、犯給法の条文の法令解釈にほかならないことを踏まえると、原審に差し戻すに当たっては、多数意見の考える解釈に従い、「事実上婚姻関係と同様の事情」の考慮要素を具体的に明らかにすべきであったと考える。
8 今回争点となった犯給法の解釈は、同性パートナーシップに対する法的保護の在り方という大きな論点の一部でもある。この論点は、社会におけるその位置付けや家族をめぐる国民一人一人の価値観にもかかわり、憲法解釈も含め幅広く議論されるべき重要な問題である。犯給法をめぐる検討も、そうした議論の十分な蓄積を前提に進められることが望ましかったことはいうまでもない。しかし、私の知る限り、そのような議論の蓄積があるとはいい難く、そのため、同性パートナーシップを現行法体系の中にどのように位置付けるか、他の権利や法的利益と衝突した場合にいかなる調整原理を用いるのかといった解釈上重要な視点はいまだ明らかとはいえない。そうした中で、個別法の解釈として同性パートナーへの法的保護の在り方を探る試みには相応の困難が避けられない。今後の立法や判例学説の展開により、近い将来新たな解釈や理解が広く共有され、多数意見の合理性を裏付けていくということはあり得ると思うが、現時点においては、先を急ぎすぎているとの印象を否めない。
以上の理由から、私は、同性パートナーは犯給法5条1項1号の「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」に該当しないと解するべきであると考える。そして、これまで述べたところによれば、このように解される同号が憲法14条に反するということもできない。したがって、以上と同旨の原判断は是認することができるから、本件上告は棄却すべきである。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀 克也
裁判官 長嶺 安政
裁判官 渡邉 惠理子
裁判官 今崎 幸彦
>> <<
参考
名古屋高等裁判所「犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求控訴事件」
裁判年月日 令和4年8月26日
裁判所名・部 名古屋高等裁判所 民事第4部
結果 棄却
判決全文 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/091434_hanrei.pdf










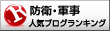

 shuzo ati @soratine
shuzo ati @soratine ドイツ語メール例文集&格言集 @dt_reibunshu
ドイツ語メール例文集&格言集 @dt_reibunshu






