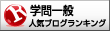歴史のパースペクティブ ―――20世紀のインディアン―――歴史の見方
部分的な真実と全体的な真実
歴史を見る場合でも同じことがいえると思う。真相を把握するためには、単に物事を部分的に見るばかりではなく、全体的に見なければならない。事物について思考し判断する場合と同様に、歴史についても部分を精察するとともに、全体を俯瞰し眺望する必要がある。
先に行われた第二次世界大戦の一環として日米の間で戦われた太平洋戦争についても同じことが言える。二〇世紀も中盤になって太平洋を挟んで日本とアメリカが対峙しあった太平洋戦争も、それを大きな歴史的なパースペクティブで捉えることは欠かせない。
アメリカ大陸の東海岸に―――彼らがその地を後にニューイングランドと名付けたように――上陸したピューリタンたちを端緒として、イギリスからの本格的な入植が始まった。やがて、それも産業革命にともないイギリス本国の産業の発展によって、当時のイギリスの植民地としてアメリカ大陸への入植はいっそう活発になった。入植者たちは新しい新天地と富を求めて、西へ西へと向かう西部開拓を押し進めてゆく。やがてカリフォルニアに金鉱が発見され、いわゆるゴールドラッシュによって、アメリカの西部開拓はさらに加速される。
しかしすべてに終末があるように、いわゆるWASPの後裔たちが、西へ西へと活路を求めていった西部開拓も、彼らがやがて北アメリカ大陸の西岸、カリフォルニアにたどり着いたとき、もはや大陸本土での新天地はなくなった。しかし、工業力の発展に伴って彼らが豊かに生み出すようになった商品や植民地での産物の販路を求めるためには、必然的に太平洋の大海原に乗り出さざるを得ない。北アメリカ大陸からは太平洋の大海原の向こうにあるユーラシア大陸の極東岸にも、遅かれ早かれ彼らもたどり着く。そこに日本は地理的に位置していた。
こうしたいわば歴史的な必然のもとに、ペリー提督が神奈川県沖の浦賀に到達したのである。このとき日本は、まだ江戸幕府300年の太平の眠りについていた。北アメリカ大陸においては、西部開拓の途上で、彼らに敵対していた先住民であるいわゆるインディアンたちは、すでにその牙もすっかり抜かれて、ほとんどの部族は消滅させられていた。彼らは土地を奪われ、狭い居留地に押し込められてゆき、多くのインディアンたちは、西洋人の持つ近代的な武器の前に殺されていった。
アメリカ合衆国人の立場からすれば、太平洋を乗り越えて極東で出逢うことになった日本人もまた、二〇世紀における新たなインディアンに他ならない。このことは、俳優の渡辺兼やトム・クルーズらが登場して、西洋人が彼らの視点から日本人を描いてひととき話題になった映画『ラストサムライ』を見ても明らかである。この映画と、アメリカ・インディアンの視点から合衆国軍との戦いを描いたケビン・コスナー監督主演の『ダンス・ウィズ・ウルブズ』の二つの映画の本質的な同質性からも見てとれるものである。アメリカ合衆国人から見れば、十九世紀のアメリカ・インディアンも、二〇世紀にアメリカが極東で出逢い太平洋戦争を戦うことになった私たち日本人も本質的に異なるものではない。
すでに日本人は相応の文化を保持していたから、もちろん、アメリカ・インディアンとは異なって、簡単には部族を消滅させられることはなかった。むしろ、黒船来航を機に、日本人は明治維新をやり遂げて強力な軍事力を持つ近代国家を確立して、欧米列強と互角に対峙し得るまでになった。とはいえ、すでに歴史に見るとうり、日本人もまたアメリカインディアンと同様に、最終的には原子力爆弾の投下によって力ずくで壊滅させられ、そして、アメリカ合衆国軍による日本の占領統治は現在にいたるまで事実上続いている。
歴史を大きなパースペクティブから見つめるとき、つまり世界史の視点で自己を客観視するとき、あるいはヨーロッパ人やアメリカ合衆国人の視点で日本と日本人を見つめるとき、アメリカ・インディアンも日本人もさしたる違いはないのである。日本人は二〇世紀のインディアンに過ぎない。これからの世界史を私たちが生き抜こうとするとき、こうした歴史の教訓と立場を自覚しておく必要があるだろう。