ホサナホサナ神の造りし日常に汲めども尽きぬ源泉がある
市原克敏『無限』
「ホサナ」とは、ヘブライ語で「救いたまえ」の意味で、イエス様のエルサレム入りの際に民衆が挙げた叫びとして知られている。とうとう救い主がお現れになったと感極まって、群衆が上げた喜びの声であったのだろう。
市原克敏に「神の造りし日常」という言葉を選び取らせたものは何だったのか、私は考える。なぜ「世界」などの語でなく「日常」なのか。
市原は生前に歌集を一冊も残さなかった。『無限』は、市原の死後にお連れ合いの賤香氏によって編まれた遺歌集である。晩年に骨髄の病気を発症された市原の歌には、通院や入院に纏わる歌も多い。市原の「日常」が決して生易しいものでなかったことは、巻末に付された賤香氏による「抛(ほう)られたる一ヶは〜市原克敏病床の記録」からも歴然としている。市原は決して苦しみを声高に語ったりはしないが、死の影が付き纏う日常が氏を広大な思索へと導いたと知ると、深い感慨に襲われる。市原の「日常」にあった「汲めども尽きぬ源泉」を探って、市原の思考の径路を辿る論考も既に発表されているし、さらに何か付言するのは私には難しい。ここでは私達の「日常」に潜む「尽きぬ源泉」とはどんなものか私なりに綴ってみたい。
私は普段から体調が良いことは極めて稀である。以前は不調時はすぐ医者へ行ったが、対症療法的に処方を受けるだけで根本的な解決には至らなかった。それで、病因の究明も見据えつつも、次第に「いかに体調を整えて生活するか」に腐心するようになっていった。日々の天気にもいちいち体調が左右される私であるし、服選びは体感に合わせて、素材やインナーの種類、首周りや靴下などのパーツにもきめ細かく気を配っている。また、何をどういう順番で食べたり飲んだりすれば体調が回復するかにも神経を遣っている。これらの事柄は、ある意味煩わしい現実かもしれない。けれどある時から、こういう工夫をすることを何だか楽しめるようになってきた。
体力をつけるために作業所の職員に勧められて始めた散歩も最近は少しサボり気味なのだが、散歩を単なる鍛錬と捉えるのでなく、時間帯によって刻々と変わる雲や空の様子、道端の草花の有り様などに目を凝らすようになって、季節の移ろいを感じつつ暮らすことの豊かさを噛み締めている。そうした努力をしても、体調が思うに任せないことも間々ある。しかしそういう時は、不如意な身体の具合に悩まされている方々のことがふと浮かび、臥しつつ執り成しの祈りをするなどしている。
また以前は、自分の作業所の仕事に不遇を託つようなところもあったのだが、今はどういう手順にすれば効率よく作業が回るかを考えたり、メンバーや職員など一人一人重視しているものの異なる相手に合わせて掛ける言葉を替えたりして意思疎通を図るなど、微細なところに目を行き届かせることを心掛けている。そうした工夫を重ねていると、たとえ段取りやコミュニケーションが少し上手くいかなかった場合でも、それはそれで次に生かせるという気がするし、むしろ自分がパーフェクトに立ち回れないことで周りがそれを補う行動に出てくれるきっかけになったりしていて、思いがけない恵みを感じられている。
最後に、掲出歌の元になった聖句を引いておく。
「シオンの娘に告げよ。『見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方で、ろばに乗り、荷を負うろばの子、子ろばに乗って。』」 弟子たちは行って、イエスが命じられたとおりにし、 ろばと子ろばを引いて来て、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。 大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また、ほかの人々は木の枝を切って道に敷いた。 そして群衆は、イエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。「ダビデの子にホサナ。主の名によって来られる方に、祝福があるように。いと高きところにホサナ。」 (マタイによる福音書21章5節〜9節)
仔ろばに乗ってエルサレムに入城した主を見て、当座多くの者は歓喜の声を上げた。でも、(え?ろば?)と内心クスッと笑った人もいたかもしれない。けれど、私はイエス様がそんな方で良かったなと心から思う。主は決して格好つけない。不遜極まりない私達に、ツッコミを入れさせてくださる優しい方なのである。











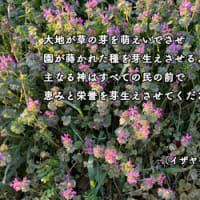















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます