奉職のなほ叶はざるわれのごとし獣類はみな檻に寝てゐる
西巻氏は歌集でも精神の病のことを公言しているので、今回のこの稿でも少し立ち入ったことを書く。氏は、体調を崩されて入院などもあった中、就労支援での農作業や民間企業の警備員など、様々な職業遍歴を重ねてこられたようである。私は不思議なご縁で西巻氏と密にやり取りする機会を得たが、そのことを通じて氏がいかに真面目な方かすぐ判った。特に、他の方であれば明言を避けるような事柄も、具体に落とし込んで語り、仰ったことに責任を取ろうとする誠実な方である。
ここ何年かの私の実感として、世の中には具体的に語った人に責任をおっ被せる風潮があるのではないかという感触を抱いている。掲出歌は、動物園で物憂く寝転んでいる動物達を眺め、自分のようだと重ね合わせている。西巻氏は、色々なことが視え過ぎるところがある気がする。そして、ある事柄の問題点などが見えた時、正直にそれを指摘できるがゆえに、浮薄な方々は「それっ!」とばかりに乗っかってしまうのだろう。結果として西巻氏は、提案者としてだけでなくその実行者としても責任を追求され、首が回らなくなって寝込む羽目になっていることが多いように、僭越ながら思う。
安定して通ふは難(かた)しけふもまた電話をかけて欠勤を告ぐ
私自身もあまり身体の強いほうではないので、この歌の心情は痛いほど解る。私の場合、朝の不調だけで心がぐらついてしまい、出勤できるかどうかという点においてすら自分を信用できない。色々手を打ってみても体調が持ち直さない時、作業所に電話して何と言い開くべきかと考えて、上司の反応を想像するだけで打ちのめされてくる。
また精神科に通院している方は、睡眠導入剤や鎮静剤などの安定剤を処方してもらっている人が殆どだと思うが、夜に眠れずに追加した安定剤が効きすぎて翌日の午前いっぱい眠気や懈さ・ふらつき等が残るのはごく日常のことである。そんな中で一時的にでも発破をかけるためにカフェインを摂り、また夜に眠れなくなるという悪循環に陥る患者がいるということもよく耳にする。
労働といふ鋳型に体(たい)を注ぐこと難しくわれの輪郭あはし
マルコによる福音書2章には、イエスが中風の人を癒す場面が描かれている。〈四人の男が中風の人を運んで来た。しかし、群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられる辺りの屋根をはがして穴をあけ、病人の寝ている床をつり降ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中風の人に、「子よ、あなたの罪は赦される」と言われた。ところが、そこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。「この人は、なぜこういうことを口にするのか。神を冒瀆している。神おひとりのほかに、いったいだれが、罪を赦すことができるだろうか。」イエスは、彼らが心の中で考えていることを、御自分の霊の力ですぐに知って言われた。「なぜ、そんな考えを心に抱くのか。中風の人に『あなたの罪は赦される』と言うのと、『起きて、床を担いで歩け』と言うのと、どちらが易しいか。人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを知らせよう。」そして、中風の人に言われた。「わたしはあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。」その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、「このようなことは、今まで見たことがない」と言って、神を賛美した。〉[2章3〜12節]
中風とは、意識はあるが突然半身不随になるような病気で、現在では脳血管障害(脳卒中)の後遺症と原因が分かってきているようである。しかし、イエスが世の中に生きていらした頃はまだそういうことも解明されておらず、中風の人は自身の罪のゆえと咎められることもあったのだろう。反駁できずただ横たわっているしかできない中風の人の苦しみを見てイエスは憐れみ、「あなたの罪は赦される」と仰せられた。その場にいた律法学者が(越権行為だ!)とばかりに目を剥いていた情景が浮かぶ。イエスは罪悪感まみれの人を裁くように行動に追い立てたりはなさらなかった。
掲出歌に戻ろう。「獣類はみな檻に寝てゐる」のである。ただ怠惰だと言うのではない。抜け出せないところに居て打ち伏しているのだ。イエスは、精神の病の患者さんが力なく横たわっているのを見て、どんな気持ちで、何を語ろうとされているだろうか。
ルカによる福音書22章31〜32節に、イエスが十字架にかかる前の晩に弟子のペトロに呼びかけた言葉が記されている。「シモン、シモン、サタンはあなたがたを、小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし、わたしはあなたのために、信仰が無くならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」
私も日々の通所はそれだけで闘いである。作業所に一報を入れるのも骨が折れる。これさえやっていればOKというものも無い。けれど、そんなジタバタでさえ誰かの励ましになるのであれば、惜しみなく分かち合いたいと思う。
西巻真『ダスビダーニャ』
西巻氏は歌集でも精神の病のことを公言しているので、今回のこの稿でも少し立ち入ったことを書く。氏は、体調を崩されて入院などもあった中、就労支援での農作業や民間企業の警備員など、様々な職業遍歴を重ねてこられたようである。私は不思議なご縁で西巻氏と密にやり取りする機会を得たが、そのことを通じて氏がいかに真面目な方かすぐ判った。特に、他の方であれば明言を避けるような事柄も、具体に落とし込んで語り、仰ったことに責任を取ろうとする誠実な方である。
ここ何年かの私の実感として、世の中には具体的に語った人に責任をおっ被せる風潮があるのではないかという感触を抱いている。掲出歌は、動物園で物憂く寝転んでいる動物達を眺め、自分のようだと重ね合わせている。西巻氏は、色々なことが視え過ぎるところがある気がする。そして、ある事柄の問題点などが見えた時、正直にそれを指摘できるがゆえに、浮薄な方々は「それっ!」とばかりに乗っかってしまうのだろう。結果として西巻氏は、提案者としてだけでなくその実行者としても責任を追求され、首が回らなくなって寝込む羽目になっていることが多いように、僭越ながら思う。
安定して通ふは難(かた)しけふもまた電話をかけて欠勤を告ぐ
私自身もあまり身体の強いほうではないので、この歌の心情は痛いほど解る。私の場合、朝の不調だけで心がぐらついてしまい、出勤できるかどうかという点においてすら自分を信用できない。色々手を打ってみても体調が持ち直さない時、作業所に電話して何と言い開くべきかと考えて、上司の反応を想像するだけで打ちのめされてくる。
また精神科に通院している方は、睡眠導入剤や鎮静剤などの安定剤を処方してもらっている人が殆どだと思うが、夜に眠れずに追加した安定剤が効きすぎて翌日の午前いっぱい眠気や懈さ・ふらつき等が残るのはごく日常のことである。そんな中で一時的にでも発破をかけるためにカフェインを摂り、また夜に眠れなくなるという悪循環に陥る患者がいるということもよく耳にする。
労働といふ鋳型に体(たい)を注ぐこと難しくわれの輪郭あはし
マルコによる福音書2章には、イエスが中風の人を癒す場面が描かれている。〈四人の男が中風の人を運んで来た。しかし、群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられる辺りの屋根をはがして穴をあけ、病人の寝ている床をつり降ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中風の人に、「子よ、あなたの罪は赦される」と言われた。ところが、そこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。「この人は、なぜこういうことを口にするのか。神を冒瀆している。神おひとりのほかに、いったいだれが、罪を赦すことができるだろうか。」イエスは、彼らが心の中で考えていることを、御自分の霊の力ですぐに知って言われた。「なぜ、そんな考えを心に抱くのか。中風の人に『あなたの罪は赦される』と言うのと、『起きて、床を担いで歩け』と言うのと、どちらが易しいか。人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを知らせよう。」そして、中風の人に言われた。「わたしはあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。」その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、「このようなことは、今まで見たことがない」と言って、神を賛美した。〉[2章3〜12節]
中風とは、意識はあるが突然半身不随になるような病気で、現在では脳血管障害(脳卒中)の後遺症と原因が分かってきているようである。しかし、イエスが世の中に生きていらした頃はまだそういうことも解明されておらず、中風の人は自身の罪のゆえと咎められることもあったのだろう。反駁できずただ横たわっているしかできない中風の人の苦しみを見てイエスは憐れみ、「あなたの罪は赦される」と仰せられた。その場にいた律法学者が(越権行為だ!)とばかりに目を剥いていた情景が浮かぶ。イエスは罪悪感まみれの人を裁くように行動に追い立てたりはなさらなかった。
掲出歌に戻ろう。「獣類はみな檻に寝てゐる」のである。ただ怠惰だと言うのではない。抜け出せないところに居て打ち伏しているのだ。イエスは、精神の病の患者さんが力なく横たわっているのを見て、どんな気持ちで、何を語ろうとされているだろうか。
ルカによる福音書22章31〜32節に、イエスが十字架にかかる前の晩に弟子のペトロに呼びかけた言葉が記されている。「シモン、シモン、サタンはあなたがたを、小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし、わたしはあなたのために、信仰が無くならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」
私も日々の通所はそれだけで闘いである。作業所に一報を入れるのも骨が折れる。これさえやっていればOKというものも無い。けれど、そんなジタバタでさえ誰かの励ましになるのであれば、惜しみなく分かち合いたいと思う。











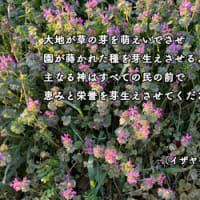















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます