ゼロトレランスが提唱される背景。
校内暴力の深刻化で多くの校則が作られました。 それは、問題の解決ではなく、子ども達のストレスに繋がったと感じます。 その反動からか、管理教育への批判が続き、教師が孤立化したように思います。
一方、親も教師も問題の本質から目をそむけてきました。 子ども達が社会を信頼しないということ。 大人達が教育の認知と位置づけをしないから、子ども達に伝わっていないということ。 簡単に言えば、社会や学校・教師が信用されていない、という問題です。
根底の問題は無視して子どもの 「ありのまま」 を伸ばそうと考えた 「ゆとり教育」 は失敗してしまいました。
学級崩壊という状態にまで追い込まれた教育現場もあるわけです。 それでも、教師の育成が真剣に論じられ実行されたとは思えません。
そして、更なる反動として 「ゼロトレランスの提唱」 に繋がっているように感じます。
PTAなどで接すると、子ども達の問題以前に親の問題を実感しています。 ゼロトレランスの運用で、出席を停止させて問題のある子ども達を家庭に返しても家庭では何も解決出来ないでしょう。 それは排除にしかならないと思います。 とことん生徒の面倒を見るにはどうするのか、という問題にどう向き合うのか?
今回報告は、都道府県の教育委員会に判断を任せるような論調の内容です。 これでは、「ゆとり教育」 の失敗を、内容を変えて繰り返すだけのような感じを持たざるを得ません。
現場教師の実態と、学校・教師を取り巻く社会構造にも目を向けてゼロトレランスの運用を考えてもらいたいと痛切に感じます。

















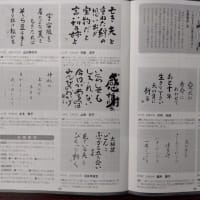


アメリカからの受け入れは、カントリーミュージックとコーラとポップコーンで十分です。
罰則を課すまでの教師や保護者の過程が問われますね。