かわばたやすなり(川端康成)の
小説『雪国』には、
にいがた(越後湯沢)の温泉地
が
描かれていましたが・・
そのなかで、主人公が
えちごちぢみ(越後縮)の産地である村を 訪れるシーン
が あり

 「 雪のなかで糸をつくり、雪のなかで織り、雪の水に洗い、雪の上
「 雪のなかで糸をつくり、雪のなかで織り、雪の水に洗い、雪の上
績み始めてから織り終るまで、すべては雪のなかであった
と
昔の人も本に書いている。 」
そう、『雪国』の中に
出てくるのですが・・
ここで記されている「昔の本 」
」
というのが、
今日、ご紹介する、
 『北越雪譜(ほくえつせっぷ)』です
『北越雪譜(ほくえつせっぷ)』です







書いたのは、
鈴木ぼくし(牧之)という、「越後縮」の 仲買人 。(※織物商ですね
。(※織物商ですね )
)
内容は
雪国のよろず百科事典で、
江戸時代後期、
数百万部をほこった、大ベストセラーでした



 べちゃ雪
べちゃ雪
 しか知らない・都会の人に、
しか知らない・都会の人に、
「本場の雪は、結晶の形で落ちてくるんだよ 」
」
とか、
「雪国には、こんな行事があるんだよ 」
」
など、
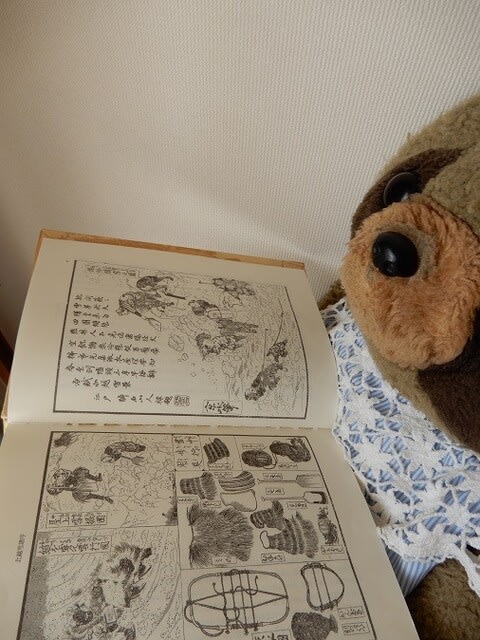 ご当地のくらしや
ご当地のくらしや 、雪にまつわる・エトセトラ
、雪にまつわる・エトセトラ


を
イラスト付きで紹介した、分かりやすい本です

 これを手に取った・読者のほうは、あたかも
これを手に取った・読者のほうは、あたかも
「異国のおとぎ話 」
」
でも きいているような
白いロマンをかんじ
うっとりしていた
らしいのですが・・
作者は
というと・・
「おめらの想像はるかに超えるほど大変なんだ こっちの暮ら
こっちの暮ら 」
」
と
ずっぷり・わからせたかった


らしく、
 雪国ならではの事故や、災害についても、
雪国ならではの事故や、災害についても、
かなり・細かく 記しています。







 今のように、「地方の事情に関する共通認識
今のように、「地方の事情に関する共通認識 」
」
が
なかった時代、
これは
たいへんに いみ(意味)のある
出版であり、
北国との取引のある商人には、さぞ役に立ったであろう


と
さっせられます


鈴木牧之が
そのような本を 書いたのは、
・彼に学問があったからだ。
とか
・江戸の文化人とつながりがあったからだ。
とか、
・牧之の郷土振興を考える立場のためだ。
とか、
色々言われていますし、その全部であろうと 思います


 それに加え
それに加え 「
「 絶対に
絶対に
忘れてはいけないのは、書かれた時代の背景だよね 」
」
と
しん(親)友・チット
は、
言っています。







いわく
 この本が 刊行された
この本が 刊行された
1837年は、
大きな・ききん(天保の飢饉)が 発生していた年
 。
。
がし(餓死)者とかが
いっぱい出ていた、
この世のじごく(地獄)・まっただ中の時です・・


それ以前に おきた
「天明の飢饉 」から、
」から、
やっとの思いで 立ち直った
東北信えつ(越)にとっては、
つまり
ものすご~~~~く・きびしい、「悪夢の再来」のじき(時期)だった
わけです。。






 だからこそ
だからこそ 「越後財界の一角を担う商人
「越後財界の一角を担う商人 」
」
として、
牧之は、
こうそう(構想)から・30年

数々の困なん(難)を のりこえてでも


ついに
江戸での出版に こぎつけたのでしょう


彼は、つまり・・
「雪国を 滅びさせねぇぞ~

 もっと、俺ったに注目してくれ~~」
もっと、俺ったに注目してくれ~~」
という、
切なるねがい(願い)を 込めたはずです
 ぼくし(牧之)は、学問や
ぼくし(牧之)は、学問や 、江戸文化人との交流
、江戸文化人との交流
には お金を使ったけど 、
、
それ以外は
つつましく・くらし 、
、
手がたく商売に はげんでいた人だった

と
伝わっています












『北越雪譜』は、
 「越後の偉人」が 郷土のために 世に出した
「越後の偉人」が 郷土のために 世に出した 、
、
雪をもとかす
じょうねつ(情熱)の本だった!
と、
今一度、きょうちょう(強調)させて、いただきます



(みそ汁も いただきます )
)












(※すいません 写真のお味噌(日本海)は富山のメーカーのなんですけど、新潟のイメージ映像が足りなかったので使いました~。隣りの県だからいいですよね
写真のお味噌(日本海)は富山のメーカーのなんですけど、新潟のイメージ映像が足りなかったので使いました~。隣りの県だからいいですよね )
)
【 おすすめ度:歴史や古典に関心のある方に。
おすすめ度:歴史や古典に関心のある方に。


 】
】
(次回の「雪の日に読む小説」は、宮尾登美子の『蔵』を 取り上げます

 )
)














