京都不動産コンサルタントのブログ
出雲といえば、何と言おうが出雲大社、
そして神道の一大聖地ということでしょう。
そのご本殿は京都平安神宮大極殿や奈良東大寺の大仏殿より
崇高無比であったと。
雲太、和ニ、京三は平安時代の 「口遊」(くちずさみ)に残る
覚え歌だといい、
この雲が出雲大社ご本殿、
和ニが高さ15丈の東大寺大仏殿、
京三は平安神宮大極殿ということが記載されています。
1丈は10尺で
1尺は約30cmですから、
東大寺15丈の45mよりも高かったということです。
実際48mだったという計算も大林組が出していましたね。

前触れが長くなりましたが、
その出雲の歴史資料を一同に集めた特別展示会が
東山七条の京都国立博物館で開催中です。
もう折り返し期となり、
9月9日(日)までです。
是非かわいい鹿の埴輪をご覧ください。

大伽藍といえば、
この博物館の真ん前にある
三十三間堂も建築物の奥行きでは負けていません。
なにせ33間ですから(笑)

但し、こちらの長さの単位の「間(けん)」は
建築業界の1間≒1.8mではなく柱間隔の間ということで、
33の柱の間隔があるよということらしいですね。
33間といえど約60mではなく、
大よそ120mらしい。

120mは出雲の丈に換算すると(?)
40丈です。ながいですね~
どちらも共通しているのは、
時の権勢を誇った人物が関与しているからこその
大伽藍だということですね。
出雲大社は大国主命であり、
三十三間堂は後白河上皇と平清盛です。
現代にも通ずるところはありますね。
出雲といえば、何と言おうが出雲大社、
そして神道の一大聖地ということでしょう。
そのご本殿は京都平安神宮大極殿や奈良東大寺の大仏殿より
崇高無比であったと。
雲太、和ニ、京三は平安時代の 「口遊」(くちずさみ)に残る
覚え歌だといい、
この雲が出雲大社ご本殿、
和ニが高さ15丈の東大寺大仏殿、
京三は平安神宮大極殿ということが記載されています。
1丈は10尺で
1尺は約30cmですから、
東大寺15丈の45mよりも高かったということです。
実際48mだったという計算も大林組が出していましたね。

前触れが長くなりましたが、
その出雲の歴史資料を一同に集めた特別展示会が
東山七条の京都国立博物館で開催中です。
もう折り返し期となり、
9月9日(日)までです。
是非かわいい鹿の埴輪をご覧ください。

大伽藍といえば、
この博物館の真ん前にある
三十三間堂も建築物の奥行きでは負けていません。
なにせ33間ですから(笑)

但し、こちらの長さの単位の「間(けん)」は
建築業界の1間≒1.8mではなく柱間隔の間ということで、
33の柱の間隔があるよということらしいですね。
33間といえど約60mではなく、
大よそ120mらしい。

120mは出雲の丈に換算すると(?)
40丈です。ながいですね~
どちらも共通しているのは、
時の権勢を誇った人物が関与しているからこその
大伽藍だということですね。
出雲大社は大国主命であり、
三十三間堂は後白河上皇と平清盛です。
現代にも通ずるところはありますね。










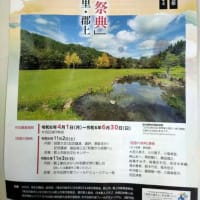




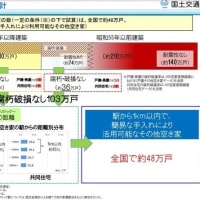
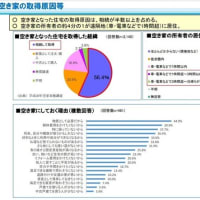

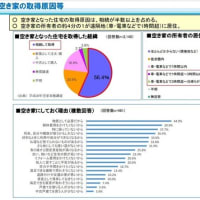






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます