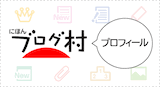コナサン、ミンバンワ!
2006=平成18年の11月も早後半。私の文化論を綴った当日記、昨夜に引続き、乗物に関わる記事の後編とさせて頂こうと思います。
今日11/19は乗物愛好者でもある私にとり、特別な日でありますね。
地元愛知の大動脈、JR東海道線が戦後、現在の様な電気運転を果した、所謂電化開業の記念日であります。1956=昭和31年の事ですから今年で丁度半世紀、50周年と言う事になります。今の所大きな記念行事などの情報が聞えて来ないのが、ちと残念ではありますが・・・。
思えば当地愛知に初めて鉄道が現れたのは遠く1886=明治19年であったやに聞いております。
この年の春、名古屋市内の熱田より、知多半島の武豊までの30km余が初開通、従って名古屋市内の路線は当時は武豊線であった事になります。この路線も今年、開通120周年と言う凄い歴史を積み重ねた事になります。
1888=明治21年までには浜松から米原までが開通し、この区間も東海道線へと昇格、武豊線は現在と同じ、名古屋南郊の大府始発となります。翌1889=同22年夏には東海道線の東京新橋~神戸間が全通し、以後我国の大動脈として飛翔する事となります。
この路線の事で今秋、小学生の我が甥が面白い質問をして参りました。それは「東海道線が岡崎の中心部より離れて通ったのはどうしてか?」との内容でありました。
以下は私の回答であります。「当時の岡崎の住民は、実は鉄道が嫌いだった。かつての宿場町だった事もあり、馬車や籠の業者が鉄道に利用客を奪われてしまい、商売が成り立たなくなって地元経済の衰弱に繋がると考えたからだ。それで東海道線は、岡崎の郊外を通らざるを得なくなった」と。
これは少なくとも半分は真実でありましょう。他の地域でもかつての宿場町を中心に、旧来の交通事業者達が仕事の減少を嫌って鉄道を忌避したと言う話はある様です。勿論、その事が理由の全てではありません。
後年判った事ですが、東海道線の当地開通に当り岡崎市の中心部はやや山がちの為、中心部に近い北寄りの配線にすると勾配が厳しくなる急な上り坂になってしまい、輸送力が苦しくなる。当時の鉄道動力は勿論、今は珍重されている蒸気機関車でありました。坂道は決して得意ではなく、急なアップ・ダウンは極力避けなければなりません。更に当時の鉄道は軍事施設の一面もありました。有事の際には陸海両軍の人員物資を速く輸送する使命もあり、この面よりも輸送力の確保が厳しく求められ、結局は郊外を通るルートのやむなきとなった模様です。岡崎中心部を通る鉄道は結局、後年の名古屋鉄道の開業まで待たなければならなかった様です。
こんな東海道線ですが、現在に至るまで名古屋を挟んだ豊橋~岐阜間では名古屋鉄道の良きライバルとなっています。
国鉄時代はその芳しくない経営体質から来る度々の運賃値上げにより不評を買ったものでしたが、1987=昭和62年のJR移行後は消費税分を除き運賃は据え置かれ、区間によっては名古屋鉄道より割安な運賃となって、近年はとみに競争力を増している様に見受けられます。
特に名古屋~豊橋間にあっては両社共、地元各位には有名な格安往復切符を設定して激闘を繰り広げています。所要時間もより短縮され、若干の追加料金にて新幹線も利用でき、自動車にての高速道路移動を上回る速達化を果たしています。こうなるともう、止むを得ない場合以外は列車の方が断然利便性は上でしょう。この事が、並行する東名道路や国道1号線の一層の渋滞緩和に貢献できれば良いと感じるのは、私1人ではないでしょう。*(新幹線)*
2006=平成18年の11月も早後半。私の文化論を綴った当日記、昨夜に引続き、乗物に関わる記事の後編とさせて頂こうと思います。
今日11/19は乗物愛好者でもある私にとり、特別な日でありますね。
地元愛知の大動脈、JR東海道線が戦後、現在の様な電気運転を果した、所謂電化開業の記念日であります。1956=昭和31年の事ですから今年で丁度半世紀、50周年と言う事になります。今の所大きな記念行事などの情報が聞えて来ないのが、ちと残念ではありますが・・・。
思えば当地愛知に初めて鉄道が現れたのは遠く1886=明治19年であったやに聞いております。
この年の春、名古屋市内の熱田より、知多半島の武豊までの30km余が初開通、従って名古屋市内の路線は当時は武豊線であった事になります。この路線も今年、開通120周年と言う凄い歴史を積み重ねた事になります。
1888=明治21年までには浜松から米原までが開通し、この区間も東海道線へと昇格、武豊線は現在と同じ、名古屋南郊の大府始発となります。翌1889=同22年夏には東海道線の東京新橋~神戸間が全通し、以後我国の大動脈として飛翔する事となります。
この路線の事で今秋、小学生の我が甥が面白い質問をして参りました。それは「東海道線が岡崎の中心部より離れて通ったのはどうしてか?」との内容でありました。
以下は私の回答であります。「当時の岡崎の住民は、実は鉄道が嫌いだった。かつての宿場町だった事もあり、馬車や籠の業者が鉄道に利用客を奪われてしまい、商売が成り立たなくなって地元経済の衰弱に繋がると考えたからだ。それで東海道線は、岡崎の郊外を通らざるを得なくなった」と。
これは少なくとも半分は真実でありましょう。他の地域でもかつての宿場町を中心に、旧来の交通事業者達が仕事の減少を嫌って鉄道を忌避したと言う話はある様です。勿論、その事が理由の全てではありません。
後年判った事ですが、東海道線の当地開通に当り岡崎市の中心部はやや山がちの為、中心部に近い北寄りの配線にすると勾配が厳しくなる急な上り坂になってしまい、輸送力が苦しくなる。当時の鉄道動力は勿論、今は珍重されている蒸気機関車でありました。坂道は決して得意ではなく、急なアップ・ダウンは極力避けなければなりません。更に当時の鉄道は軍事施設の一面もありました。有事の際には陸海両軍の人員物資を速く輸送する使命もあり、この面よりも輸送力の確保が厳しく求められ、結局は郊外を通るルートのやむなきとなった模様です。岡崎中心部を通る鉄道は結局、後年の名古屋鉄道の開業まで待たなければならなかった様です。
こんな東海道線ですが、現在に至るまで名古屋を挟んだ豊橋~岐阜間では名古屋鉄道の良きライバルとなっています。
国鉄時代はその芳しくない経営体質から来る度々の運賃値上げにより不評を買ったものでしたが、1987=昭和62年のJR移行後は消費税分を除き運賃は据え置かれ、区間によっては名古屋鉄道より割安な運賃となって、近年はとみに競争力を増している様に見受けられます。
特に名古屋~豊橋間にあっては両社共、地元各位には有名な格安往復切符を設定して激闘を繰り広げています。所要時間もより短縮され、若干の追加料金にて新幹線も利用でき、自動車にての高速道路移動を上回る速達化を果たしています。こうなるともう、止むを得ない場合以外は列車の方が断然利便性は上でしょう。この事が、並行する東名道路や国道1号線の一層の渋滞緩和に貢献できれば良いと感じるのは、私1人ではないでしょう。*(新幹線)*