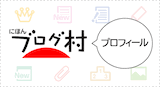国会、特に参院では 先年の安倍政権期・総務省文書問題や、先般の岸田総理・ウクライナ訪問時の大型しゃもじの文言不適切問題などが 過分に取り上げられている様だ。
これらの与党側の不適切や不足を全部擁護しきれない所もある一方、立憲民主党を初め特定野党側の攻撃的取り上げにも 全て与する訳には参らないのも事実。この様な事象をどこかで区切らなければ、参院の存在意義自体が形骸化する事ともなりかねず、ひいては廃止➡国会一院化の議論にも繋がりかねないとみる者だが、それで良いのか。拙者などはむしろその方向を望む者だが。
恐れながら そうした議論というより論争には距離を置き、今回は我国産業経済の根幹を揺るがしかねない 自動車産業の事共に少し触れる事にしたい。既報の様に、特に欧州において地球温暖化抑制に資する意味もあって 自動車の電動化、EVシフトが急速に・・というより強引に進められている印象があった。特に北欧ボルボなど急進勢力は、後 10年強で生産する全車を EV化するかの様な CMの挙に出ているのはご覧になった事もあろう。
しかしここへきて、その雲行きがやや怪しくなってきた様な風情もある様だ。この事につき、日付跨ぎともなるが 3/25の読売新聞ネット記事を引用して みて参ろうと思う。
「ガソリン車販売を事実上禁止する方針だった EU、2035年以降も条件付で容認」
欧州連合(EU) の執行機関・欧州委員会は 3/25、ガソリン車の販売を (西暦)2035年以降も条件付きで認める方針を明らかにした。二酸化炭素(CO2) と水素を合成して作る液体燃料「e-fuel」(イー・フューエル) のみを使用する車両は販売できるようにする。
欧州委は 2021(令和3)年 7月、乗用車や小型商用車の新車による CO2排出量を 2035年までにゼロにする規制案を発表した。ハイブリッド車(HV) を含むガソリン車の販売を事実上禁止し、電気自動車(EV) や燃料電池車への移行を促す内容で、欧州議会も 2022(令和4)年 10月に EU加盟国と合意した。
しかし 自動車メーカーを多く抱えるドイツが今年 2月、イー・フューエルを使用する車両は認めるべきだと主張、イタリアなど他の加盟国の一部も同調した。イー・フューエルは燃焼時に CO2を排出するが、工場などから出る CO2を原料とするため環境負荷が低く、脱炭素につながる燃料として期待されている。ただ ガソリンより割高になるという課題もある。(引用ここまで)
やはり「全部は無理だったか」との印象が付き纏う。進行に際しての強硬姿勢は拙者も感じてはいたが、やはり「自動車の祖国」といわれる独や、高性能スポーツ「フェラーリ」「ランボルギーニ」などを擁する伊などから相当な異論が出たのだろう。使用燃料を将来にも適合するだろう厳しい物品に限定すれば、認めて良いとの判断に傾いたという事だろう。
この方向に進むとなると、これまでのエンジン技術も活かせるという事となろう。相当なEVシフトも視野に入れながら、尚も HVや燃料電池車の併存も肯定するトヨタ自動車の進路は正しかったという事になるか。尤も肝心な所で、系列の日野自動車や フォーク・リフトなどの産業向け車両などを手がける豊田自動織機辺りがエンジン性能面の不正表記に関わっていたというから、それは厳しく糾されなければならないだろうが。
それにしても、強い信念に裏打ちされた様な強硬姿勢を表しながら EUの自動車政策は、ここへきてブレたと言われても仕方がないのではないか。前述の独・伊各国の産業事情もあろうが、EVシフトの進め方については 各国のエネルギー事情などとの絡みもあろう。例えばフランス国などは、原子力政策などで概ねブレない姿勢だし、独・伊両国はそこまでの態度が取り難く、又 自国の自動車産業の都合もあって そうした挙に出たのかも知れない。
そうした所に留意するにしても、EVについて やや世界の趨勢に出遅れたのではないかとの指摘もあった我国の自動車産業は、少なくとも「望みなきに非ず」の状況と位は言えるのではないか。
前出の系列不正問題も抱え 決して楽観できない場面のトヨタだろうが、既に EVメインの方向性に振った感もある日産や三菱自やホンダと立場こそ違え、ここは踏ん張り所だろう。少しでも好結果に繋がる様、奮闘を望みたい所。今回画像も昨秋ので恐縮。同年の我国内にての世界ラリー選手権日本大会「ラリー JAPAN」に出場のトヨタ競技車「ヤリス」の健闘の様子を。種目は異なるも、我国内シリーズに 試作進む燃料電池車も出場している模様。