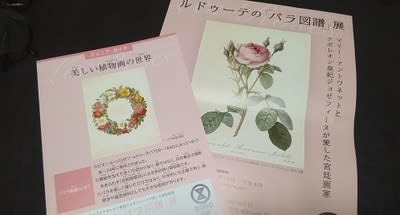
GW最終日の昨日は、横浜のそごう美術館で「ルドゥーテの『バラの図譜』展を見て来ました。
ルドゥーテとは、生涯を通じて数多くの美しい季節の花々を描き、その類まれな描写力で「花のラファエロ」「バラのレンブラント」と称えられた植物画家であり、正式の名前はピエール=ジョセフ・ルドゥーテ(1759-1840)と言います。
ルドゥーテは18世紀後半にベルギーで代々画家を職業とする家に生まれ、19世紀前半までフランスで活躍しました。
ルイ16世王妃マリー・アントワネットの博物蒐集室付画家として重用されただけでなく、フランス革命後はナポレオン皇妃ジョゼフィーヌがバラ栽培の為に巨費を投じて建てたマルメゾン宮殿の植物画家となりました。
彼の描いた植物画をモチーフに、陶製品や布製品などさまざまな小物が商品化されているので、ルドゥーテの名前は知らなくても、その作品を目にした方は意外に多いのではないでしょうか?
私自身、以前持っていた緑地にピンクのバラの花が散りばめられた日傘を、ある人に「これ、ルドゥーテの図柄じゃない?」と言われたことがあります。実際はノンブランドの商品だったので、ルドゥーテ柄の傘ではなかったと思いますが、それだけ「花」、特に「バラ」と言えば、ルドゥーテの代名詞になっているのでしょう。
彼の作品は、その繊細優美な画風と共に、克明で正確な描写から、博物学的価値も高く評価されています。
例えば下の作品は、薄絹を何枚を重ねたような柔らかそうな花弁が繊細なピンクのグラデーションで彩られて、その優美な佇まいに思わず目が釘づけになってしまいます。
正確な形態把握はもちろんのこと、背景に描かれた5つの蕾の濃いピンクが大輪の花の嫋やかさを一層引き立て、さらに上半分を支配するパステルカラーと下半分の鮮やかな葉のグリーンの色調のコントラストが絶妙で、絵画としての完成度はすこぶる高い。そして、まだ現代のようなカラー写真のなかった時代に、写実性ではひとつの頂点を極めた作品とも言えるでしょうか?

凛とした佇まいの真紅のバラ。誰も寄せ付けない孤高感さえ漂わせて…

今回の展覧会は彼の代表作と言われるバラの画集『バラ図譜』(扉絵と点刻彫版による多色刷り銅版画169点)を中心に、貴重な大判の初期作品や肉筆画も展示されています。
今回の展覧会では初めてルドゥーテの作品の"実物"を間近に見ることが出来、改めてその優美さと緻密な描写に感嘆しました。
彼が用いたとされる「点刻彫銅版画」と言う技法も、今回初めて知りました。通常、凹版銅版画は線描で対象を表現するのですが、点描はおそらく1枚の版に何百、何千と言う気の遠くなるような数の点を打刻して、陰影や立体感を表現したと思うので、版を担当した職人さん⋆はさぞかし大変だっただろうなと想像します。
⋆ルドゥーテは数多くの作品を手がけた為、彼自身による下絵と仕上げの着色、職人による版、刷りの分業で、作成したのでしょう。分業体制は鋳造彫刻や日本の浮世絵の制作と似ていますね。
またバラの品種の多さにも驚きました。花弁の形や全体のプロポーションから「これもバラなの?」と思えるようなバラも沢山あって、まさに「目から鱗が落ちる」経験でした。

一緒に見ていた夫曰く「バラであるか否かのポイントは"棘"の有る無しなんじゃない?」~なるほどね。この棘にしても、突かれたら痛いだろうなあと思わず想像してしまう鋭いものから、産毛のようにビッシリと茎に密生しているものまであり、それこそ千差万別でした。
中には大輪の花の真ん中からスッと茎が伸びて、その先に蕾が描かれているのも何枚かあり、バラの生態にあまり詳しくない私には不思議な光景でした。
当時はナポレオン皇妃ジョゼフィーヌも尽力したと言われるように、遠くはアジアの中国(中国原種なのに、なぜかインディカ種と名付けられ…おそらく当時としては西欧の人々から見れば極東の中国は遠すぎて、アジアのイメージと言えばインドが限界だったのでしょうね)や中東からバラの原種が集められ、バラの品種改良や新たな品種の開発が熱心に行われていたのですね。これも王侯貴族や大商人など、潤沢な資金があるからこそ可能なわけで…
皇妃が建てたマルメゾン宮殿には、最盛期で250種のバラが栽培されていたと言います。それだけに植物画家ルドゥーテがその才能を発揮する機会は限りなくあったのでしょう。
展覧会場では古楽器チェンバロのミニコンサートも会期中不定期に行われており、一角に据えられたチェンバロを、自由に見学したり、写真撮影することも出来ました(もちろん、ルデゥーテ作品の撮影は不可です)。
そのチェンバロ自体、優れた装飾性で見惚れるほど姿が美しく、思わず夢中でスマホカメラのシャッターを切ってしまいました(笑)。チェンバロ演奏のBGMも流れて、バッハが大好きな私には堪らない空間でした。




会期は5月28日(日)まで。チェンバロのミニコンサートのスケジュールも下記のリンクで確認できます。

























