或る一人の男が歴史を変えようと奮闘した。
しかし、歴史は変わらなかった。
変わったのは男の運命だった。
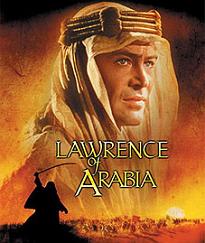 現在進行中の名作映画リバイバル上映プロジェクト『午前十時の映画祭』で、「アラビアのロレンス」を見て来た。実は映画史上に残る傑作と誉れ高い本作を、全編を通して見たのは今回が初めてだった。
現在進行中の名作映画リバイバル上映プロジェクト『午前十時の映画祭』で、「アラビアのロレンス」を見て来た。実は映画史上に残る傑作と誉れ高い本作を、全編を通して見たのは今回が初めてだった。
本作の日本公開は1963年2月。その後も何度かリバイバル上映されたとは言え、その何れもタイミングが合わず、その後ビデオやDVD化されても、「見るなら映画館の大きなスクリーンで」と言う思いで今まで来てしまった。今回、やっと望みが叶ったことになる。
本作は期待に違わぬスケールと重厚感で私を圧倒した。そして、100年近く前の史実を描きながら、当時と殆ど変わらないアラブの現状を図らずも照射して、絶望感にも似た苦い後味を残したのだった。欧米を中心とした列強の支配と、アラブ部族社会の団結力の欠如は、今もなおアラブ社会を苦しめている。パレスチナ問題然り。イラク問題然り。
 右写真は現在のアカバ。ヨルダン唯一の交易港で、言わば海の玄関口であり、また、海浜リゾート地としても名高い。
右写真は現在のアカバ。ヨルダン唯一の交易港で、言わば海の玄関口であり、また、海浜リゾート地としても名高い。
西にイスラエル、東にサウジ・アラビアとの国境が接している。紅海に面し、海を隔てた南側にはエジプトが控えている。その立地から軍事及び交通の要衝としての価値が高く、この地の領有権を巡って、歴史上、行く度かの争いも起きた。そのひとつが、本作で描かれたロレンス率いるアラブ軍による、オスマン・トルコ支配下にあったアカバ陥落である。
背後に迫り来る山々の裏側に、広大な渓谷ワディ・ラムが控えている。因みにワディとはアラビア語で「枯れた川」を意味する。
縁あって、私は今から十数年前、本作の舞台となった中東に約3年間駐在する機会を得た。当時は本作未見であった為に、もっぱら休暇の地として過ごしたアカバや、アカバに向かう途上、横目に見ながら通り過ぎただけのワディ・ラムについて、今回の鑑賞を機に、私は感慨を新たにしたと言えるだろう。
 アカバはヨルダンの首都アンマンから、デザート・ハイウエイを約300㎞南下した地点にある。いよいよアカバも近い、となった所で、右手にワディ・ラムの広大な風景を望むことができる。私が駐在していた頃にも、ワディ・ラムでベドウィン(砂漠・土漠の遊牧民族)のようにテントを張って一夜を過ごすツアーがあった。視界を遮る建物も、街明かりも一切ない土漠で見る満天の星
アカバはヨルダンの首都アンマンから、デザート・ハイウエイを約300㎞南下した地点にある。いよいよアカバも近い、となった所で、右手にワディ・ラムの広大な風景を望むことができる。私が駐在していた頃にも、ワディ・ラムでベドウィン(砂漠・土漠の遊牧民族)のようにテントを張って一夜を過ごすツアーがあった。視界を遮る建物も、街明かりも一切ない土漠で見る満天の星 は格別らしいが、当時、私は乳幼児を抱えていたので、残念ながら参加できなかった。
は格別らしいが、当時、私は乳幼児を抱えていたので、残念ながら参加できなかった。
アカバ湾は、ナポレオンフィッシュの生息地として知られる紅海に面している。海は透明度が高く、私達家族もガラスボートに乗って、その豊穣の海の中を覗き込むなどして、南国リゾートの休暇を楽しんだ記憶がある。そうした長閑な記憶とは全く違った、アカバの歴史的に複雑で数奇な一面を、私は本作「アラビアのロレンス」で知るに至ったのである。

4時間近い長尺の、壮大で複雑な物語を簡潔にまとめるには、私は明らかに力不足だ。それでも敢えてまとめるとするならば、以下のようになるだろうか?
 時代は第一次世界大戦の最中(さなか)。敵国ドイツについていたオスマン・トルコに打撃を与えること、そのトルコの支配下にあり、その牙城の一角であるアラブをつき崩し、自国の領土とすることが、当時の英国の謀略だったのだろう。そこで英国陸軍の情報将校であったロレンスは、アラブ情勢を探るべく、エジプトの英国陸軍司令部より、アラブへ派遣される。
時代は第一次世界大戦の最中(さなか)。敵国ドイツについていたオスマン・トルコに打撃を与えること、そのトルコの支配下にあり、その牙城の一角であるアラブをつき崩し、自国の領土とすることが、当時の英国の謀略だったのだろう。そこで英国陸軍の情報将校であったロレンスは、アラブ情勢を探るべく、エジプトの英国陸軍司令部より、アラブへ派遣される。
しかし、ロレンスはアラブ人達との信頼関係を深めるにつれ、本国の思惑とは違った方向へ思いを巡らせ始める。それはアラブの主権の確立、即ち独立だった。その端緒となるはずだったアカバ陥落の後、ロレンスは軍功を賞賛されるも、その運命は意外な方向へと転換するのだった…
 アラブの土地はアラブ人に、と言うロレンスの考え方はフェアで、理想だ。主権は、本来その土地に住む者に与えられるべきだ。ところが大国の欲望は留まることを知らない。英国は後に「三枚舌外交」(フサイン・マクマホン協定、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言)と皮肉られた手法で、アラブの土地を欧州列強で分割、支配下に置くことになるのである。
アラブの土地はアラブ人に、と言うロレンスの考え方はフェアで、理想だ。主権は、本来その土地に住む者に与えられるべきだ。ところが大国の欲望は留まることを知らない。英国は後に「三枚舌外交」(フサイン・マクマホン協定、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言)と皮肉られた手法で、アラブの土地を欧州列強で分割、支配下に置くことになるのである。
 ここで考えたいのは、ロレンスの人物像だ。彼は初登場シーンから、軍人らしからぬその異質さを見せている。語学が堪能で、博識で、考古学者としての一面を持つだけでない。身のこなしが柔らかく、足取りも軽やかなのだ(走り方もナヨナヨしている)。一般的な軍人のキビキビとした動作とはほど遠いのだ。それは彼のある性向を暗にほのめかしているのだろうか。
ここで考えたいのは、ロレンスの人物像だ。彼は初登場シーンから、軍人らしからぬその異質さを見せている。語学が堪能で、博識で、考古学者としての一面を持つだけでない。身のこなしが柔らかく、足取りも軽やかなのだ(走り方もナヨナヨしている)。一般的な軍人のキビキビとした動作とはほど遠いのだ。それは彼のある性向を暗にほのめかしているのだろうか。
彼は劇中で、貴族の婚外子であることを自ら告白するが、そうした出自も、彼を異端児たらしめているように見える。ここで言う異端児はけっして悪い意味ではなく、思想的にリベラルと言うことだ。アウトサイダーだからこそ権力にも盲従せず、アラブ人の立場で現状を観察することができ、その不条理に気づいたのだと思う。
もちろん本作は史実を下敷きとしながらも、映画として劇的効果を高める為にフィクションが加えられ、一部史実とは異なるようだ(反乱軍を率いていたのはロレンスではなくファイサル王子。トルコ軍はジュネーブ条約を遵守し、捕虜に対して残虐行為を行うことなどなかった等)。アラブ反乱におけるロレンスの位置づけも、これまで二転三転していると聞く。それでもなお本作が見る者に感動を与えるのは、ひとつにはロレンスの波瀾万丈の半生を、雄大な砂漠の風景の中で描いたことにあるのだろう。少なくとも彼はアラブを理解し、アラブの為に戦い、アラブの人々も、そのカリスマ性を一時は信じたはずだ。同時に、本作では砂漠と言うロケーションもまたひとつの主役であり、雄大な自然の中で蠢く人間の矮小さが印象的だった。思わずつぶやいたものだ。「人間ってちっぽけだなあ…」と。
「撮影隊ではなく、探検隊」とデビッド・リーン監督をして言わしめた苛酷な砂漠での撮影は、砂漠の美しさと冷徹さをあますことなくスクリーンに映し出している。当時のメイキング映像には、「ロケーションの探索にジープ数十台と飛行機を駆使し、撮影場所となった砂漠ではスタッフ・キャスト用に百以上のテントを設営する」様子が残されていると言うから、その苦心惨憺が偲ばれる。この空前絶後のロケーションを可能にしたのは、常に「(困難を伴う)新しい道を歩むことを心がけた」監督のチャレンジ精神なのだろう。
 そして、その撮影を陰で支えたひとりが、他ならぬヨルダンの故フセイン前国王であったことを、今回初めて知った。実は本作に登場するファイサル王子は、故フセイン前国王の祖父、アブドゥッラー国王の弟君に当たる。現ヨルダン・ハシミテ王国建国にも、本作で描かれたアラブの反乱は少なからず関与しているというわけだ。
そして、その撮影を陰で支えたひとりが、他ならぬヨルダンの故フセイン前国王であったことを、今回初めて知った。実は本作に登場するファイサル王子は、故フセイン前国王の祖父、アブドゥッラー国王の弟君に当たる。現ヨルダン・ハシミテ王国建国にも、本作で描かれたアラブの反乱は少なからず関与しているというわけだ。
撮影当時、フセイン国王は自国の軍隊をエキストラとして貸し出すなど、撮影に協力を惜しまず、度々撮影現場にも足を運び、そこで後に二番目の妻となった英国人女性、アントワネット・アヴリル・ガーディナー(Antoinette Avril Gardiner)と出会っている。因みに彼女との間に生まれた長男が、アブドゥッラー現国王である。(写真はヨルダン駐在時、夫が故フセイン前国王と謁見した時のもの)
しかし、歴史は変わらなかった。
変わったのは男の運命だった。
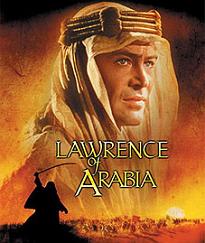 現在進行中の名作映画リバイバル上映プロジェクト『午前十時の映画祭』で、「アラビアのロレンス」を見て来た。実は映画史上に残る傑作と誉れ高い本作を、全編を通して見たのは今回が初めてだった。
現在進行中の名作映画リバイバル上映プロジェクト『午前十時の映画祭』で、「アラビアのロレンス」を見て来た。実は映画史上に残る傑作と誉れ高い本作を、全編を通して見たのは今回が初めてだった。本作の日本公開は1963年2月。その後も何度かリバイバル上映されたとは言え、その何れもタイミングが合わず、その後ビデオやDVD化されても、「見るなら映画館の大きなスクリーンで」と言う思いで今まで来てしまった。今回、やっと望みが叶ったことになる。
本作は期待に違わぬスケールと重厚感で私を圧倒した。そして、100年近く前の史実を描きながら、当時と殆ど変わらないアラブの現状を図らずも照射して、絶望感にも似た苦い後味を残したのだった。欧米を中心とした列強の支配と、アラブ部族社会の団結力の欠如は、今もなおアラブ社会を苦しめている。パレスチナ問題然り。イラク問題然り。
 右写真は現在のアカバ。ヨルダン唯一の交易港で、言わば海の玄関口であり、また、海浜リゾート地としても名高い。
右写真は現在のアカバ。ヨルダン唯一の交易港で、言わば海の玄関口であり、また、海浜リゾート地としても名高い。西にイスラエル、東にサウジ・アラビアとの国境が接している。紅海に面し、海を隔てた南側にはエジプトが控えている。その立地から軍事及び交通の要衝としての価値が高く、この地の領有権を巡って、歴史上、行く度かの争いも起きた。そのひとつが、本作で描かれたロレンス率いるアラブ軍による、オスマン・トルコ支配下にあったアカバ陥落である。
背後に迫り来る山々の裏側に、広大な渓谷ワディ・ラムが控えている。因みにワディとはアラビア語で「枯れた川」を意味する。
縁あって、私は今から十数年前、本作の舞台となった中東に約3年間駐在する機会を得た。当時は本作未見であった為に、もっぱら休暇の地として過ごしたアカバや、アカバに向かう途上、横目に見ながら通り過ぎただけのワディ・ラムについて、今回の鑑賞を機に、私は感慨を新たにしたと言えるだろう。
 アカバはヨルダンの首都アンマンから、デザート・ハイウエイを約300㎞南下した地点にある。いよいよアカバも近い、となった所で、右手にワディ・ラムの広大な風景を望むことができる。私が駐在していた頃にも、ワディ・ラムでベドウィン(砂漠・土漠の遊牧民族)のようにテントを張って一夜を過ごすツアーがあった。視界を遮る建物も、街明かりも一切ない土漠で見る満天の星
アカバはヨルダンの首都アンマンから、デザート・ハイウエイを約300㎞南下した地点にある。いよいよアカバも近い、となった所で、右手にワディ・ラムの広大な風景を望むことができる。私が駐在していた頃にも、ワディ・ラムでベドウィン(砂漠・土漠の遊牧民族)のようにテントを張って一夜を過ごすツアーがあった。視界を遮る建物も、街明かりも一切ない土漠で見る満天の星アカバ湾は、ナポレオンフィッシュの生息地として知られる紅海に面している。海は透明度が高く、私達家族もガラスボートに乗って、その豊穣の海の中を覗き込むなどして、南国リゾートの休暇を楽しんだ記憶がある。そうした長閑な記憶とは全く違った、アカバの歴史的に複雑で数奇な一面を、私は本作「アラビアのロレンス」で知るに至ったのである。

4時間近い長尺の、壮大で複雑な物語を簡潔にまとめるには、私は明らかに力不足だ。それでも敢えてまとめるとするならば、以下のようになるだろうか?
 時代は第一次世界大戦の最中(さなか)。敵国ドイツについていたオスマン・トルコに打撃を与えること、そのトルコの支配下にあり、その牙城の一角であるアラブをつき崩し、自国の領土とすることが、当時の英国の謀略だったのだろう。そこで英国陸軍の情報将校であったロレンスは、アラブ情勢を探るべく、エジプトの英国陸軍司令部より、アラブへ派遣される。
時代は第一次世界大戦の最中(さなか)。敵国ドイツについていたオスマン・トルコに打撃を与えること、そのトルコの支配下にあり、その牙城の一角であるアラブをつき崩し、自国の領土とすることが、当時の英国の謀略だったのだろう。そこで英国陸軍の情報将校であったロレンスは、アラブ情勢を探るべく、エジプトの英国陸軍司令部より、アラブへ派遣される。しかし、ロレンスはアラブ人達との信頼関係を深めるにつれ、本国の思惑とは違った方向へ思いを巡らせ始める。それはアラブの主権の確立、即ち独立だった。その端緒となるはずだったアカバ陥落の後、ロレンスは軍功を賞賛されるも、その運命は意外な方向へと転換するのだった…
 アラブの土地はアラブ人に、と言うロレンスの考え方はフェアで、理想だ。主権は、本来その土地に住む者に与えられるべきだ。ところが大国の欲望は留まることを知らない。英国は後に「三枚舌外交」(フサイン・マクマホン協定、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言)と皮肉られた手法で、アラブの土地を欧州列強で分割、支配下に置くことになるのである。
アラブの土地はアラブ人に、と言うロレンスの考え方はフェアで、理想だ。主権は、本来その土地に住む者に与えられるべきだ。ところが大国の欲望は留まることを知らない。英国は後に「三枚舌外交」(フサイン・マクマホン協定、サイクス・ピコ協定、バルフォア宣言)と皮肉られた手法で、アラブの土地を欧州列強で分割、支配下に置くことになるのである。 ここで考えたいのは、ロレンスの人物像だ。彼は初登場シーンから、軍人らしからぬその異質さを見せている。語学が堪能で、博識で、考古学者としての一面を持つだけでない。身のこなしが柔らかく、足取りも軽やかなのだ(走り方もナヨナヨしている)。一般的な軍人のキビキビとした動作とはほど遠いのだ。それは彼のある性向を暗にほのめかしているのだろうか。
ここで考えたいのは、ロレンスの人物像だ。彼は初登場シーンから、軍人らしからぬその異質さを見せている。語学が堪能で、博識で、考古学者としての一面を持つだけでない。身のこなしが柔らかく、足取りも軽やかなのだ(走り方もナヨナヨしている)。一般的な軍人のキビキビとした動作とはほど遠いのだ。それは彼のある性向を暗にほのめかしているのだろうか。彼は劇中で、貴族の婚外子であることを自ら告白するが、そうした出自も、彼を異端児たらしめているように見える。ここで言う異端児はけっして悪い意味ではなく、思想的にリベラルと言うことだ。アウトサイダーだからこそ権力にも盲従せず、アラブ人の立場で現状を観察することができ、その不条理に気づいたのだと思う。
もちろん本作は史実を下敷きとしながらも、映画として劇的効果を高める為にフィクションが加えられ、一部史実とは異なるようだ(反乱軍を率いていたのはロレンスではなくファイサル王子。トルコ軍はジュネーブ条約を遵守し、捕虜に対して残虐行為を行うことなどなかった等)。アラブ反乱におけるロレンスの位置づけも、これまで二転三転していると聞く。それでもなお本作が見る者に感動を与えるのは、ひとつにはロレンスの波瀾万丈の半生を、雄大な砂漠の風景の中で描いたことにあるのだろう。少なくとも彼はアラブを理解し、アラブの為に戦い、アラブの人々も、そのカリスマ性を一時は信じたはずだ。同時に、本作では砂漠と言うロケーションもまたひとつの主役であり、雄大な自然の中で蠢く人間の矮小さが印象的だった。思わずつぶやいたものだ。「人間ってちっぽけだなあ…」と。
「撮影隊ではなく、探検隊」とデビッド・リーン監督をして言わしめた苛酷な砂漠での撮影は、砂漠の美しさと冷徹さをあますことなくスクリーンに映し出している。当時のメイキング映像には、「ロケーションの探索にジープ数十台と飛行機を駆使し、撮影場所となった砂漠ではスタッフ・キャスト用に百以上のテントを設営する」様子が残されていると言うから、その苦心惨憺が偲ばれる。この空前絶後のロケーションを可能にしたのは、常に「(困難を伴う)新しい道を歩むことを心がけた」監督のチャレンジ精神なのだろう。
 そして、その撮影を陰で支えたひとりが、他ならぬヨルダンの故フセイン前国王であったことを、今回初めて知った。実は本作に登場するファイサル王子は、故フセイン前国王の祖父、アブドゥッラー国王の弟君に当たる。現ヨルダン・ハシミテ王国建国にも、本作で描かれたアラブの反乱は少なからず関与しているというわけだ。
そして、その撮影を陰で支えたひとりが、他ならぬヨルダンの故フセイン前国王であったことを、今回初めて知った。実は本作に登場するファイサル王子は、故フセイン前国王の祖父、アブドゥッラー国王の弟君に当たる。現ヨルダン・ハシミテ王国建国にも、本作で描かれたアラブの反乱は少なからず関与しているというわけだ。撮影当時、フセイン国王は自国の軍隊をエキストラとして貸し出すなど、撮影に協力を惜しまず、度々撮影現場にも足を運び、そこで後に二番目の妻となった英国人女性、アントワネット・アヴリル・ガーディナー(Antoinette Avril Gardiner)と出会っている。因みに彼女との間に生まれた長男が、アブドゥッラー現国王である。(写真はヨルダン駐在時、夫が故フセイン前国王と謁見した時のもの)
(了)

























