3.上野の東京都美術館で開催中の「マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展~「印象、日の出」から「睡蓮」まで」(前期)
順序としては、こちらが一番先に見た展覧会でした。常に美術に関連した有益な情報を発信してくれるHさんのおかげで、前期(9/19~10/18)・後期(10/20~12/13)と2枚のチケットを事前に公式サイトで、かなりお得な価格で入手することが出来ました。この件に関してはHさんに感謝!
なぜ、前期・後期とチケットを販売するのかと言えば、期間限定で展示される作品があるからです。
前期は「印象派」と言うグループの名前の由来にもなった記念碑的作品《日の出、印象》(1872)、後期は《ヨーロッパ橋、サン=ラザール駅》(1877)と、それぞれ期間限定で展示されます。両作品共、門外不出とは言わないまでも、滅多に貸し出されないマルモッタン・モネ美術館が誇るコレクションのひとつと言うことなのでしょうか?
特に《印象、日の出》は実に21年ぶりに東京に来たらしく、マルモッタン・モネ美術館からは貸し出しの条件として、本作品は他の作品とは別区画で単独展示して欲しいと言われたのだとか。

モネ32歳頃の作品で、今見れば何のことはない印象派の作品なのかもしれませんが、発表された当時の画壇では、その曖昧な形態描写と淡い色遣いで「未完成品」扱いされたほど、従来の絵画のセオリーを無視したセンセーショナルな作品でありました。
実際、展示室で目の当たりにしても、薄暗い展示室の照明の下では私の目が悪いせいか、全体的にぼやけて見えました。ネットに上がっている画像群を見ても、かなり色彩の再現にバラツキが見られ、肉眼で見るのとは大きく印象が異なります。それほど繊細な色遣いで描かれた作品と言うことなのでしょう。
おそらく照明によっても見え方がかなり変わるのかもしれません。国立西洋美術館でも、同じ作品が展示替えによって位置を変えただけで、照明の当たり具合(照射される角度)の変化で、思いがけない色が新たに浮かび上がって来たり、細部までクッキリ見えるようになったり、またはその逆だったりと、見え方が大きく変わるぐらいですから。
また、2年前にパリのオルセー美術館で印象派絵画を見た時に感じたことですが、改装工事で壁の色が深い藍色に変わったことで、印象派絵画の色彩が一層光を帯びて華やいで見えたのが印象的でした。特にエドゥアール・マネの《草上の昼食》の美しかったこと!現在、国立西洋美術館のモネの部屋は白一色の壁ですが、これがオルセーと同様に藍色の壁だとしたら、モネの繊細な色遣いの作品群が、どんな風に変わって見えるのだろうと言う興味があります。
《日の出、印象》は既成の価値観に抗い、絵画と言うジャンルに新たな地平を切り開いた作品として、美術史上特筆すべきものですが、個人的に好きか、印象に残るか、と聞かれれば、私は「それほどでも」と答えるでしょう。と言うのも、既に印象派が近代西洋絵画の一ジャンルとして広く認知されているので、その文脈の中では驚きがないからです。
この日の展示室の鑑賞者の反応も、仰々しく列に並んで見た割には特にこれと言った感想はないようで、その価値を分かりかねて戸惑っているようにも見えました。結局、一般の鑑賞者には作品の歴史的価値は事実として理解はできるけれども、鑑賞の楽しみにはあまり関係がないということなのでしょうか?もちろん、美術史をより深く理解したいと言う人には必見の作品ではあります。
 写真は《白いクレマチス》(1887)。モネ47歳頃の作品で、既に創作拠点をパリ郊外のジヴェルニーに移した後に、自邸の庭で描いたものと思われます。
写真は《白いクレマチス》(1887)。モネ47歳頃の作品で、既に創作拠点をパリ郊外のジヴェルニーに移した後に、自邸の庭で描いたものと思われます。
キャンバス一面に白と緑を基調に柔らかな筆致で描かれたクレマチス。そのたおやかさに心が癒されます。モネのジヴェルニーにおける幸福で充実した日々が容易に想像できる作品です。
本作品もまた、花のみをキャンバス全体に描いた大胆な構図が従来の花の描き方にはなかった点で、美術史上特筆すべきものであり、後年の、池の輪郭線さえなく、ただ水面に浮かぶ睡蓮と水面に映り込んだ周囲の景色を、色彩の競演(饗宴?)とも言うべき色遣いと、画家の手の動きさえ想像できるような筆触で描いた《睡蓮》の作品群に連なるものと言えます。
今回の展覧会はモネ10代の最初期から80代の最晩年までの作品約90点を展示し、画家モネの生涯に渡る画業の軌跡を辿る構成となっています。これまで日本では何度もモネ展が開催されていますが、これほどまでに全年代の作品を網羅した展覧会は、私が記憶する限り、本展覧会がおそらく初めてと思われます。さすが"モネ"の名を冠している美術館だけのことはあります。見ごたえがあります。
特に印象に残っているのは、モネが白内障を患って以後の最晩年の作品です。日本各地の美術館に数多くのモネの作品が収蔵されていますが、殆どが盛期の作品であり(最晩年の作品と言えるのは国立西洋美術館の《睡蓮》(1916)を含め3点ほど)、今後日本で、これだけの数の最晩年の作品を見られる機会は、もうないかもしれません。その意味でもオススメの展覧会です。
ただし、平日でも入場まで30分待ちが珍しくないほど混雑しています。それでも見る価値のある展覧会だと思います。
 左の画像は《バラの小道 ジヴェルニー》(1920-22)。モネが80~82歳にかけて描いた作品です。
左の画像は《バラの小道 ジヴェルニー》(1920-22)。モネが80~82歳にかけて描いた作品です。
60歳の頃から徐々に視力の衰えを感じたモネでしたが、白内障と診断された後も、当時は現在ほど術後の治癒率が高くなく、失明の恐れもあった為、長らく手術を躊躇っていたそうです。
この作品は、白内障を患ったモネが、白内障の影響で色彩の識別も困難な中で描いた作品と言われています。実際、モネの手術前と後の作品を比較して、白内障による色の識別能力の変化について言及した研究報告もあるようです。
「高齢者に多い白内障では、濁った水晶体の中で短波長の光が吸収されてしまうので、赤や緑はよく見えるが、青(などの短波長の色)だけが暗くなって見にくくなる。(中略)白内障の目では景色に青味が失われているのが分かる。」( 「ユニーバーサルデザインにおける色覚バリアーフリーへの提言」(東京大学) 3ページ参照)
「ユニーバーサルデザインにおける色覚バリアーフリーへの提言」(東京大学) 3ページ参照)
睡蓮を200点以上も描いた執念で、モネはバラの小道を何点も描いています。色の識別もままならない中で、描き続けたバラの小道。この作品はジヴェルニーに移住後の充実した日々の中で描かれた透明感溢れる色彩と軽やかな筆触の作品群とは異なり、赤やオレンジ等の暖色系を基調に、ジョルジュ・ルオー作品を想起させるような厚塗りで丹念に色を塗り重ね、重厚感たっぷりに描いています。形態はもはや色の塊として描かれているのみ。目の衰えを補うかのように力強いタッチで描かれた本作にもまた、新たな表現に挑み続けるモネの画家としての執念を感じます。
下の画像は日本で見られるモネの作品で最晩年の作品と言える、アサヒビール大山崎山荘美術館 所蔵の作品《日本の橋》(1918-24)。モネは1926年に86歳で亡くなっているので、亡くなる2年前に完成を見た作品と言えます。
もはや形態は色彩の付属物としてすら感じられる、色彩が主役の作品でしょうか?白内障の手術を受け、色彩を再び取り戻したモネは、再び穏やかな筆致を取り戻し、柔らかな色彩の饗宴で、彼が愛したジヴェルニーの庭にある"日本の橋"を描いたのです。そして間違いなく彼の絵画は、抽象表現への扉を開いたのです。

 「マルモッタン・モネ美術館展公式サイト(東京都美術館)
「マルモッタン・モネ美術館展公式サイト(東京都美術館)
写真は2年前に訪れたジヴェルニーのモネの自宅にある日本庭園。遠くに日本の橋が見えます。こうして見ると、橋に垂れ下がる枝垂れ柳と言い、靄のように橋に覆いかぶさる木々と言い、約100年前の絵と殆ど変わらない光景が目の前に広がっています。
モネの作品を見ると言うことは、モネと言う画家の目を通して、私達はこの世界を見ていると言うことなのです。

4.東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4-3階)特集 藤田嗣治、全所蔵作品展示。

最近は時々一緒にとっておきの映画を見に行く仲でもあるIさんから、企画展チケット『Re:play 1972/2015 「映像表現72」展、再演』をいただいたので、久しぶりに東京国立近代美術館(以下、東近美、竹橋)に、先日行って来ました。
『Re:play 1972/2015 「映像表現72」展、再演』は、その名の通り、1972年に開催された映像展示の再演で、1972年当時の若手の作家らによる最先端の映像作品を、映像機器(←これ自体、骨董的価値あり?)も含めて展示すると言う形の展覧会だったようで、今回は43年後の作家へのインタビュー映像も交えての再演となっています。
前衛アートの映像作品はあまり見る機会がないので、少し戸惑いながらの鑑賞?となりましたが、自分が小学生の頃に作られたらしい、当時としては斬新であったであろう作品を、43年の時を経て見ることの不思議さは、そう簡単には言い表せないものです。再演することの意味も含めて考えながら見る展示と言う感じでした。
しかし、東近美は常設展がとにかく素晴らしく充実しているので、ガイドツアーも含め常設展を先に見て少し疲れていたせいもあり、企画展はサラッと見るに留めました。
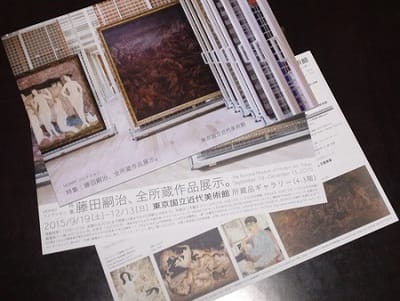
今回、白眉だったのは、何と言っても東近美所蔵の藤田嗣治作品、全25点(+1点は京都国立近代美術館より)を、3、4階のフロア、約1,500㎡を使って一堂に会した特集展示です。
エコール・ド・パリの画家として名を馳せた藤田が、太平洋戦争中に戦争画の大作を多数描いたことは知る人ぞ知る事実ですが、今回の特集では戦後70年を記念して、所蔵する戦争画もすべて展示しています。まだ戦禍に深刻さの見られない初期の明朗な作風から、敗戦の色濃い後期の重苦しい作風までの戦争画が時系列で展示され、その画風の変化が如実に見て取れるだけでなく、戦争画と言うジャンルにおいても、画家として貪欲に絵画表現の追及に注力した藤田の姿勢が、検証資料の展示によって詳らかにされている点が興味深かったです。
今回の特集展示によって、「戦前世界の画壇の中心地であったパリで成功を収めた藤田が、戦争によって帰国を余儀なくされ、軍部の命令によって嫌々戦争画を描かされていた」と言う私の浅はかな思い込みは見事に覆されました。
あの白磁を思わせる乳白色の肌の女性を描いてパリ画壇で認知された彼が、初期の作風はまだしも、中期の国威発揚画や、後期の目を背けたくなるような残酷な修羅場を描いたことに、私はどうしても違和感を禁じえなかった。国民の殆どが同じ方向を向いていた異様な時代の雰囲気の中で、彼も体制に従わずには生きながらえなかったのだと勝手に解釈して、その違和感に無理やり理由づけしていたのです。
しかし、実際の藤田は過去の西洋絵画の名作をも参考にして、戦争の実相(その残酷さを告発すると言うより、純粋に画家として、極限状況の人間の姿を描くことに焦点を当てているように見えた)を描くことに夢中になっていたのです。それは文献資料として遺された彼の発言によっても明らかです。その結果、最後期の作品は狂気さえ帯びて、戦争の残酷さを率直に伝え、見る者を戦慄させる迫力に満ちています。
戦後、その戦争画への積極的な参加により、画家仲間から戦争責任を問われた藤田は逃げるようにパリへと旅立ち、フランスへ帰化してしまいます。
展示室で藤田の全ての作品を見終えてのち、私の目には藤田も、モネや北斎と同じく、描くことに自らの表現の追及に拘り続けた「画狂」に見えました。描きたいと言う欲求(欲望?)の前には遠慮も斟酌もへったくれもない、一人の愚かで、しかし真摯な画家の痕跡が、そこには確かにありました。
 『MOMAT コレクション 特集:藤田嗣治、全所蔵作品展示。』公式サイト
『MOMAT コレクション 特集:藤田嗣治、全所蔵作品展示。』公式サイト
モネが愛したジヴェルニーの自宅のノルマンディー庭園(9月)

順序としては、こちらが一番先に見た展覧会でした。常に美術に関連した有益な情報を発信してくれるHさんのおかげで、前期(9/19~10/18)・後期(10/20~12/13)と2枚のチケットを事前に公式サイトで、かなりお得な価格で入手することが出来ました。この件に関してはHさんに感謝!
なぜ、前期・後期とチケットを販売するのかと言えば、期間限定で展示される作品があるからです。
前期は「印象派」と言うグループの名前の由来にもなった記念碑的作品《日の出、印象》(1872)、後期は《ヨーロッパ橋、サン=ラザール駅》(1877)と、それぞれ期間限定で展示されます。両作品共、門外不出とは言わないまでも、滅多に貸し出されないマルモッタン・モネ美術館が誇るコレクションのひとつと言うことなのでしょうか?
特に《印象、日の出》は実に21年ぶりに東京に来たらしく、マルモッタン・モネ美術館からは貸し出しの条件として、本作品は他の作品とは別区画で単独展示して欲しいと言われたのだとか。

モネ32歳頃の作品で、今見れば何のことはない印象派の作品なのかもしれませんが、発表された当時の画壇では、その曖昧な形態描写と淡い色遣いで「未完成品」扱いされたほど、従来の絵画のセオリーを無視したセンセーショナルな作品でありました。
実際、展示室で目の当たりにしても、薄暗い展示室の照明の下では私の目が悪いせいか、全体的にぼやけて見えました。ネットに上がっている画像群を見ても、かなり色彩の再現にバラツキが見られ、肉眼で見るのとは大きく印象が異なります。それほど繊細な色遣いで描かれた作品と言うことなのでしょう。
おそらく照明によっても見え方がかなり変わるのかもしれません。国立西洋美術館でも、同じ作品が展示替えによって位置を変えただけで、照明の当たり具合(照射される角度)の変化で、思いがけない色が新たに浮かび上がって来たり、細部までクッキリ見えるようになったり、またはその逆だったりと、見え方が大きく変わるぐらいですから。
また、2年前にパリのオルセー美術館で印象派絵画を見た時に感じたことですが、改装工事で壁の色が深い藍色に変わったことで、印象派絵画の色彩が一層光を帯びて華やいで見えたのが印象的でした。特にエドゥアール・マネの《草上の昼食》の美しかったこと!現在、国立西洋美術館のモネの部屋は白一色の壁ですが、これがオルセーと同様に藍色の壁だとしたら、モネの繊細な色遣いの作品群が、どんな風に変わって見えるのだろうと言う興味があります。
《日の出、印象》は既成の価値観に抗い、絵画と言うジャンルに新たな地平を切り開いた作品として、美術史上特筆すべきものですが、個人的に好きか、印象に残るか、と聞かれれば、私は「それほどでも」と答えるでしょう。と言うのも、既に印象派が近代西洋絵画の一ジャンルとして広く認知されているので、その文脈の中では驚きがないからです。
この日の展示室の鑑賞者の反応も、仰々しく列に並んで見た割には特にこれと言った感想はないようで、その価値を分かりかねて戸惑っているようにも見えました。結局、一般の鑑賞者には作品の歴史的価値は事実として理解はできるけれども、鑑賞の楽しみにはあまり関係がないということなのでしょうか?もちろん、美術史をより深く理解したいと言う人には必見の作品ではあります。
 写真は《白いクレマチス》(1887)。モネ47歳頃の作品で、既に創作拠点をパリ郊外のジヴェルニーに移した後に、自邸の庭で描いたものと思われます。
写真は《白いクレマチス》(1887)。モネ47歳頃の作品で、既に創作拠点をパリ郊外のジヴェルニーに移した後に、自邸の庭で描いたものと思われます。キャンバス一面に白と緑を基調に柔らかな筆致で描かれたクレマチス。そのたおやかさに心が癒されます。モネのジヴェルニーにおける幸福で充実した日々が容易に想像できる作品です。
本作品もまた、花のみをキャンバス全体に描いた大胆な構図が従来の花の描き方にはなかった点で、美術史上特筆すべきものであり、後年の、池の輪郭線さえなく、ただ水面に浮かぶ睡蓮と水面に映り込んだ周囲の景色を、色彩の競演(饗宴?)とも言うべき色遣いと、画家の手の動きさえ想像できるような筆触で描いた《睡蓮》の作品群に連なるものと言えます。
今回の展覧会はモネ10代の最初期から80代の最晩年までの作品約90点を展示し、画家モネの生涯に渡る画業の軌跡を辿る構成となっています。これまで日本では何度もモネ展が開催されていますが、これほどまでに全年代の作品を網羅した展覧会は、私が記憶する限り、本展覧会がおそらく初めてと思われます。さすが"モネ"の名を冠している美術館だけのことはあります。見ごたえがあります。
特に印象に残っているのは、モネが白内障を患って以後の最晩年の作品です。日本各地の美術館に数多くのモネの作品が収蔵されていますが、殆どが盛期の作品であり(最晩年の作品と言えるのは国立西洋美術館の《睡蓮》(1916)を含め3点ほど)、今後日本で、これだけの数の最晩年の作品を見られる機会は、もうないかもしれません。その意味でもオススメの展覧会です。
ただし、平日でも入場まで30分待ちが珍しくないほど混雑しています。それでも見る価値のある展覧会だと思います。
 左の画像は《バラの小道 ジヴェルニー》(1920-22)。モネが80~82歳にかけて描いた作品です。
左の画像は《バラの小道 ジヴェルニー》(1920-22)。モネが80~82歳にかけて描いた作品です。60歳の頃から徐々に視力の衰えを感じたモネでしたが、白内障と診断された後も、当時は現在ほど術後の治癒率が高くなく、失明の恐れもあった為、長らく手術を躊躇っていたそうです。
この作品は、白内障を患ったモネが、白内障の影響で色彩の識別も困難な中で描いた作品と言われています。実際、モネの手術前と後の作品を比較して、白内障による色の識別能力の変化について言及した研究報告もあるようです。
「高齢者に多い白内障では、濁った水晶体の中で短波長の光が吸収されてしまうので、赤や緑はよく見えるが、青(などの短波長の色)だけが暗くなって見にくくなる。(中略)白内障の目では景色に青味が失われているのが分かる。」(
睡蓮を200点以上も描いた執念で、モネはバラの小道を何点も描いています。色の識別もままならない中で、描き続けたバラの小道。この作品はジヴェルニーに移住後の充実した日々の中で描かれた透明感溢れる色彩と軽やかな筆触の作品群とは異なり、赤やオレンジ等の暖色系を基調に、ジョルジュ・ルオー作品を想起させるような厚塗りで丹念に色を塗り重ね、重厚感たっぷりに描いています。形態はもはや色の塊として描かれているのみ。目の衰えを補うかのように力強いタッチで描かれた本作にもまた、新たな表現に挑み続けるモネの画家としての執念を感じます。
下の画像は日本で見られるモネの作品で最晩年の作品と言える、アサヒビール大山崎山荘美術館 所蔵の作品《日本の橋》(1918-24)。モネは1926年に86歳で亡くなっているので、亡くなる2年前に完成を見た作品と言えます。
もはや形態は色彩の付属物としてすら感じられる、色彩が主役の作品でしょうか?白内障の手術を受け、色彩を再び取り戻したモネは、再び穏やかな筆致を取り戻し、柔らかな色彩の饗宴で、彼が愛したジヴェルニーの庭にある"日本の橋"を描いたのです。そして間違いなく彼の絵画は、抽象表現への扉を開いたのです。

写真は2年前に訪れたジヴェルニーのモネの自宅にある日本庭園。遠くに日本の橋が見えます。こうして見ると、橋に垂れ下がる枝垂れ柳と言い、靄のように橋に覆いかぶさる木々と言い、約100年前の絵と殆ど変わらない光景が目の前に広がっています。
モネの作品を見ると言うことは、モネと言う画家の目を通して、私達はこの世界を見ていると言うことなのです。

4.東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4-3階)特集 藤田嗣治、全所蔵作品展示。

最近は時々一緒にとっておきの映画を見に行く仲でもあるIさんから、企画展チケット『Re:play 1972/2015 「映像表現72」展、再演』をいただいたので、久しぶりに東京国立近代美術館(以下、東近美、竹橋)に、先日行って来ました。
『Re:play 1972/2015 「映像表現72」展、再演』は、その名の通り、1972年に開催された映像展示の再演で、1972年当時の若手の作家らによる最先端の映像作品を、映像機器(←これ自体、骨董的価値あり?)も含めて展示すると言う形の展覧会だったようで、今回は43年後の作家へのインタビュー映像も交えての再演となっています。
前衛アートの映像作品はあまり見る機会がないので、少し戸惑いながらの鑑賞?となりましたが、自分が小学生の頃に作られたらしい、当時としては斬新であったであろう作品を、43年の時を経て見ることの不思議さは、そう簡単には言い表せないものです。再演することの意味も含めて考えながら見る展示と言う感じでした。
しかし、東近美は常設展がとにかく素晴らしく充実しているので、ガイドツアーも含め常設展を先に見て少し疲れていたせいもあり、企画展はサラッと見るに留めました。
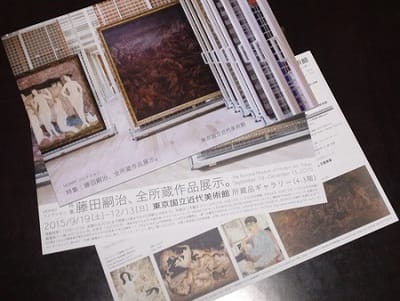
今回、白眉だったのは、何と言っても東近美所蔵の藤田嗣治作品、全25点(+1点は京都国立近代美術館より)を、3、4階のフロア、約1,500㎡を使って一堂に会した特集展示です。
エコール・ド・パリの画家として名を馳せた藤田が、太平洋戦争中に戦争画の大作を多数描いたことは知る人ぞ知る事実ですが、今回の特集では戦後70年を記念して、所蔵する戦争画もすべて展示しています。まだ戦禍に深刻さの見られない初期の明朗な作風から、敗戦の色濃い後期の重苦しい作風までの戦争画が時系列で展示され、その画風の変化が如実に見て取れるだけでなく、戦争画と言うジャンルにおいても、画家として貪欲に絵画表現の追及に注力した藤田の姿勢が、検証資料の展示によって詳らかにされている点が興味深かったです。
今回の特集展示によって、「戦前世界の画壇の中心地であったパリで成功を収めた藤田が、戦争によって帰国を余儀なくされ、軍部の命令によって嫌々戦争画を描かされていた」と言う私の浅はかな思い込みは見事に覆されました。
あの白磁を思わせる乳白色の肌の女性を描いてパリ画壇で認知された彼が、初期の作風はまだしも、中期の国威発揚画や、後期の目を背けたくなるような残酷な修羅場を描いたことに、私はどうしても違和感を禁じえなかった。国民の殆どが同じ方向を向いていた異様な時代の雰囲気の中で、彼も体制に従わずには生きながらえなかったのだと勝手に解釈して、その違和感に無理やり理由づけしていたのです。
しかし、実際の藤田は過去の西洋絵画の名作をも参考にして、戦争の実相(その残酷さを告発すると言うより、純粋に画家として、極限状況の人間の姿を描くことに焦点を当てているように見えた)を描くことに夢中になっていたのです。それは文献資料として遺された彼の発言によっても明らかです。その結果、最後期の作品は狂気さえ帯びて、戦争の残酷さを率直に伝え、見る者を戦慄させる迫力に満ちています。
戦後、その戦争画への積極的な参加により、画家仲間から戦争責任を問われた藤田は逃げるようにパリへと旅立ち、フランスへ帰化してしまいます。
展示室で藤田の全ての作品を見終えてのち、私の目には藤田も、モネや北斎と同じく、描くことに自らの表現の追及に拘り続けた「画狂」に見えました。描きたいと言う欲求(欲望?)の前には遠慮も斟酌もへったくれもない、一人の愚かで、しかし真摯な画家の痕跡が、そこには確かにありました。
モネが愛したジヴェルニーの自宅のノルマンディー庭園(9月)


























