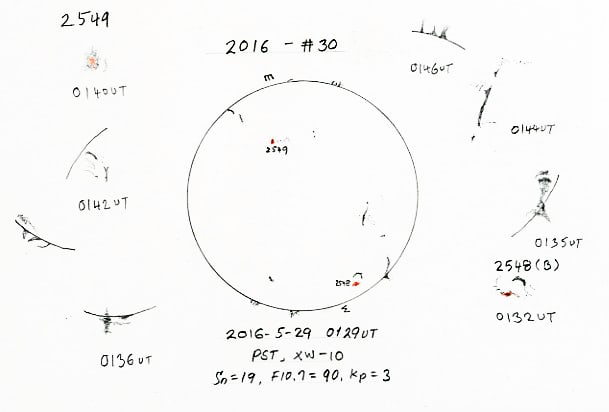以前から7MHzのEFHWアンテナを自宅に上げてある。このアンテナはなかなか性能が良くて国内の交信なら多少のパイルでもとってもらえることもある。国内コンテストで最近入賞したのもの7MHzのQRP部門だった。このアンテナは、リグがある場所からだいぶ離れているので、同軸ケーブルをずっと地面に這わせてある。もしかすると、このケーブルのシールドと地面との容量結合によってカウンターポイズの働きをしているような気もする。
これに対して、最近作った14から24MHzのEFHWは、何とか海外へも電波は飛ぶものの、反応が悪い。時々SWRが低くならなくなったりして、動作が不安定になることもある。QRPはアンテナが命である。このアンテナちょっといまいちな気がする。今参戦中のCQ WW WPXコンテストも結局ほとんどが7MHzのWの局ばかり、21MHzと14MHzはちょっとしかつながらなかった。
ということで、6mでは性能を確認したデルタループを作ってみた。長さは一波長で、周波数は18から24MHzとして、ギボシを使って周波数を変えられるようにしてある。ネットで調べると、デルタ部分の角度でインピーダンスはいろいろ変わるらしい。山の上ではエレメントの展開できる場所が限られているので、アンテナチューナーでインピーダンスの変化は吸収することとした。一応物はできたので、来週あたり試してみるかな。