
【命題】
乳幼児期から感音性難聴でしかも進行性で、親、家族、教師、学友の声が聞こえないまま学童期、青年期を過ごしてきた。
このことは、人格形成に大きな影響を与えるという。
【推理】
なぜか。
人との会話は、相手との人間関係も含めて、豊かな内容を持つので、その有無や量、質ともに人格形成に大きな影響を与える。
この時期に生きた会話が脳にインプットされていなかったということは言葉や知識の蓄積もさることながら、感情や感性の発達、思考の訓練が出来ていなかったことになる。
言葉を受け取った時に、そのメッセージは意味の伝達だから、メッセージの意味理解を通じて、自身の中に思考が生じる。
自身の中に新たな理解や知識が追加されることで脳細胞は興奮する。喜怒哀楽につながる。
【検証】
乳児期に高熱が元で難聴になり、学童期にタ行、サ行の発音が不明瞭だったということはその頃までも難聴だったことが伺われる。これは感音性の難聴だ。
親や兄弟の語りかけもほとんど理解できていなかったのではないか。補聴器をしていた時でも隣で交わされている会話が分からないということは、聴力が今より良かったとしても感音性の難聴であれば虫食い状態にしか聞こえていなかったはずだ。
確かに親や兄弟、親戚、教師、学友の顔は思い浮かべても声や言葉がまるで浮かばない。
いわゆる心に響く言葉を聞いた記憶がない、人に何か言われて怒ったり、喜んだりした経験はほとんどない。
(続く)
ラビット 記
乳幼児期から感音性難聴でしかも進行性で、親、家族、教師、学友の声が聞こえないまま学童期、青年期を過ごしてきた。
このことは、人格形成に大きな影響を与えるという。
【推理】
なぜか。
人との会話は、相手との人間関係も含めて、豊かな内容を持つので、その有無や量、質ともに人格形成に大きな影響を与える。
この時期に生きた会話が脳にインプットされていなかったということは言葉や知識の蓄積もさることながら、感情や感性の発達、思考の訓練が出来ていなかったことになる。
言葉を受け取った時に、そのメッセージは意味の伝達だから、メッセージの意味理解を通じて、自身の中に思考が生じる。
自身の中に新たな理解や知識が追加されることで脳細胞は興奮する。喜怒哀楽につながる。
【検証】
乳児期に高熱が元で難聴になり、学童期にタ行、サ行の発音が不明瞭だったということはその頃までも難聴だったことが伺われる。これは感音性の難聴だ。
親や兄弟の語りかけもほとんど理解できていなかったのではないか。補聴器をしていた時でも隣で交わされている会話が分からないということは、聴力が今より良かったとしても感音性の難聴であれば虫食い状態にしか聞こえていなかったはずだ。
確かに親や兄弟、親戚、教師、学友の顔は思い浮かべても声や言葉がまるで浮かばない。
いわゆる心に響く言葉を聞いた記憶がない、人に何か言われて怒ったり、喜んだりした経験はほとんどない。
(続く)
ラビット 記










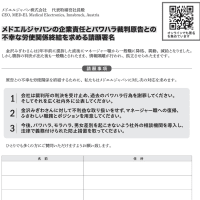

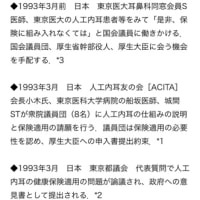






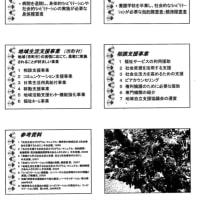

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます