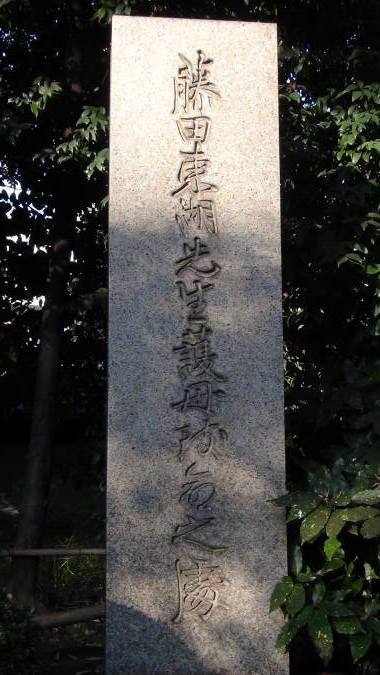この11月20日累計歩行数が4万kmとなり、
地球一周を完了し、今二周目に挑戦している。
思えば、血液のがんの治療をして、
抗がん剤の副作用を抑える薬の副作用で、
もともと予備軍であった糖尿病が顕在化して、
インスリンを注射するようになってから、
毎日欠かさず朝食後と昼食後に約8000歩、
一日で1万6千歩を歩いた記録の累計距離である。
2009年9月より、毎日の歩行数をPCに記録して置いた。
一歩を60cmで換算し歩行距離が累計4万kmになった。
ボクの歩きの一歩は、70cmあるが、
疲れた時、階段を昇り降りするときも入れると、
平均しておよそ60cmと換算しての距離だ。
実に7年と2か月かかっている。
お陰で大した病気もせずに過ごすことが出来た。
この後も歩くことを励行し、健康を保ち、
世の中の移り変わりの状況を眺めて行きたいものである。
地球一周を完了し、今二周目に挑戦している。
思えば、血液のがんの治療をして、
抗がん剤の副作用を抑える薬の副作用で、
もともと予備軍であった糖尿病が顕在化して、
インスリンを注射するようになってから、
毎日欠かさず朝食後と昼食後に約8000歩、
一日で1万6千歩を歩いた記録の累計距離である。
2009年9月より、毎日の歩行数をPCに記録して置いた。
一歩を60cmで換算し歩行距離が累計4万kmになった。
ボクの歩きの一歩は、70cmあるが、
疲れた時、階段を昇り降りするときも入れると、
平均しておよそ60cmと換算しての距離だ。
実に7年と2か月かかっている。
お陰で大した病気もせずに過ごすことが出来た。
この後も歩くことを励行し、健康を保ち、
世の中の移り変わりの状況を眺めて行きたいものである。