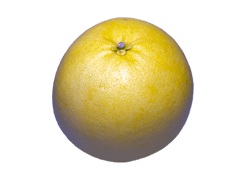昨晩13日午後8時半頃に修二会が行われている東大寺二月堂へ
御香水を授かりに行ってきました。
午後7時からのおたいまつの後なので、帰る人とすれちがいましたが、
夜のとばりの中に二月堂がひっそりとたたずんでいました。

二月堂から奈良市内を眺めれば、東大寺大仏殿も夜の闇の中に

一般の人が御堂の中にはいれるのは、南、西、北面ですが、
御香水を授かれるのは西面だけなので、
その重い木の扉を開けると、人人で座れるところは少なく、
静寂の中すみませんと小声で御願いして、
少しだけあいている場所に座ることができました。
練行衆の読経が耳の中に・・・・・
足が痛い、正座はつらく、胡坐や体育館座りをする。行儀が悪いが!
五体投地のあの音、聞くだけでも痛そう。でも人により音が違います。
走りの行で木のさしかけ(沓)をはいて内陣を駆け回っておられたのが、
内陣に松明が回り、素足での静かな走り行の合間にも五体投地もあり、その後
昨夜のお水取の行で、須弥壇下の香水壺に蓄えられていた香水が、
一般のひとにも、授けられました。
格子戸の中に皆がそれぞれに手を突出し、その手の内に、少量ですが分け与えていただきました。
口に含ませていただくと、何とも言えない気持ちになり、残りを顔に擦り込みました。
ネットで検索しましたが、
”御香水は走りの行法のあと、練行衆に喉の渇きを癒すものとして授与され、お相伴として参詣者にも振る舞われるのです。観音の霊力のこもった霊水として、信者さんたちには大変に貴重なものだそうです。”
その後、韃靼の行が行われるのですが、11時40分、あきらめて早々に家路につきました。
東大寺のホームページからの引用ですが、
修二会とは
「十一面悔過(じゅういちめんけか)」といい、十一面観世音菩薩(じゅういちめんかんぜおんぼさつ)を本尊とし、「天下泰平(てんかたいへい)」「五穀豊穣(ごこくほうじょう)」「万民快楽(ばんみんけらく)」などを願って祈りを捧げ、人々に代わって懺悔(さんげ)の行を勤めるものです。
本行の行法
おたいまつに伴われて、練行衆が上堂すると、初夜の行法としてまず「読経(法華音曲)」、初夜の「時」、「神名帳」、 「初夜大導師の祈り」、「初夜咒師作法」があり、引き続いて半夜の「時」、禮堂に出ての「法華懺法」が行われます。 ただし、五、六、七日及び十二、十三、十四日には「法華懺法」のかわりに「走り」が行われます。後夜になると後夜読経、後夜の「時」、「後夜大導師の祈り」、「後夜咒師作法」、さらに 晨朝の「時」が勤められ、その後童子の手松明の明かりを頼りに下堂して就寝します。下堂する時間は、日によりますが、午前一時から午前四時半頃までの間となります。
なお13日は後夜咒師作法の後に「達陀」が行われます。