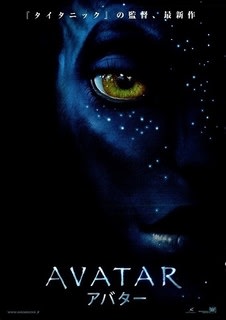武将ジャパン2022/11/08
序盤は純朴な好青年だった。
それが源頼朝の過酷な政治スタンスを目の当たりにするうちに心は灰色になり、父の北条時政を追放した頃には、ついには自身が真っ黒に。
2022年大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の主人公・北条義時の豹変ぶりに、ふと、こんなことを考えたりもしませんか?
なぜ義時が主役になったのだろう――。
例えば立身出世という明快なストーリーを望むのであれば、彼は選ばれなかったはず。
ならばNHKの狙いは何なのか?というと、キャッチコピーに現れている気もします。
三谷幸喜が贈る予測不能エンターテインメント!
確かに、鎌倉殿の13人の主人公が発表された時点で、
「えっ?北条義時って???」
と違和感あるいは驚きを抱かれた方も多かったでしょう。
源頼朝や北条政子ならまだしも、二代目執権・義時とは、まさしく予測不能――。
前半生は「何もしない人」と揶揄されるほど影が薄く、表舞台に立ち始める頃には陰謀の渦中にいて、何度も結婚を繰り返す。
英雄と持ち上げるには黒すぎて、しかも平安末期から鎌倉時代など視聴率だって望めなさそうだ。
やはり大河ドラマの主人公に適していない人物では?
実際、そんな意見も多くあったようですが、あらためて考えてみたいのがこれ。
「そもそも大河の主人公はどういう基準で決めるられるのか?」
そんなもん、歴史の有名人に決まってるだろ……とは言い切れないのが大河の歴史。
義時が主役となるにまで進んだ、NHKの紆余曲折を振り返ってみましょう。
大河ドラマは第一作の時点で意外な主人公
いったい大河ドラマらしい主人公とは何なのか?
このテーマを考えていく上で無視できないのが“時代”というものでしょう。
昭和に始まり平成を経て、令和へ。
作品が、その時勢に影響されるのは当然のことであり、例えば第一作から見てみると、現在ではまず取り上げられないだろう主人公も中にはいます。
1963年『花の生涯』
1964年『赤穂浪士』
1965年『太閤記』
1966年『源義経』
1967年『三姉妹』
【参照】大河60(→link)
第2作の『赤穂浪士』ですね。
忠臣蔵が最後に取り上げられたのは1999年『元禄繚乱』ですが、以降、『忠臣蔵』そのものの人気と知名度が急低下し、仮に今「再来年は忠臣蔵を!」とNHKに意気揚々とされても、しらけてしまう視聴者のほうが多いでしょう。
かつての同作品は「自らの身を犠牲にしても主君の仇を討つ」という精神性に魂を揺さぶられる風潮はあったかもしれません。
しかし今では「逆恨みで吉良上野介に襲いかかるのって、単なるテロ行為ではないか?」という指摘もあり、赤穂浪士にシンパシーを感じる視聴者が減っている可能性は低くありません。
そもそも第1作『花の生涯』からして、なかなか振り切った人選です。
主人公は井伊直弼――【桜田門外の変】という暗殺で大河の最終回を迎えるなんて、今となっては驚異的な選択でしょう。
こうして見ていくと大河ドラマの始まりと、61作目ともなる現在では、何かが違うことが浮かび上がってくるのです。
【皇国史観】との訣別
第一作で井伊直弼が主人公に選ばれたことが悪いと言いたいわけではありません。
むしろ非常に画期的でした。
というのも井伊直弼は、長州閥からすると吉田松陰を刑死に追いやった不倶戴天であり、いわば宿敵です。
さらに薩摩閥からすれば、桜田門外の変に薩摩藩士が積極的に関わっているため、直弼が単純な悪党であると世間に見られていた方が都合がよろしい。
明治維新後、薩長による藩閥政治が幅を利かせ、現代においても影響力が残っているとすれば、そこに忖度の論理が働く。
井伊直弼の暗殺を討幕へつながる快事としたい権力層。
いや、そうではないと反論したい佐幕派の子孫たち。
そんな歴史観の駆け引きがあり、井伊直弼を主人公とするのは非常にナーバスなものだったのです。
今では大人気の新選組ですら、長いこと悪役が定番でした。
変革が起きたのが戦後です。
戦前は、天皇に忠義を尽くした武士が称賛され、権力を握っていた幕府は悪者となり、幕藩体制をひっくり返した明治維新はともかく素晴らしい、民草に歴史はなく国家のために命を尽くすべし――そんな驚くべき思想も普遍化していました。
皇国史観を掲げた研究者の代表格・平泉澄の「豚に歴史はありますか?」という言葉はその象徴でしょう。
しかし敗戦を経て価値観の激変が起き、歴史作品においても過去の歴史観への克服が課題となりました。
要は大河ドラマは【皇国史観】からの決別が意識されていた――そう見なせるのが『花の生涯』と『三姉妹』でしょう。
明治維新へ続く重要なステップであった【桜田門外ノ変】を再検証した『花の生涯』。
明治維新のために人生を踏み躙られた姉妹の、声なき声を描いた『三姉妹』。
両作品には【皇国史観】へのアンチテーゼがあります。
大河ドラマだけではありません。
当時のこうした価値観は他の時代劇にも反映されています。
・上からの命令に絶対服従させられる理不尽さ
・人命を軽視する国家権力
・美化される武士道と死の酷い現実
軍国主義の暴走によって死地を彷徨った戦争体験者にとって、こうした辛さは身近なものであり、彼らが描く批判精神は多くの日本人にとって苦く、同時に現実のものでした。
武士道そのものを“悪”としたいわけではありません。
それを無理に拡大解釈した結果、あまりにも多くの方が亡くなってしまう暴走行為を戦後の制作者たちは批判していたのです。
こうした作品のうち、知名度が高く、現在でも手に取りやすい作品を挙げておきます。
・映画およびリメイク版テレビドラマ『柳生一族の陰謀』
・映画およびリメイク版テレビドラマ『十三人の刺客』
・原作『駿河城御前試合』および漫画版『シグルイ』
・原作および漫画、映画版など『魔界転生』
根付かない【野史】目線
【皇国史観】の後、歴史学で広がったのが【マルクス主義史観】です。
学術的な用語解説は長くなりますので、大河の歴史をふまえつつ、簡単にさわりだけ説明させていただきますと……。
【マルクス主義史観】とは庶民や労働者こそが時代を動かすという歴史観。前述の言葉「豚に歴史はありますか?」の真逆ですね。
非常に画期的であり、見るべきこともありますが、何事も行き過ぎはよくありません。
たとえば【島原の乱】を労働者の革命として持ち上げすぎたため、宗教色を軽視しするような弊害が生じました。
また、マルクスという語感からして、いかにも西洋主導で生まれたようにも思えますが、そう単純な話でもありません。
【正史】に対する【野史】や【稗史(はいし)】という概念が古くからあります。
為政者ではなく、民間伝承やその歴史をまとめたものです。
大河ドラマでいえば前述の『三姉妹』は、歴史に名を残さない三姉妹が主人公であり、こうした系統の作品といえるでしょう。
しかし、視聴率が伸び悩むという欠点があり、1980年『獅子の時代』を最後に、この手の架空人物、野史目線の大河はなくなりました。
それから40年以上も経過し、深刻な弊害が大河に生じます。
2020年『麒麟がくる』に登場したキャラクターの「駒」や「東庵」。
彼らは実在しない人物であり、一部の視聴者から「ファンタジーはいい加減にしろ!」という激しいバッシングの対象となったのです。
その理屈でいきますと、第5作『三姉妹』の主人公も実在した人物ではないため、作品の内容に関係なく批判の対象となってしまいます。
問題は、駒や東庵など、声なき声を表現する立場の者たちを否定してしまうことでしょう。それこそ「豚に歴史はありますか?」という言葉の既視感が滲んできたものです。
たとえ架空の人物であろうと、時代背景を反映した描写はできます。
むしろ歴史フィクションの定番技法です。
にもかかわらず、それが否定されるとあっては、野史アレルギーのような、危うい何かを感じてしまいます。
かつて日本には、大河ドラマ以外にも数多の時代劇がありました。
そこでは無名で歴史に登場などしない、庶民の暮らしや娯楽が描かれたり、小悪党が登場したり。
架空キャラがテレビ画面に氾濫していましたが、令和の時代となるとほとんど見かけません。
野史を認めず、正史しか存在しない歴史エンタメなど、他の時代や国と比較しても異常です。
一事が万事そうとは言いませんが、日本社会が極めて余裕を無くし、堅苦しい状況に陥っているんじゃないか、と、不安が尽きないほど。
中央の為政者だけを描く思考に偏ると、庶民だけでなく、琉球やアイヌの歴史を取りこぼすことにもなってしまいます。
沖縄が舞台の大河は1993年半年枠『琉球の風』のみで、北海道舞台の大河はまだ存在せず。
現在、歴史に対する世界の見方は変わっています。
先住民はじめマイノリティ目線で描くことが重要視されるようになり、例えばNHKでも放映されたドラマ『アンという名の少女』では、原作『赤毛のアン』にはなかった先住民目線のカナダ史が取り上げられました。
大河でもそうした見方を取り入れていかねば、海外から取り残されてしまうのではないでしょうか。
近代史は鬼門
他にも大河に根付かなかったジャンルはあります。
近代ものです。
1984年『山河燃ゆ』
1985年『春の波濤』
1986年『いのち』
明治時代から第二次世界大戦後という時系列を描いたこの三部作は視聴率が低迷。
1987年『独眼竜政宗』が記録的大ヒットをしたこともあり、以降、近代史は避けられるようになりました。
時代ものは大河で、近代史ものは朝ドラで――いつしかそんな棲み分けが進んでいくのです。
東京オリンピックに合わせて放映された2019年『いだてん』は、そのルールを破りましたが、視聴率は記録的な低水準に陥り、再び近代史はタブーであると印象付けてしまいました。
その影響もあってか、2021年『青天を衝け』は、幕末パートが非常に長い。
主人公の渋沢栄一は幕臣時代の活躍はあまりなく、主な活躍は明治以降です。
渋沢を描くなら経済活動に重きを置くのがドラマの魅力のはずですが、幕末時代を引っ張るためか、劇中では徳川慶喜との交流にかなり時間が割かれました。当時の慶喜と渋沢はそこまで懇意ではありません。
明治をさしおき幕末を引き伸ばす。
渋沢とほとんど接点がない新選組までクローズアップする。
その描き方からは、なんとしても話題性と視聴率を得たいという苦労がうかがえたものです。
【近代史】が避けられる理由としては、視聴率以外の問題もあります。
江戸時代以前であれば、歴史と政治は断絶が入ります。
しかし、明治時代以降はそうはいきません。国境を越えた影響などもより濃くなる。
2019年『いだてん』はオリンピックがテーマでしたが、政治および経済と密接な関係にあることはよく指摘されます。
あのドラマでは、自分の祖父がでたと政治家がSNSで表明することもありました。
経済効果についても、広く日本社会に行き渡るのであれば何ら問題ありませんが、口利きによる逮捕劇が続く現状を考えれば、綺麗事ばかりでないことも間違いないでしょう。
公共放送で特定の権力の宣伝につながりかねない描写をしてもよいものかどうか――近代史以降の作品には常にこの問題がつきまといます。
慎重にならざるを得ないのです。
原点回帰か? 革新か?
重ねて申し上げますが、大河ドラマは【皇国史観】の見直しともいえる井伊直弼から始まりました。
その流れも時代と共に変化。
高度経済成長期を迎えると、大河は当初あった革新的なテーマではなく、むしろ豪華キャストとセットをアピールするものとなります。
明るい題材で一国一城の主になるような立身出世劇。
司馬遼太郎に始まり、吉川英治、山岡荘八といったおなじみの作家の時代が訪れます。
しかし、バブルが弾け“失われた30年”も経験すると、その状況も変わり、敗者や悪役だった側の言い分も取り上げられるようになります。
2004年『新選組!』は国会で「あんな維新志士を殺した連中を大河にするのか」という旨の抗議がありました。
2012年『平清盛』は、源平合戦の負ける側。
2013年『八重の桜』は“朝敵”会津藩の言い分を描いています。
日本で最も人気が高いとされる戦国武将・真田幸村が2016年『真田丸』まで主役になれなかったのは「討死という暗い終わり方がウケないからだ」とされていましたが、彼もついに登場しました。
女性城主をとりあげた2017年『おんな城主 直虎』では、良妻賢母以外の女性像を鮮やかに描き、奸臣とされた小野政次の描き方も斬新。
こうして見ていくと、なかなか進歩しているようで、実際は迷走作品もあります。
例えば【皇国史観】では神聖視されていた吉田松陰。
2015年『花燃ゆ』では、あまりに脳天気に扱われました。
知名度が低い松陰の妹・杉文がヒロインであり、松下村塾がまるで部活動のようなゆるいノリで描かれたのです。
松下村塾は大河ドラマの題材に向いているとは思います。
しかし、あんなテロリストサークル活動を明るく描く大河は、いったい何のニーズだったのか?と謎は深まるばかり。
松下村塾が時に暗殺謀議もするほどの危険性があったからといって、ここまでごまかせるものだろうか?
そう疑念を抱いた視聴者から、ヒロインは「テロサーの姫(テロリストサークルでちやほやされる女性メンバー)」とあだ名をつけられていたほど。
2018年『西郷どん』も、日本史上において二度の内戦(戊辰戦争と西南戦争)を引き起こした西郷隆盛を、これまたあっけらかんと能天気に描いていました。
トランポリンの上で弾むメインビジュアルからして、何がしたいのか理解しがたいものがあります。明治維新とフランス革命を関連づけるにせよ、あまりに雑でした。
そして2021年『青天を衝け』は、さらに踏み込んできます。
【皇国史観】の思想的原点として、幕末の志士が信奉していた【水戸学】があります。
平泉澄も【水戸学】を研究していましたが、【皇国史観】と共に【水戸学】も忘れ去られてゆきます。
1970年に衝撃的な事件を起こし自決した三島由紀夫が熱心な信奉者だったこともあり、肯定的な評価はありませんでした。
しかし、です。
2021年『青天を衝け』では、主人公である渋沢栄一が【水戸学】信奉者だったためか、思想の中身を簡略化したうえで肯定的に扱うことに……。
かなり問題のある人物であり、【水戸学】インフルエンサーであった徳川斉昭と藤田東湖も好人物として登場していました。
【水戸学】信奉者が引き起こした惨劇である【天狗党の乱】も、残酷な要素を最小限にとどめ、かつ青年らしい愛国心の暴発程度とされています。
皇国史観】の克服から始まったであろう大河ドラマが、気づいたら【水戸学】を肯定している。
それだけではありません。
記念すべき大河ドラマ第一作主役であった井伊直弼を、研究結果を無視してまで矮小に描く。
「茶歌ポン」という悪意あるあだ名を大仰に扱う。
討った側に共感させるように演出する。
これは一体どうしたことなのか……。
大河ドラマは一周退化したと感じさせる描き方でした。
そして北条義時だ
こうした歴史観の変化を踏まえた上で、あらためて北条義時という主役を考えてみます。
彼は【皇国史観】では悪役。
【承久の乱】で後鳥羽院に勝利し、流刑にしたのですから、まさに逆臣中の逆臣です。
しかし逆臣を扱った大河に、先例がないわけではありません。
1991年『太平記』でも、逆臣の代表格である足利尊氏が主役でした。
武士と天皇の関係性という意味では、『太平記』と同じ脚本家である池端俊策氏の2020年『麒麟がくる』も興味深い関係性がみられます。
明智光秀は織田信長を打ち果たした逆賊です。
では【皇国史観】から見た場合の光秀は?
これは織田信長の評価に依存するでしょう。
信長は逆臣である足利義昭を追放した。
ただし、正親町天皇を崇拝していた勤皇の志があったのか、それとも天皇に取って代わろうとしていたのか?
見方は分かれますが、池端氏は「正親町天皇が信長を疎んじていた」という解釈でドラマを書いていました。
それでも光秀が信長を討った理由は、正親町天皇を救うためだったとはされていません。
勤皇を動機にしないところに、池端俊策氏なりの解釈と、発表当時の歴史観が見てとれます。
では『鎌倉殿の13人』は?
オープニングの時点で「武士が後鳥羽院と戦う」とハッキリ示されています。
逆賊として立ち向かう様子を最初から示しているのです。
こうも難しい題材は、三作目である三谷幸喜さんでなければ書ききれないでしょう。
幕末史ほどデリケートでないものの、2020年代に逆賊を主役に据える――相当の覚悟と気合を感じます。
つまり大河ドラマの歴史は一周回って、また別の展開を見せているのでしょう。
2023年『どうする家康』については、明治政府がこれでもかと過小評価してきた徳川家康が主役です。
2024年『光る君へ』の紫式部はどうか?
実は『源氏物語』は【皇国史観】からすると「皇室を題材に猥褻な描写をした」として、発禁にされるほどでした。
大河ドラマに政治を持ち込むな。
エンタメに政治を持ち込むな。
そうした意見はよく聞かれますが、いくら遠ざけようとしてもどこかに必ず繋がりがあり、ましてや為政者を描くとなれば政治を完全に遮断するのは不可能なこと。
『鎌倉殿の13人』の脚本家である三谷幸喜さんは、『新選組!』が政治家に問題視されたことを振り返っています。
偏った思想におもねるではなく、人は常に進歩していける――大げさかもしれませんが、だからこそ大河ドラマには、そんな役割も期待したくなるのです。
【参考文献】
本郷和人『歴史学者という病』(→amazon)
一坂太郎/星亮一『大河ドラマと日本人』(→amazon)
斎藤貴男『「明治礼賛」の正体』(→amazon)
他
https://bushoojapan.com/taiga/kamakura13/2022/11/08/171946