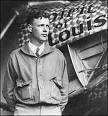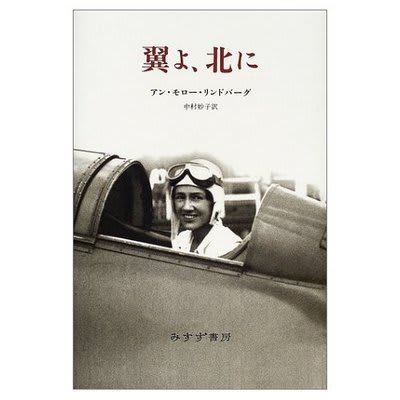The most certain test by which we judge whether a country is really free is the amount of security enjoyed by minorities. Liberty, by this definition, is the essential condition and guardian of Religion;
- Lord Acton
ある国家が真に自由であるかどうかの確実な試薬は少数者が享受する安全の量にある。この定義によれば、自由は宗教の基本的な条件であり保護者である・・
- アクトン卿
これは、アクトンが1887年の2月に行ったu演の一部。「権力は腐敗する・・・」と看破したこの人物については、少なからぬ思い入れがあるので、この“The History of Freedom in Antiquity"の講演を全部、 仮題『古代の自由史』として末オてみることにした。
訳を進めるに連れて自らの教養・素養の無さを痛感してはいるが、これはいつものことなのでどういうことはない。同時進行で勉強をすればよいだけのことだ。
しかし、ほんとうに西欧を知るにはどうしてもラテン語・ギリシャ語の世界に多少は脚を突っ込む必要がある。加藤周一は電車の中でラテン語をマスターしたらしい。有限の人生、限られた時間でどこまでできるか分からんけど、これもちょっと楽しみながらやってみようか・・・と思っているところ。
私の青春前期はこの人の影響が大きい。

- Lord Acton
ある国家が真に自由であるかどうかの確実な試薬は少数者が享受する安全の量にある。この定義によれば、自由は宗教の基本的な条件であり保護者である・・
- アクトン卿
これは、アクトンが1887年の2月に行ったu演の一部。「権力は腐敗する・・・」と看破したこの人物については、少なからぬ思い入れがあるので、この“The History of Freedom in Antiquity"の講演を全部、 仮題『古代の自由史』として末オてみることにした。
訳を進めるに連れて自らの教養・素養の無さを痛感してはいるが、これはいつものことなのでどういうことはない。同時進行で勉強をすればよいだけのことだ。
しかし、ほんとうに西欧を知るにはどうしてもラテン語・ギリシャ語の世界に多少は脚を突っ込む必要がある。加藤周一は電車の中でラテン語をマスターしたらしい。有限の人生、限られた時間でどこまでできるか分からんけど、これもちょっと楽しみながらやってみようか・・・と思っているところ。
私の青春前期はこの人の影響が大きい。