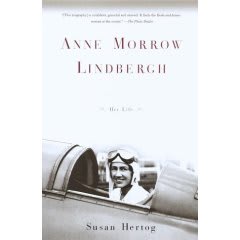飛行の意味をどう捉えるかにもよるが、ジャンプの歴史は少なくとも“近代における”飛行の歴史よりはるかに古い。
紀元前2200年の昔、舜帝(※注)は巨大な麦わら帽子2個の助けを借りて炎上する塔から脱出し、領地の上空を飛んだという。ただ、麦わら帽子は私もよくかぶるし大きいものは1m近くもあるが、こんなものをいくら集めてもパラシュートの用は成さないだろうから、これは神話・伝説の域を超えない。
※舜帝(しゅんてい・中国古代の伝説上の聖天子。尭(ぎょう)と並称して「尭舜(ぎょうしゅん)」という)
しかし、852年、スペインのアーメン・ファーマンが巨大な外套を着て高い塔から跳んで大怪我をしたという話は本当だろうし、その後多くの“向こう見ず”が、両腕に様々な素材でできた羽のようなものを付けて高い所から跳んだことも事実だろう。
かく言う私も、小さい頃にこの種のジャンプを試みた一人だ。私の生家は小さな漁村にあり、目の前がすぐ砂浜になっていた。現在のように冷凍技術が進んでいなかったので、漁師たちが獲ってきた魚は市場に出す前に海中に浮かべた直方体の“生けす”に入れておく。私たちはこれを“ダンベ”と呼んでいたが、用済みのダンベは無造作に浜に並べてあった。これが結構大きなもので、横に立てると4mほどの高さになる。
この上から傘をさして跳ぶのである。下は砂浜だから怪我をすることはない。随分長い間飽きることもなく、このダンベからの傘さしジャンプで遊んだものだが、結局この程度のパラシュートでは落下速度はほとんど減衰されないということがよく分かった。
さて、1797年、史上初と記録に残るフランスのガーネリンのジャンプはもちろんこんな遊びではない。水素気球で一気に2000mまで上がり、そこからバスケットごと落下するというものだ。

その名も「大きな傘」。ベントホールが無いので乱流でキャノピーはかなり暴れまわったらしいが、出発地点から1km足らずの地点に無事着地したというから凄い。とんでもない勇気と幸運だ。
しかし、私の興味はそれだけではない。フランス軍に従軍する前に物理学を学んだ彼がパラシュートジャンプに情熱を注ぐようになった切っ鰍ッが「フランス革命」にあり、敵軍の捕虜になって3年間捕らわれていたハンガリーの牢獄から脱出するために、その構想に没頭したという事実である。これは、ミノス王の追っ手から逃れるために、クレタ島の断崖から飛んだというダエダロス・イカロスの伝説に通じるものがあるだろう。
地上は王の領地つまり隷従を強いる領域、大空は神の世界つまり自由の領域・・・という考え方が、長い歴史を通じて人間の心理の深層に横たわっていることは否定できないように思える。
紀元前2200年の昔、舜帝(※注)は巨大な麦わら帽子2個の助けを借りて炎上する塔から脱出し、領地の上空を飛んだという。ただ、麦わら帽子は私もよくかぶるし大きいものは1m近くもあるが、こんなものをいくら集めてもパラシュートの用は成さないだろうから、これは神話・伝説の域を超えない。
※舜帝(しゅんてい・中国古代の伝説上の聖天子。尭(ぎょう)と並称して「尭舜(ぎょうしゅん)」という)
しかし、852年、スペインのアーメン・ファーマンが巨大な外套を着て高い塔から跳んで大怪我をしたという話は本当だろうし、その後多くの“向こう見ず”が、両腕に様々な素材でできた羽のようなものを付けて高い所から跳んだことも事実だろう。
かく言う私も、小さい頃にこの種のジャンプを試みた一人だ。私の生家は小さな漁村にあり、目の前がすぐ砂浜になっていた。現在のように冷凍技術が進んでいなかったので、漁師たちが獲ってきた魚は市場に出す前に海中に浮かべた直方体の“生けす”に入れておく。私たちはこれを“ダンベ”と呼んでいたが、用済みのダンベは無造作に浜に並べてあった。これが結構大きなもので、横に立てると4mほどの高さになる。
この上から傘をさして跳ぶのである。下は砂浜だから怪我をすることはない。随分長い間飽きることもなく、このダンベからの傘さしジャンプで遊んだものだが、結局この程度のパラシュートでは落下速度はほとんど減衰されないということがよく分かった。
さて、1797年、史上初と記録に残るフランスのガーネリンのジャンプはもちろんこんな遊びではない。水素気球で一気に2000mまで上がり、そこからバスケットごと落下するというものだ。

その名も「大きな傘」。ベントホールが無いので乱流でキャノピーはかなり暴れまわったらしいが、出発地点から1km足らずの地点に無事着地したというから凄い。とんでもない勇気と幸運だ。
しかし、私の興味はそれだけではない。フランス軍に従軍する前に物理学を学んだ彼がパラシュートジャンプに情熱を注ぐようになった切っ鰍ッが「フランス革命」にあり、敵軍の捕虜になって3年間捕らわれていたハンガリーの牢獄から脱出するために、その構想に没頭したという事実である。これは、ミノス王の追っ手から逃れるために、クレタ島の断崖から飛んだというダエダロス・イカロスの伝説に通じるものがあるだろう。
地上は王の領地つまり隷従を強いる領域、大空は神の世界つまり自由の領域・・・という考え方が、長い歴史を通じて人間の心理の深層に横たわっていることは否定できないように思える。