旧制今治中学校を前身とする愛媛県立・今治西高等学校は、港湾を東向きに開く旧今治市の北西部に位置する。一学年450名、全校生徒数1350名のありふれた進学校の一つである。私はこの高校で3年間を過ごし、校内・校外に何人かの友人や恩師を得た。その中でも、格段に面白い人物の数人を紹介しながら、織田が浜の話しを続けるが、その前段階の小中学校時代にも少し触れる。
「しまなみ海道」開通以降、いくらかは全国的に知られるようになった、芸予(げいよ)諸島の最も今治寄りの大島の漁村で生まれ育った私は、小中学校を通じて、先生の顔色を見るに聡く、後輩をいじめず、通信簿は5で覆われるなど、所謂(いわゆる)優等生の見本みたいな少年だった。思春期を迎えた頃、自己流の空手を始めたこともあって体躯は劇的に変化するのだが、13歳あたりまでは細く長く、しばしば原因不明の熱を出して学校を休む。しかしそれで特段身体が弱いというわけではなかった。
生家と庭続きのような砂浜と海は、単に海水浴だけでなく私の遊び場そのものだったから、年間を通して村の子供仲間たちと一緒に走り回り、夏は泳ぎ回って、年中日焼けがとれないような小学生だった。
ところが、元職業軍人で後に政治家になった父の口癖が「信念と努力!」、教育方針が「何でも一番になれ!」などという、普通の人間にはおよそ不可能なもので、それを忠実に実行しようとしていたから、私はかなりの無理をしていた。その無理が「原因」となり、何かの「縁」に触れることで、「結果」となって現れるのは時間の問題にちがいなかった。
私の高校時代は、この「縁」が「果」を生み、その「報」(因縁果報)が現れ始めた時期であったとも言えるだろう。もちろん、父の信念や母の愛育がマイナスの「報い」のみを生んだわけではない。
彼の信念の内容が如何様(いかよう)なものであり、何処(いずこ)に淵源を持つのかは今のところ定かではない。しかし、家族に耳の聞こえない者がいたこと、向学心に燃えた相当に聡明な少年が、寒村漁家の貧しさの故に職業軍人への道を選ばざるを得なかったこと、16歳から26歳までの10年間の海軍生活で、文字通り命懸けで鍛え上げられた何か。それらが、社会的に弱い者への思いやりや、理不尽に強い者への怒りを、彼の中で成熟(じょうじゅく)させたのは確かなようである。
その信念は、戦後、私が生まれた直後のまだ30代半ば、当時全国的に報道された燧灘(ひうちなだ)の漁業権を巡る紛争で現れたのだろうし、その後、政治の世界では、多くの敵を生むと同時に、それ以上の理解者を得ながら、4期16年間の仕事を全うさせたのだろう。当然ながら、それらの方々の中には、実にさまざまな種類の人々が含まれていたのを、私はよく知っている。
「何でも一番!」は、ある意味とんでもない間違いだが、長ずるに連れ、私がこの世界や人間の観方(みかた)を扱う「思想・哲学」や、それらの根っこにある「信の体系=宗教」に興味を持つようになるのは、自然な流れだったのだろうと思う。
信念とは「何ごとかを信じる一念」のことであり、一念とは「一つの今の心」と書く。意識的・無意識的に何ごとかを信じるということは、詰まるところ宗教の領域になる。それは人間に限ったことではない。インドの詩人・タゴールが、森に在って「静かに!心よ。樹々(きぎ)たちは天に祈りを捧げているのだ」と謳ったのも当然だろう。
樹木は大地を信じ、魚は海洋を信じ、鳥は大空を信じ、子は親を信じることで、その分に応じて成長しながら生きている。また更に、現在の一瞬の心の連続が、一個の人間だけでなく全ての生命の一生涯を超えて永遠に続く、と仏法では説く。
樹木は大地を信じ、魚は海洋を信じ、鳥は大空を信じ、子は親を信じることで、その分に応じて成長しながら生きている。また更に、現在の一瞬の心の連続が、一個の人間だけでなく全ての生命の一生涯を超えて永遠に続く、と仏法では説く。
そして、「何を」信じ行うか・・・が、自己の心身にどれほど大きな影響を与えるかを、強烈に体験するのは、高校時代も終盤になった頃であるが、このあたりのことごとは、稿を別にする。
また、高等女学校を出て父の妻となった母の愛育については、いまだに進行中なので、簡単には相対化することはできない。ただ、「小さいことは気にしない」ということや「大概のことはなんとかなる」などという脳天気な性格は、大いに母親譲りである。
★★★
ある日、西川が「おやじさん、ちょっとついてきてくれないか?」と言う。今治の京町という、東京だと歌舞伎町みたいな場所にあるバンドの練習場で、ときどき近在のチンピラが言いがかりを付けてくる、ということらしかった。
バンドメンバー数名と共にその練習場に行くと、たしかに「私は間抜けなチンピラです」と顔で語っている男たちが2~3人いた。そして、しばらく遠巻きに私たちを眺めていたが、私が拳を鳴らしている間にどこかに行ってしまった。たぶん、それから顔を出すことはなかったのだろう、私の用心棒役はそれっきりである。
その後、何かの大きなイベントがあった夏の「織田が浜」で「ロング・ビーチ」は活躍し、西川・作詞作曲のエレキ演奏は、かなりの数の観客を喜ばせた。その時、大三島から手伝いに来ていた少女と、朝日が昇るまで何ごとかのお話をしたこともよく覚えている。
これに味をしめて、「うちの島でもやるか~・・・!」などという企画を持ち上げ、島の公民館の大広間を無料で提供してもらい、町内放送までしたにもかかわらず、来たのは中学時代の同級生10人足らず・・・なんてことも、西川を友人に持ったおかげの楽しい出来事の一つだ。その後、彼は立教大学に進み、学生でありながら音楽関係の事務所を持った。それなりに人徳のある奴だったということだ。「あずさ2号」をヒットさせた「狩人」という兄弟歌手二人も彼と懇意だったらしい。彼との交際は私が新宿を去って神奈川・川崎の奥地に転居するまで続く。
西川に加えて、次回登場することになる、面白すぎる矢野君、優等生ソノモノのまま東京大学に進んだ石川君、後もう一人(あいつ誰だったかな?)の五人で、冬の歌舞伎町で小コンパ(飲み会)を開いたあたりからが、「織田が浜」の話の伏線になるのだが、今回はこれまでにする。
★★★
かくして、難なく高校に進学した私は、意気揚々としていた。島から街に出るということは、当時の島の子供にとって、冒険か事件のようなもので、小学生の頃は「今治行き計画書」みたいなものを母に提出し、500円の旅費を遠慮がちにもらう。年に1回あるかないか。中学になると新聞配達で月5000円は自由に使えるお金ができ、財布が空になるまでの数回程度だったのだから、あの対岸の大きな街の大きな学校の近くに下宿できるということが、どれほど嬉しかったことか。
入学後間もなく、中二の冬から自己流で始めた空手の腕を磨くべく、「どんどび」近くの警察道場に通い始めた。そこでは、どんな反則技を使っても、とうてい勝てそうもない20代後半の青年が剛柔流の師範代をしていた。下宿から道場まで往復40分ほどの商店通りを、週に何回か鉄下駄をガラガラ鳴らしながら通う。お店の方たちはさぞ迷惑したろう。私は大まじめだったのだが、今に想うと漫画の風景だ。
「盲(めくら)蛇に浮カず」そのものの少年の話は、いつの間にか学年中に広まり、やがて私に「おやじ」とあだ名を付けて、用心棒にしようという、これまた相当に面白い同級生が現れた。後に登場する「西川」(彼には君を付けたことがない)だが、先に少し触れておくと、彼が街の音楽仲間を集め、リーダーとして作った、エレキバンド「ロング・ビーチ」の(お金の計算ができない)マネージャー兼用心棒役をしばらくしていたことがある。私は音楽オンチだが音楽自体は好きらしい。ロング・ビーチとはつまり、織田が浜・唐子浜と続く数キロに及ぶ美しい海岸のことである。
「盲(めくら)蛇に浮カず」そのものの少年の話は、いつの間にか学年中に広まり、やがて私に「おやじ」とあだ名を付けて、用心棒にしようという、これまた相当に面白い同級生が現れた。後に登場する「西川」(彼には君を付けたことがない)だが、先に少し触れておくと、彼が街の音楽仲間を集め、リーダーとして作った、エレキバンド「ロング・ビーチ」の(お金の計算ができない)マネージャー兼用心棒役をしばらくしていたことがある。私は音楽オンチだが音楽自体は好きらしい。ロング・ビーチとはつまり、織田が浜・唐子浜と続く数キロに及ぶ美しい海岸のことである。
ある日、西川が「おやじさん、ちょっとついてきてくれないか?」と言う。今治の京町という、東京だと歌舞伎町みたいな場所にあるバンドの練習場で、ときどき近在のチンピラが言いがかりを付けてくる、ということらしかった。
バンドメンバー数名と共にその練習場に行くと、たしかに「私は間抜けなチンピラです」と顔で語っている男たちが2~3人いた。そして、しばらく遠巻きに私たちを眺めていたが、私が拳を鳴らしている間にどこかに行ってしまった。たぶん、それから顔を出すことはなかったのだろう、私の用心棒役はそれっきりである。
その後、何かの大きなイベントがあった夏の「織田が浜」で「ロング・ビーチ」は活躍し、西川・作詞作曲のエレキ演奏は、かなりの数の観客を喜ばせた。その時、大三島から手伝いに来ていた少女と、朝日が昇るまで何ごとかのお話をしたこともよく覚えている。
これに味をしめて、「うちの島でもやるか~・・・!」などという企画を持ち上げ、島の公民館の大広間を無料で提供してもらい、町内放送までしたにもかかわらず、来たのは中学時代の同級生10人足らず・・・なんてことも、西川を友人に持ったおかげの楽しい出来事の一つだ。その後、彼は立教大学に進み、学生でありながら音楽関係の事務所を持った。それなりに人徳のある奴だったということだ。「あずさ2号」をヒットさせた「狩人」という兄弟歌手二人も彼と懇意だったらしい。彼との交際は私が新宿を去って神奈川・川崎の奥地に転居するまで続く。
西川に加えて、次回登場することになる、面白すぎる矢野君、優等生ソノモノのまま東京大学に進んだ石川君、後もう一人(あいつ誰だったかな?)の五人で、冬の歌舞伎町で小コンパ(飲み会)を開いたあたりからが、「織田が浜」の話の伏線になるのだが、今回はこれまでにする。
(その3につづく)
今はあの潮音静かだった渚もコンクリートの塊になってしまった。前方に燧灘と四国山脈。

越智郡吉海町立津倉小学校の風景(昭和40年代のころ)。現在は今治市立。
今はあの潮音静かだった渚もコンクリートの塊になってしまった。前方に燧灘と四国山脈。

越智郡吉海町立津倉小学校の風景(昭和40年代のころ)。現在は今治市立。











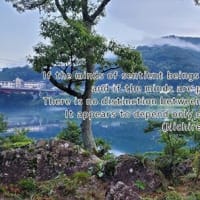
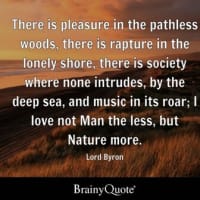
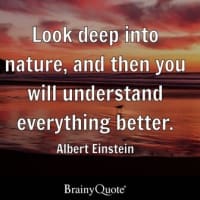







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます